常識をもって相対論を考え直す:森野正春氏
この章で述べている事はただ一つ。
『時計が遅れるというような事は常識的に有り得ない』
ただ、それだけです(^_^;)。相対論は未だに理解されておらず、かつ、質問する事すら許されていないのだと力説されております。そして、相対論で出てくる遅れた時計とは狂った時計の事だと述べています。そして最後には、時間の遅れというのは、物理学者も哲学者も説明出来ないと述べています。
内容的にはそれだけであり、相対論の物理的矛盾を突こうという考察は全くないので、本コンテンツで議論する話題ではないでしょう。まあ、題目が常識でもって相対論を考えるという事なので、それはそれでいいと思いますが。
1つ、引用しますと、
多くの人々がこの理論の魅力にひかれて、物理学者の書いた解説書を長い間、熱心に読んできたのですが、まだ誰もこの理論を理解し納得できないでおります。
とあります。“誰も”というのが物理学者以外を指すのでしたら、
日本には沢山の物理学者がいることになりますね(^_^;)。
ただ、知ろうとする気持ちを挫くような解説書(?)があるとすれば、確かに改めるべきではありますから、著者の主張である、
学問というものは理解することが大切なのではないでしょうか。
には全面的に賛成致します。
相対論は崩壊する:窪田登司氏
[前著への反応]と[読者の便りを分析する]
著者への反論は、「学校で教えているから正しいのだ!」というような感情的なものだったという事です。これが本当なら、確かに著者の『問題提起』は有用だったと言えるでしょう。内容が正しいか正しくないかは別にして…。
[アインシュタインと著者の考え方の違い]
この部分で著者の立場が明確になっているので、反論がしやすいです。大抵のこの手の本は、自らの立場が明確でない場合が多く、反論のやりようがない事が往々にしてあるので助かります。
アインシュタインの立場と著者の立場を箇条書きに分けてみます(ただし、重力や加速度運動のない、慣性系での論議)。
| アインシュタイン | 窪田登司氏 |
| 光は誰がどのような速度で見ても一定速度である。 | 光は一度空間に放たれると観測者の運動とは切り放されて無関係になる。よって、観測者の立場によって光速度も変わる。 |
| 等速度運動しているロケット内部では、外を見ない限り、自分が運動しているのかどうか分からない。 | ロケット内部で光を飛ばすと、ロケットが動いているか否かで光速度が変化するために、ロケットの動きが検出可能。 |
| 光をロケットから、横の方向に飛ばすと、ロケットが動いていようがいまいが、真横の壁にぶつかる。 | 光をロケットから、横方向に飛ばすと、ロケットが動いていた場合は、光が後ろの方へ流されていってしまう。 |
となります。著者の考え方は、『相対論以前の段階にまで、物理学を戻せ』と説いているように、なるほど、19世紀半ばの理解です。そして丁寧にも、著者自身がどちらが正しいかの検定方法を書いてくれています。さらに、もしアインシュタインの仮定が正しければ、相対論は正しいでしょうと述べていて、中々潔いです。それだけ自信があるという事でしょうか?
では、その実験方法を述べましょう。
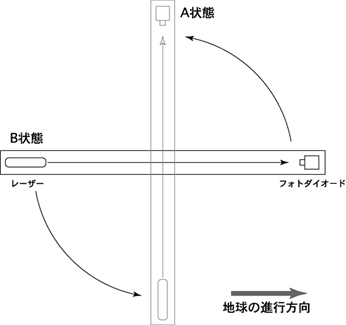 装置は長い板とレーザー装置、そして、受光するフォトダイオードです。要は、長く飛んでも拡散しない光源と、光を感知するものがあればなんでもいい事になります。
装置は長い板とレーザー装置、そして、受光するフォトダイオードです。要は、長く飛んでも拡散しない光源と、光を感知するものがあればなんでもいい事になります。
著者の主張によると、光源を出た光は、真っ直ぐ飛び、装置の運動によって受光部への到達位置が微妙に異なる事になります。Bの状態の場合は、光は受光部へ真っ直ぐ到達しますが、Aの状態の時は、地球は太陽の周囲を約30km/sで動いているので、光が受光部のある部分に到達した頃には、受光部が移動しているため受光部の少し後ろへ流されて到達するという主張です。光は秒速30万kmのため、板の長さ(=レーザーと受光部の距離)が10mだとすれば、AとBとでは、光の到達点が1mm程ずれるであろうという結論になります。
また、これは著者自身も書いていることですが、地球は太陽の周りを公転している以外に自転もしていますし、太陽系全体や銀河系全体も動いています。宇宙全体を考えれば、宇宙背景放射に対する太陽系の運動が分かっており、350km/sという速度で動いていますから、これを採用するのがもっとも妥当だと思われます。なお、銀河に対する太陽系の動きや銀河自身の銀河団に対する動きも、数百km/s程度の速度です。そうすると、板の長さが10mなら、光の到達点は1cm程ずれてもおかしくありません。
著者の説明は明快であるし、主張もはっきりしております。ところが、何故この実験を自分自身でしようとしないのかが分からない。
ただ一言、
これはレーザー光線を使って実際に実験してみれば分かることなのですが、なかなかやろうとするグループがありません。
と書いてあるだけです。また、「教えてガリレオ!」というTV番組でこの実験をやろうとしたプロデューサーの弁によると…、
「物理学者に相談すると一喝の元に、相対性理論は間違っていないから、そんな実験は無意味だ! と言われ、実験にはこぎつけられません」という返事で没になってしまいました。
ということです。そんな返事をする物理学者の顔が見たいものですが、根本的に、
何で物理学者や、他のグループに頼るの?というのが疑問です。
この実験は、数万円で出来ます。第一、半導体レーザーなんてそこらじゅうに溢れているので、わざわざ“半導体レーザーを使って研究している機関”に実験を依頼する事はありません。そもそも、依頼して、そんなズレは出なかったと答えが返ってきたとしても、物理学者を信用していない著者なんですから、物理学者が実験データに細工をしたとかなんとか言うのがオチだと思いますが…。文具屋(?)でレーザーポインタを買ってくればよろしい。安いものなら数千円です。10mの板の設置は多少困難ですが、体育館程度の場所を借りれば問題ないので、なんとかなるでしょう。
もしも、この実験をするにあたって、物理学者は信用ならないが、一人でやるには精度的に困難だというのならば、良い方法があります。大工さんか建築士に頼みなさい。レーザーを使った機器はその精度と簡便さにより、測量の分野に確実に浸透しています。例えば、レーザー水準器や、レーザー墨出し器なんてものが日常的に使われているのです。墨出し器なんて、昔は墨を塗った糸をピンとはじいて、柱とかに直線を描いていたもので、一軒家を立てている現場とか行くと必ず置いてありましたが(カンナやノコギリと違って、家庭では見慣れないから目につく)、今はこれがレーザー機器に置き換わっていて、水平、垂直、直線出しに使われています。
最近では、欠陥住宅の調査等で使用され、TVでもちょくちょく出てます。昔ならば、家が傾いていることを示すのに、ゴルフボールやビー玉を転がしましたが(まあ、今でも演出としてはありますが)、今は、レーザー水準器を床に置いて、クルクル回して水平を調べ、「ほら、この部屋は6mで2.5cmも傾いていますよ」「あら、怖い」みたいな…。
現物は、タジマツールの とか、大昭和精機の
とか、大昭和精機の とかどうでしょう、お客さん。前者はドムみたいで中々でしょ。共に10m先で1mm以下の誤差で測れます。板を180度回転させれば、30km/sの動きを考慮すれば、2mmの変化が出ますし、350km/sならば2.3cmもズレます。このレーザー墨出し器で十分に実験出来ます。また、板を回転させなくても、12時間たてば地球が自転するので、回転させたのと同じ状況になりますから、やはり、2mm〜2.3cmの変化が出るかどうかが分かります。
とかどうでしょう、お客さん。前者はドムみたいで中々でしょ。共に10m先で1mm以下の誤差で測れます。板を180度回転させれば、30km/sの動きを考慮すれば、2mmの変化が出ますし、350km/sならば2.3cmもズレます。このレーザー墨出し器で十分に実験出来ます。また、板を回転させなくても、12時間たてば地球が自転するので、回転させたのと同じ状況になりますから、やはり、2mm〜2.3cmの変化が出るかどうかが分かります。
…ていうか、この墨出し器を使って建築物を立てたとして、著者が言うようなズレが日常茶飯事で出ていたら、世の中、欠陥住宅だらけになってしまうのですが…。
その他、心配しても仕方ない話ですが、レーザーに著者の言うようなズレがあったとしたら、レーザースポットで照準を付けるライフルなどは使えませんね(^_^;)。100m先の標的を狙うのに±20cmも狂ってしまってはお手上げです。例えば、ゴルゴ13では、北半球での仕事の後、南半球での仕事を請け負う時、コリオリ力によるズレを修正するため、銃身の微調整を銃の修理屋に依頼する場面が出てきますが、スナイパーは、コリオリ力の補正云々を考える以前に現在の地球の位置を常に把握し、エーテルの流れを知っておかねばならなくなってしまいます。
[アインシュタインの二つの仮定の矛盾]
冒頭にこのような記述があります。
アインシュタインは特殊相対性理論を作るに当たって、二つの仮定を置いたことは、再三述べてきましたが、これらの仮定は、じつは相反している要請であることは、多くの科学者はすでに承知しています。
・・・ 中略 ・・・
もう一度念のため二つの仮定というのを記しておきますと、光の速度はどんな観測者から見ても一定だとする<光速度不変の原理>と、光は物体と同様にガリレオの相対性原理に従う運動をする、というものです。
この2つは確かに相反しています。
そもそも特殊相対論はガリレイ変換を捨てた理論ですから、著者の認識そのものが間違いです。
ただ、後の文脈に、アインシュタインはこの2つを繋げるために、ガリレイ変換を捨ててローレンツ変換を作った(採用した)という著者の正しい解説もあります。前著ではこのような記述は見られなかったため、少しは学んだようです。もっとも、それ以外の主張は変わっていませんが(^_^;)。
また、前著の時も著者が主張しておりましたが…、
もしアインシュタインがこの世にいなかったら、相対性理論は間違いなく生まれていません。
と、ここでも力説し、当時26歳であったアインシュタインが、数学的に幼稚だったというような説明をしており、今の世ならば到底受け入れられないものであると主張しています。アインシュタイン以前に
式の上で相対論を完成させていた人々が大勢いる事を著者はいまだに知らないようです。ローレンツ変換を考えて発表した人(不完全なものもありますが)を、発表年と、当時の年齢と共に書き出してみますと…、
| フォークト | 37歳 | 1887年 |
| フィッツジェラド | 38歳 | 1889年 |
| ラーモア | 41歳 | 1898年 |
| ポアンカレ | 44歳 | 1898年 |
| ローレンツ | 39歳 | 1892年 |
| アインシュタイン | 26歳 | 1905年 |
となり、アインシュタイン以前にも先人が沢山いました。アインシュタインがこの世にいなくても、特殊相対論は数年もしないうちに登場したであろう事は容易に想像できます。詳しくは前回の時も書いたので割愛します。
[ガリレオの相対性原理とマックスウェル電磁理論]
ここで著者は、マックスウェルの電磁気学で登場する光速度一定を、アインシュタインがどのような考察をしてローレンツ変換を導出したかを述べています。この部分は正しいようです。ただし、その変換式に物理的意味は無いとしています。
理由は、『光速以外の何かの速度ωを発見したとき、それはいかなる座標系でも不変であると仮定すると全く同じ論理展開ができる』からだそうです。確かにその通りですが、そうだとして、なぜ変換式が無意味なのでしょうか?
光でなくても、座標系によらない一定速度のものが登場すれば、それを記述するためには必ずローレンツ変換にぶつかるという正しい主張を著者はしていながら、ローレンツ変換を仮定から作られた虚構の式とします。いや、『仮定から作られた式』という主張も正しい。光速度不変という仮定があったればこそ、この式が作られたわけですし、だからこそ、その後、光速度を精密に測る実験が繰り返されたわけです。
何故著者がこれを虚構とするかというと、著者本人は座標によって光速度が変化するという仮定に立脚して理論を組み立てているからです。この勝負、実際の検証実験がなければどっちもどっちです。もちろん、光速度が、光源の動きや観測装置の動きがあったとしても一定であるという事は既に実験によって何度も確かめられておりますので、著者の仮定の方が間違いなのは実証済みではありますけれども。
[マイケルソン・モーレーの実験について]
著者の主張の中心部はこの節にあります。ただ、前著で主旨のほとんどは述べてあり、それについての反論も既に述べてあるので、軽く解説します。
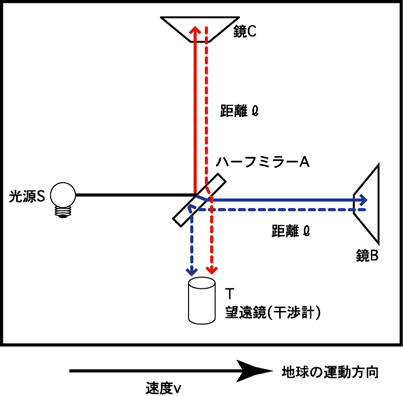 マイケルソン・モーレーの実験は何度も出ています。ABとACの距離は同じとして、光がA→B→Aと進む場合と、A→C→Aと進む場合とで、時間的なズレがあるかどうか調べる実験です。
マイケルソン・モーレーの実験は何度も出ています。ABとACの距離は同じとして、光がA→B→Aと進む場合と、A→C→Aと進む場合とで、時間的なズレがあるかどうか調べる実験です。
A→B→Aの方は、光の速度c、地球公転速度v、距離AB=AC=Lとして、
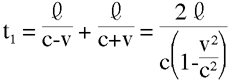 …式1
…式1
がでます。著者もこれは書いていて、
『これは光速度が見掛け上、行きは(c-v)に、帰りは(c+v)になっていることと同じです。』
と述べています。ここには異存ありません。まあ、しいて言えば、これは装置そのものが動いていると見る慣性系から見た表現だという事です。
次に、A→C→Aの場合ですが、AからCへ、あるいはCからAへ行く間に装置が動いてしまうので、
『AからCに向けて発射した光は、飛んで行っている間に鏡Cは右方向に動いているので、本当は反射しないはず』
と著者は書いています。確かに、装置が地球と共に動いている事を観察する系から見て、真っ直ぐ上に光を出せば鏡Cにぶつからない事もあるでしょう。装置が止まっていると見る系では、光は最初から後ろへ逸れていくようにセットされていると感じます。
そこで、少し右前方に光を出します。著者によるとあらかじめそっちの方向にうまく反射するようにセットする必要があるという事ですが、実際には自動的にそうなります。このことは、シンクロトロン放射などで既に確認済ですし、前著の反論の時に詳しく説明しましたので割愛します。
著者の主張には、レーザー光は地球の動いている向きによって到達ポイントが狂うというものがありますから(地球公転速度より、10mで1mmずれる)、首尾一貫して間違っております。著者自身の考えに内部矛盾が無いのが救いと言えば救いです…。
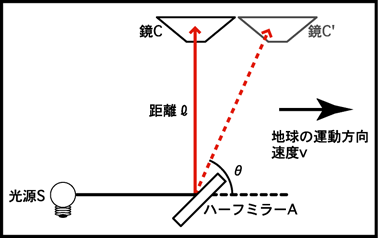 具体的に、A→Cに行くには、装置が動いているとみる系において、A→C'に行くという事です。A→C'→Aの往復にかかる時間はピタゴラスの定理により、
具体的に、A→Cに行くには、装置が動いているとみる系において、A→C'に行くという事です。A→C'→Aの往復にかかる時間はピタゴラスの定理により、
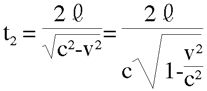 …式2
…式2
です。式1と式2では分母にルートのあるなしの違いがありますから、これが検出されるとして実験がなされたわけです。著者はこれに対し次のように反論します。式1を出す場合は、行きの光速度は見掛け上(c-v)であって、帰りは(c+v)だとしたのだから、今回も見掛けの光速度c-vcosθを使うべきであると主張します。もっとも、この式は計算の過程で出てきており、いきなりは使われていませんが、結果的に同じです。詳細は後述します。
前回の反論の時にも述べましたが、これはドップラー効果を示す時によく使う近似であり、特別な発想ではありません。この式について著者に多くの質問があったそうです。今回著者はp132にこの説明をしていまして、確かにドップラー効果の話をしています。
実は私は、この部分に質問が集中したという点に少々ショックを感じています。すなわち、前著の説明を見て、『ああ、これはドップラー効果を導く時によく使われる近似だね』という事に気付かない読者が多数いる事に他ならず、少なくとも高校で習う物理の範疇でのドップラー効果の話が身についていない事になるからです。もっとも、高校で物理を取らなかった人も多いのでしょうけども…。
余談ですが、この本に出てくる読者の反応(あるいは著者が尋ねた物理学者の反応)というのは、著者の言う通り、あまり的を射た反論とは言えません。そういう反論ばかりを著者が選んだのかも知れませんが、まともな反論は著者の耳に達していないのかもしれません。ちょっと心配です。
さて、見掛けの光速度をc-vcosθとするという時点で「これはドップラー効果の時の近似だ」と気付いたとしたら、後は著者の主張の間違いを指摘するのはそんなに難しくはありません。ドップラー効果を述べる時のこの近似がどういう前提の元に近似されているかが分かっていれば、簡単です。それは、短時間のうちにθが大きく変わらないような時…言い換えれば、ACとAC'がほとんど変わらない場合の時に使える近似です。
確かに、ACとAC'は、マイケルソン・モーレーの実験でもほとんど同じで、θは僅かしか変わりません。ほとんど同じだからこそ干渉計を用いて苦労したわけです。しかし、このほとんど同じ部分の差を測定するのがこの実験の本質なのですから、その差を無視する近似を使って計算する式が使える筈がありません。
例えばもしこれが、次のように分かりやすい間違いだったらどうでしょう。
【y=xという関数と、y=x0.5という関数がある。xが1付近だったらどちらの関数の答えも1に近く、そんなに差はない。だから、x=x0.5として差し支えないだろう…】
要するに、今問題としているのは、この差がいかほどかを議論しているのであって、これを無しと見なすような近似をしたら意味がないのです。
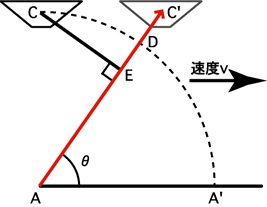 左図を見て下さい。まず求める部分というのは、AC'間の距離です。これをアインシュタインは、ピタゴラスの定理により、
左図を見て下さい。まず求める部分というのは、AC'間の距離です。これをアインシュタインは、ピタゴラスの定理により、
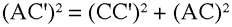
としたのです。これは厳密にそうであって、近似ではありません。著者の使用した関係は、AC'を2区間に分けて、
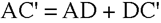
とします。ADは、ACと同じ長さです(CDA'を繋ぐ点線はAを中心にして描かれる円の一部)。そして、DC'を求める時に、近似vt2/2cosθを使います(CC'がvt2/2です)。厳密には、この長さはEC'ですね。
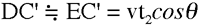
つまり、AD+DC'を求める時に近似して、AD+EC'を使ってもいいじゃないかというのが著者の主張です。この時、ED分だけ距離が余計に加算されますが、これによって、式2が式1の近似解へと変化するのでした。
すなわち、t2<t1となるべき式が、t2を出す段階でEDという距離だけ余分に走らされる近似式のためt2+(ED)/cという時間になり、t1=t2+(ED)/cが成り立つ事になる。そして、(ED)/cは、無視しても影響ない誤差だから、t1=t2としてもいいだろうと著者は主張しているわけです。そもそも、ピタゴラスの定理を使った厳密解を近似解に直してまでそちらを採用するという話自身、かなり脱力なんですが…。
さて、窪田氏の話はまだ続いていますが、前著とほとんど主張は同じであり、間違い方も同じです。例えば、[同時の相対性]の話で、
たとえば、列車の中央にいる人Dは列車の両端B、Cから同時に発した光を受ける。しかし、大地の人Aは列車の進行方向の先端Cから発した光の方が先にDに届いたと主張する。すなわち列車内で同時である事象が大地の人にとっては同時ではないのである。
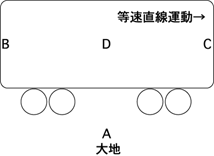
という風に同時の相対性が書いてあるとして、これを攻撃していますが、
この説明なら私もNOと言います。この説明は明らかに間違っているからです。著者は、『相対論を正しく理解してないので、こんなふうになってしまった』と述べていますが、私もその意見に
賛成です。
正しくは、
列車の人Dも、地上の人Aも、Dへは同時に光が届いたと見るのが正解で、
ただしBとCの光の発射時刻は、AはBが早いと主張し、DはB、C同時と主張するとならねばなりません。
この間違いはNHKの
アインシュタインロマンでも放映された間違いで、後の
再放送でこっそり直されていたという、いわく付の間違いです。こういう主張が堂々と載っている本は、早く訂正されるべきだと私も思います。
エーテルと新しい非対称重力理論:早坂秀雄氏
本が出る前に指摘していましたが、早坂氏の右回りのコマは軽くなるという実験に対する反証実験についての記述は一切ありませんでした。それどころか著者紹介の部分に次のような記述もあります。
世界で最も権威ある米国の物理学専門誌『フィジカル・レビュー・レターズ』(1989年)に発表した「右回転ジャイロによる重力減衰の効果」の実験はニュートンの万有引力の発見に匹敵するといわれ,今後の追試実験が世界中で注目されている。
もっとも、この部分は著者本人が書いたのではないでしょうが、どちらにせよ、認識が甘いものです。反証実験は既に何件も行われています。「もしかすると著者本人が反証実験の事を知らないのではないか? それだったら仕方がない事かも?」と思うかも知れませんが、それはまず有り得ません。
反証実験は著者が発表したフィジカル・レビュー・レターズに載っているからです。自らが投稿した雑誌での反響を、自らが見ないなんて事があるでしょうか?
具体的に、早坂氏が出した論文は、Phy.Rev Lett.63,25,2701(1989)に載っており、それは1989年12月18日号です。そして、既に次の号であるPhy.Rev Lett.64.8,825(1990)には反証実験が載っております。自らが出した論文の次の号に載っている反論を見ていない筈はないでしょう。もちろん、それ以外にもネイチャー等に反証実験が載っており、追試が成功したグループはなく、早坂氏の実験より精密な実験で、否定的な結論が出されています。
このような状況で『今後の追試実験が世界中で注目されている』と書くのはかなり恥ずかしい事だと思うので、早坂氏のためにも、是非書き換えてあげたら如何かと思います(本人が書いたのではない筈ですから)。
[エーテルを否定したマイケルソン・モーレーの実験と最近の実験結果]
まず著者は、現在の量子力学や一般相対性理論には“場”の概念は不可欠である事を述べています。これは確かに正しい…というよりも、どちらも“場”を使った理論なのですから。
ところが、その次に、
すなわち、空間は空虚なものではなく、「何か」が充満しているものとしている。その何かというのは、ダークマターか背景輻射か何か分からないが、いわゆる真空のエネルギーである。
という記述があります。どこからダークマターや背景輻射の話か出てくるのか? そして、何故それが
いわゆる真空のエネルギーになるのか分かりません。ダークマターや背景輻射というのは、空間の
上に置かれているもので、空間
そのものの性質とはなんら関係ないものです。
この手の誤解はちょくちょく見られるものですが、要するに、空間の性質の話と、空間の中に置かれた物体の性質の話とがゴチャゴチャになっているわけです。
続いて、最近のエーテル検出の話として、シルバーツースという人と、マリノフという人の実験を紹介しています。巻末に実験内容が載っているのですが、シルバーツース氏の論文は初っ端から面白い。まず最初に、光速度cは、振動数νと波長λから、

であると述べた後、光速度が変化する場合は波長λが変化し、νは変化しないとある。確かに、音波が空気中から水中に入るような時はそうなっています。そして、『マイケルソン・モーレーの方法では、光速度を測ることはできない』と述べるわけですが、この装置は光速度はエーテルに対して一定だとして考えられたものであって、λやνが出てくる幕はありません。もちろん、エーテルの濃い所から薄い所に出るような場合は別ですが、装置が同一のエーテルの中にドップリ使っているという設定では無意味な話です。
もしかすると装置が置かれていた場所では、たまたま東西方向と南北方向とでエーテルの密度が違う場所だったのかも(^_^;)。今ならこういう議論は笑い話になりますが、100年前は実際にそういう話があって、地下室ではエーテルが引きずられていたのだとか言われて、山のてっぺんで実験したりもされています。
[特殊相対性理論との関わり]
ここでは窪田氏と同様な意見が述べられておりまして、加速器での素粒子の衝突実験等の加速度運動を伴う現象に、特殊相対論のような慣性系に適応すべき理論で議論ができるのかという話をしています。
そして、
磁界によって屈曲された素粒子飛跡の時間の遅れなどに をどのように応用しているのだろうか。
をどのように応用しているのだろうか。
と述べられています。著者は東北大学の教授だそうですから、本に書く以前に、学生に直接聞いてみればいい。
原理は簡単で、慣性系の運動則というのは、速度一定(dx/dt=一定)の運動則でありますから、加速度が含まれる方程式に直したい場合は、それら方程式をもう一度時間微分すればよろしい。このあたりの事はニュートン力学でもお馴染みです。例えば、ニュートン力学での運動量mvから、力Fとの関係を
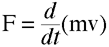
としたように、

とすればいいだけです。少なくともニュートン力学を変形できる人ならば、特殊相対性理論の、加速度運動への応用も楽にこなせます。
この手の変形は特殊相対論の入門で登場する部分ですから、「どのように応用しているのか」という疑問が著者にわくという点が不思議です。
ただし一般的には、特殊相対論は加速度運動には手も足もでないみたいな認識がありますから、物理に一度もタッチしてなく、自ら何も計算した事がない人が、ブルーバックスのような啓蒙書のみを読んでこのような疑問を抱いたというのならば、話は分かるのですが…。
くどいかも知れませんが、『特殊相対論を加速度運動をする物体にどのように適応するか?』という問題は、大学1年の教養問題レベルなのです。
次に、著者は、A.Aspectの実験について述べています。詳しくはE.P.R.パラドックスについて話をせねばならず、何度も出てきた話題ですので割愛しますが、要するに、1つの場所から分裂した2つの粒子は、一方の性質が決定されるとたちどころにもう一方の性質も決定されるという実験です。この『たちどころに』という部分が問題であり、この点を突いて著者はアインシュタインの特殊相対性理論は間違っているとするわけです。
著者の誤解は、一方の粒子の性質が決まった瞬間に何かその情報を伝える伝令粒子が他方へ飛んでいるというような感覚を持っているという事。アスペの実験は、このような隠れた粒子がない事を示したのであって、特殊相対論の話とはなんら関わらないのでした。
この実験の示したものは、古典的な局所的存在というものは存在していないという事の証明です。『たちどころに』収縮するのは波動関数であり、ある見えない粒子が光速度を越えて介在しているのではありません。
相対論とは関係なく、アインシュタインは局所的存在こそ全てという哲学を持っていたので、量子論の解釈としての彼の主張が誤りであったという事は言えます。著者はこの点を述べていて、それは確かに正しいのですが、そこから相対論の是非を云々するデータはありません。事実、このアスペの実験を通しても、有益な情報を光速度以上のスピードで他方に送る事はできないのですから。
著者はこのアラン・アスペの名前をそのままローマ字読みして「アスペクト」と称しております。名前がアランである事からも分かる通り、この人はフランスの人で、アスペクトとは読まないでしょう。実は、アスペの実験を相対論が間違っている証拠だと勘違いして日本に紹介した人が、人名読みも間違って伝えたようで、そのスジの人は、揃いも揃って「アスペクト」と呼んでいたりします。
[重力の非対称性]
冒頭で述べたように、著者の右回りのコマ実験は否定的追試実験結果が出ていて、それに対する著者本人の反論等は何も出ていません。ところが、この節では、
私の行っているジャイロによる重力変化の実験が正しいならば…
と、話を切り出しています。
間違っていると言われているのに、正しければこうなると力説しているのです。著者がまずやるべき事は、追試実験が何故否定的結果に終わったかを追及する事だと思いますが(まさしく、マイケルソン・モーレーのエーテル検出否定実験の時ように)。
という事でこの節の中身についてはいくら力説しても仕方がないものですが、重力の非対称性の説明として、カルタンの非対称場の理論を引用しています。カルタンの理論について私はあまり知らないのですが、著者の話を読むと、接続係数Γμνσの対称性の話らしい…。
確かに一般相対論では、Γμνσに対する対称条件、

を仮定しており、それを元に組み立てられています。
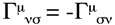
となるような部分を取り扱うには捩率という話が出てきますが、アインシュタインはこれを統一場理論に使いました。もっとも、統一場理論は完成しませんでしたが、こういうねじれを持った空間を考える理論は色々あるようです。
が、これがどうして重力の非対称性と結び付くかが分かりません。もっと詳しく説明を聞かねば是非は言えませんが、どっちにせよ、まずは実験の否定的結論を著者に論駁してもらわない事には埒が開きません。
相対論を打ち砕くシルバーハンマー:日高 守氏
[シルバーハンマーとは何か]
著者によると、シルバーハンマーというのは、理論が構築された後に発見される見落とされた関数の事だそうです。要するに理論構築の土台となった部分に単純なミスが見付かると、親亀コケたら皆こけたというように総崩れになるという事のようです。
まあ、確かにそうです。逆説的ではありますが、この本に書かれている“相対論は間違い”とする説は、著者の言うシルバーハンマーによって崩れているのですから(+実験事実の誤認もあります)。
[二〇世紀最大の発見]
この節で著者は歴史的な式E=Mc2が一般に知られているような重要な意味を全く持っていないとし、それを説明しています。実は、私個人も歴史的な意味という事から考えれば、当時はそれほど意味を持っていなかったのではないかと思っています(ただし、著者の主張とは全く別の考察からです)。第一、アインシュタイン自身も1905年9月の論文を書いた後、E=mc2についてあまり確信を持っていなかったようです。結局、ラジウム塩などを使った実験についての実験的考察をしており、実験で確かめられる事を期待していたフシがあります。
もっとも、1910年には、エネルギーと質量のが換算があまりに差があるので、当分の間は観測不可能だと思っていたようですが(三十数年後に原爆という判り易い形で検証されるとは思っていなかった)。
まず、E=mc2を最初に定式化したのはポアンカレであり、1900年の事でした。本書を書いた著者達は、一人を除いて異口同音に「相対論はアインシュタイン一人がデッチあげた」という主張でありますので、この当たりの話は知らないのかもしれません。前著の反論の時に、『アインシュタインがいなくても、特殊相対論は生まれていた筈で、それは多分ポアンカレによるものだろう』という主旨の事を述べたと思います。
ポアンカレのE=mc2導出の経緯はニュートン力学+マックスウェルの電磁気学的なものです。ポアンカレは光の質量について考えました。光についても、運動量p=mvが成り立つと仮定して、パルス的な光の質量を考えます。ここで、電磁場の運動量密度と関係のあるポインティング・ベクトルを使った運動量保存則を考え、p=E/cを導出し、m=E/c2としたのでした。
また、質量が速さに依存する(いわゆる相対論的質量)事を示したのは、ローレンツが最初で、1899年の事です。ローレンツはローレンツ変換を既に導いていたので、単なる式の変換で導出できたと思われます。ただし、ローレンツはあくまでニュートン力学の範疇で組み立てており、縦質量だの横質量だの色々と作ってまして、相対論が生まれる前後は、質量の定義が(静止質量を含めて)3つもあったようです(^_^;)。
さらに、電磁質量の話まで遡れば、エネルギーと質量が互いに変換可能だという考えは二十数年前まで遡れたりしますが、歴史的な事ばかり述べても仕方ないので、このへんで切り上げます。一応、このくらい述べておけば、E=mc2という変換式が当時、それほどユニークな考えではなかった事は分かるでしょう。アインシュタインのユニークさはもっと別のところにあります。
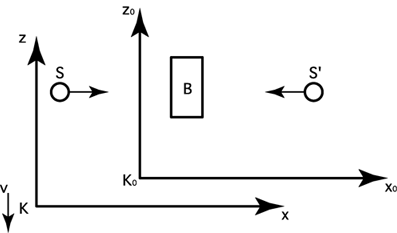 さて、それでは著者が指摘しているアインシュタインの論文(巻末資料2)について考えます。内容は次の通りです。
さて、それでは著者が指摘しているアインシュタインの論文(巻末資料2)について考えます。内容は次の通りです。
まず物体Bが空間に浮いており、そこに両脇から2つの光がやってきます。これが、SとS'です。この2つの光はどちらもE/2のエネルギーを持ち、最終的にBにぶつかり吸収されます。ぶつかった後も物体Bは、中央に留まりつづけたままです。ここまでは、K0系で見た時の話。
次に、K0系に対してz軸方向に負の速度vを持つ慣性系Kを考えます。この場合は物体Bはz軸正方向へvの速度で動いています。そして、2つの光SとS'は光行差現象により、角度α(=ほぼv/c)で上向きに角度を持ちながらBへぶつかるように観測されます。重要なのは次です。
K0系における考察から,Bの速度はSおよびS'の吸収のあとで変わらないことがわかる。
SとS'は共に運動量を持っています。それが角度αでぶつかっているのに、物体Bの速度は変化していないのです。
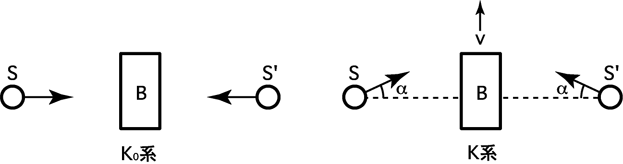
アインシュタインの考察を整理して書き出してみます。
| [その1] | K0系で見て物体Bは、SとS'が衝突した前も後も常に静止していた。このため、K系でみれば、衝突前も後も常に、速度vでz軸方向へ進んでいる筈である。 |
| [その2] | K0系でみれば、SとS'の衝突によって、これら2つの持つ運動量は相殺されるが、K系でみれば角度α(≒v/c)でBにぶつかっている。よってK系で見ると、相殺されないz軸方向の運動量が残る筈である。 |
| [その3] | K系でみたBの最初の運動量は、Bの質量をMとすれば、Mvである。その後、SとS'がぶつかった後、消え損ねた運動量は[その2]の考察から、
(Sの運動量+S'の運動量)sinα
である筈だ。 |
| [その4] | SとS'の元々の持っていたエネルギーをそれぞれE/2とすれば、マックスウェルの電磁気学から、それぞれが持っていた運動量はE/2cになる。そこで、sinα≒v/cという近似を使えば、Bに与えられた運動量は、
(E/2c + E/2c)(v/c) = Ev/c2
となり、元々のBの運動量Mvと併せて、
Mv + (E/c2)v
となるであろう。 |
| [その5] | 普通、運動量が増えれば速度が増す。しかし、[その1]の考察により速度vに変化は無かった。さてどうするか? 運動量は元々Mvであって、運動量が増えたのにも関わらずvが増えないのであるから、運動量保存則を満たすためには質量Mが増えたと見なす以外に方法がない。そこで、SとS'が衝突した後のBの質量をM'とする。 |
| [その6] | すると運動量保存則は、
Mv + (E/c2)v = M'v
となる。よって、
M'-M = E/c2
となる。今回増えた質量分はまさに、M'-Mであるから、増加分(M'-M)を新たにMとすれば、
E = Mc2とできる。 |
ざっとこうなります。
ちなみに、この巻末資料2には、短いのに2カ所もケアレスミスがあります。
1つ目は、本文上から8行目に出てくる座標系Kですが、明らかに座標系K0です。
2つ目は2ページ下から9行目のE/c2の運動量ですが、これはE/2cの運動量です。この短い論文の中に2ヶ所も誤植があるとは…。多分、アインシュタインのミスでも、訳者(の一人)の湯川博士のミスでもなく、単に活字をひろった印刷屋のミスではないかと勝手に想像していますが(でも、E/c2とミスるのは物理屋だよなぁ)。
ちなみに日高氏はこのミスに気付いて無く、運動量をそのままE/c2で使っています(以下参照)。式の変形や省略に過敏に反応する人なのに、ここを指摘しなかったのは何故なのでしょうか。
これに対する著者の反論は、
「物体の運動量Mvと輻射複合体S、S'の運動量(E/c2)を足すと運動量M'vになる」この仮想実験の結果はいったい何処から得られたのでしょうか。
・・・ 中略 ・・・
実はこの結果は実験データがないから仮定したものなのです。その仮定とは、「質量MにエネルギーEが吸収されたのち、質量M'に増加したと仮定する」というものです。
となっていて、最初から質量とエネルギーの等価性を記述した式だったとします。すなわち、最初から等価だとした式を使って、等価式を出しているだけだと…。
ある意味では、著者の主張はもっともだと思います。しかし、前述した[その5]の思考過程をみて下さい。運動量が増えて、なおかつ速度が変化していないという前提では、運動量保存則を満たすためには、質量が変化したと考えるのが一番妥当です。ただ、いきなりアインシュタインが、何のお膳立てもなく『質量が増加したのだ』などと述べても誰も相手にしなかったでしょう。そこで、冒頭に述べたような歴史的背景が重要になります。質量とエネルギーが等価になるという考えは、電磁質量の概念や光のエネルギーと質量の関係をポアンカレが考察していたように、特殊な前提の時には有り得るだろうという考えは既にあったのです。アインシュタインはそれを一般化したのでした。
著者の指摘は、この論文には観測や実験での事実の記載が一切なく、仮想実験だけで書いてあるので間違っているというものです。確かに、エネルギーを与えられると質量が増えるというような実験事実は当時ありません。だからこそその後の実験が必要だったのですし、実験結果の前に質量とエネルギーの等価性を見抜いたからこそ、アインシュタインの名が有名になっているわけです。
ただ、ここで出てきた一連の考察を考えると、質量を増やすのが一番もっともな選択である事は理解して頂けたのではないかと感じております。それとも、光が絡んだ場合は、運動量保存則は成り立たないと考える方を選びますか? もちろんそれも1つの方法ですし解決策ではありますが、後の実験によって否定される事になるでしょう。後世になってアインシュタインの選択が正しかったのが分かったのであって、論文が出た段階で正しいか否かは分からなかったのです。
なお、基本的な著者の誤り(意図的かも)として、ここで登場するアインシュタインの論文は1946年のものであり、後年になってからのものです(アインシュタインは、後年2通りの方法でこれを解いています。1934年の講演と、この1946年のものです)。
[それでも相対論?]
日高氏は数式の省略を許さない人で、見れば分かるから略していいだろうという部分があると間違いとして指摘します。この節では、著者のこの姿勢が露になります。例えば時間τを別の時間tと関連づけるとしてτ(0,0,0,t)と書いた後、それの時間微分として、

としてある部分に反論します。τ(0,0,0,t)の時間微分ならば、
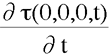
とすべきであろうと(^_^;)。その通りです。それはもちろんそうなんですが…なんと言うか、こういう突っ込みをされると凄く疲れそう。
話が前後しますが、著者は冒頭の一節にこのような文を書いています。
そういう私は相対性理論を疑ったことが一度もありません。まったく理解できなかったのです。なぜ間違った式を使っているのか。なぜ物理学者までもが小学生でもわかる数学トリックに騙されてしまうのでしょうか。
…多分著者のような性格だと、相対論だけでなく、他の物理理論も全く先に進めず、「何故間違った式を…」と連発する事になると思いますが如何でしょうか? これは
数学屋さんが見て、物理屋さんの使う数学がいい加減なので、少々気を悪くしているというレベルの話ではありませんよね。
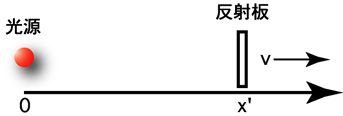 次に、光が時刻τ0の時にX軸に沿ってx'まで進み、τ1の時に反射し、τ2で原点に戻った時の事を考えます。ここで、装置と共に動く慣性系からみれば、
次に、光が時刻τ0の時にX軸に沿ってx'まで進み、τ1の時に反射し、τ2で原点に戻った時の事を考えます。ここで、装置と共に動く慣性系からみれば、
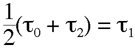
であるとできます。何しろ装置と一緒に運動していると見る系では、光源も反射板も止まっているのですから。
そして、今度は装置を動いていると見る系…すなわち観測者に対して装置はvの速度を持って動いていて、光源も反射板も動いているとします。その観測者のいる系の時間をtとし、τはtとその空間座標であるx,y,zを使って、τ(x,y,z,t)で表せるとします。そこで、上の式を『書き直して』、
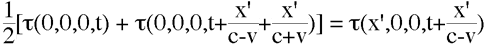
とアインシュタインはしています。著者はここにも反論します。ただ単にτ0,τ1,τ2を、一般的な関数としたτ(x,y,z,t)に書き直しただけの式に対し、
逃げる泥棒とすれ違うより追いかける方が時間がかかるように、運動している線分上を光が往復すれば復路よりも往路に時間がかかり、運動系の記述とは一致しなくなります。
と述べます。つまり、装置が動いていると見る系では、光源から反射板へ到達する時間の方が、反射板が速度vで逃げているので長くなり、反射した後は、逆に光源が近付いてくるから時間が短くなると説いています。
もちろんその通りです。
もし書き直した式が、装置を動いていると見る座標系として、
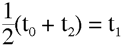
となっていたら確かに間違いですが、このような式はどこにも出ていません。すなわち、
著者の反論すべき式は、巻末のアインシュタインの6月論文の中には全く出てこないのです。著者はここで詰ってしまって、相対論の論文の先を見ていないようですが、これは単なる著者の勘違いだと思われます。
なお、復路は時間が短く、往路では時間がかかるという事実は、上述した式の

の部分がまさしくそれです。
次に、著者は、観測者が速度0、速度1、速度vで動く場合、極端には光に乗って光を見た場合に、その光速度は、
光速度不変ではすべてcと答える事ができます。あなたは? やはり運動している観測者の速度に関係なく光速度はcですか? それぞれのデータ、0や1、vやcはどうなったのでしょうか。それらをすべて無視しませんでしたか?
とします。声を大にして言いましょう。
無視はしていません。運動する観測者の速度を取り入れて、なおかつ光速度はcなのです。
この部分は、相対論を
信じている人の中にも多くの誤解を生んでいますので仕方がないかもしれませんが、光速度が観測者の動きは無視して常にcなのではなく、
観測者の動きを考慮してもcなのです。
速度v1とv2の物体があって、それぞれの上で相手の速さを見れば、相対論では、
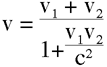
と算出されるので、v1をcとしてしまうと、v2が何であってもv=cとなってしまうのであって、決して計算していないのではありません。
相対論に反対する人だけでなく、相対論をブルーバックス程度でカジッた人でも光だけ特別としてしまう風潮があるために、このような間違った指摘がまかり通る事になります。もちろん経緯としては光速度不変が先にあって、それに合うように速度合成則が算出されたのですが、決して光だけが特別だとして扱っているわけではありません。
著者の主張している速度合成則は多分、
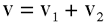 (ただし、0≦v<c)
(ただし、0≦v<c)
 (cには何足してもc)
(cには何足してもc)
というような、cだけを特別扱いしたものでしょう。相対論はそんな理論ではありません。
[マイケルソン・モーレーの実験について]
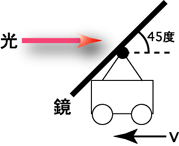 この本の中で、もっとも下らないと思われるミスはここにあります。
この本の中で、もっとも下らないと思われるミスはここにあります。
著者はマイケルソン・モーレーの実験の類似思考実験として、45度の傾きを持った鏡にぶつかる光を考えています。そして、鏡が止まっていれば(図のような場合)光は90度反射されて真上に届くとしています。ここまではよろしい。
ところが、鏡がvの速度で光に近付いたりすれば、光は真上では無くてナナメ前方に飛ばされるとします。つまり、著者は光をサッカーボールと同じようなものとして扱っていて、反射すると鏡の速度がベクトルとして加わると思っているようです。
マイケルソン・モーレーの実験は、エーテル内を飛んでいく光の波を考えていますが、波はそれを伝える媒質に対して常に同じ速度で動きます。反射鏡が動こうが光源が動こうが関係ありません。
このような、反射鏡による光の速度変化の主張を堂々と述べているのは、本書の中でも日高氏だけです。窪田氏もその他誰もが、少なくとも波としての光の性質だけは間違えていません(他の著者が指摘しているのは、エーテルに対して動いている観測者が見る光速度についてです)。この波の性質は中学校で習ったと思いますが…いや習わなくても水面の波紋を見れば誰でも理解出来る筈です…。
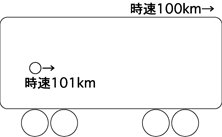 また、続いてこの著者の勘違いをさらに決定づける端的な思考実験もあります。マイケルソン・モーレーの実験で、エーテル流と平行に走る光の方の考察で、行きの光の見掛けの速度がc-vで、帰りがc+vとする部分に、著者は反論します。この部分に反論する人も、本書の中では日高氏だけだと思います。
また、続いてこの著者の勘違いをさらに決定づける端的な思考実験もあります。マイケルソン・モーレーの実験で、エーテル流と平行に走る光の方の考察で、行きの光の見掛けの速度がc-vで、帰りがc+vとする部分に、著者は反論します。この部分に反論する人も、本書の中では日高氏だけだと思います。
図のように時速100kmで走る列車があり、101kmで飛ぶボール(ここで既に波ではなく、物体を登場させている)があるとすると、列車内部では、101-100=1であり、時速1kmの速度のボールに見える。マイケルソン・モーレーの実験では、行きはc-vだからいいとして、帰りはc+vだから、この考えをボールに当てはめると、この計算は、
列車内で時速1kmで壁にぶつかったボールが反射すると時速201kmで跳ね返ると述べている!
と同じだと主張し、マイケルソン・モーレーの計算を間違いだとするのです。ここまでくるとさすがに目がテン(・_・;)になってしまいます。
船が時速100kmで航行していて、後ろから波が時速101kmでくれば、船上では、時速1kmで近付いてくるように見えますし、一旦反射して船と逆向きに走り出した波は、時速201kmで離れて行きます。
波なんだからそれでいいんです。
…ところで、この本には監修っているのでしょうか?
一般相対論と量子力学の概念的矛盾:竹内 薫氏
この章は他の著者のものと違って、
すごくまとも
です。どうして、この本の中に入っているのか不思議なくらいです。
内容は、一般相対論が繰り込み不可能であるために、量子力学と相容れない事や、空間や時間を量子化しようとした、スナイダーやヤンの話であり、短いながらも中々面白い小論です。また、宇宙背景輻射の赤方偏位が量子化されているかという議論など興味深い話もあります。やや、簡単な比喩が多すぎるので、もっと本格的なものも読みたくなりました。
しかし、他の論に混じってこういうのが入っているというのは、逆にビックリしますね。『まとも』な本が並ぶ本屋の列に、数冊ある疑似科学本という状況ならばよくありますが…。
時間と時刻を混同している相対論:石井 均氏
まず、著者の発想は、よくも悪くも理系的発想ではありません。他にうまい表現が見付からないのですが…。
昔、C.P.スノーという人が『人類には自然科学的文化と人文科学的文化の二種類があって、この2つは中々融合しない』と嘆いたそうですが、著者の文章にはそんな趣きがあります。
よって、著者の文章に対して、私が自然科学的発想でもって間違いを指摘するのも何か場違いな気もしますし(やろうと思えばいくらでも出来る文章なのですが)、著者がやっている人文科学的発想による相対論批判も、大いに的外れであります。ただ、こういう“的外れ”が悪いといっているわけではありません。それも人間の思考の一つの形態ですので…。
なにやら概念的な話になってしまいましたが、以下に具体例を挙げて見ましょう。
タイトルにもあるように、著者は時刻と時間を明確に区分します。その方法は、自然科学的発想で見られるような、「ある時刻と別の時刻の差を時間という」みたいなものではありません。
一時刻プラス一時刻は一時刻であり非数学的で絶対である。これに対して、一時間プラス一時間は二時間であり数学的で相対的である。このことから明らかなように真に絶対的時刻としての時間というものは非数学的でもある。したがってニュートンの考えている意味とは異なる意味において絶対時間(時刻としての時間)というものが現実に存在するのである。
と、このように著者は展開します。事実、著者は本文中でアインシュタインだけでなくニュートンの考えている絶対時間の考えも否定しています。要するに、時刻というのは非数学的なものであるというのが著者の主張です。また、
時刻というのは、どの系にも同時に存在する絶対的なものである。時間は時刻間の差である。ということは時間は絶対的なものであるとしなければならない。
という一文もありまして、ここでいう“絶対的”という表現は、著者の言う“非数学的なもの”でありましょう。だいたいの雰囲気が分かりましたでしょうか?
これ以上引用しても同じだと思いますが、著者は時間は数学では切り取れない絶対的なものだという主張からこれを書いているわけであり、物理的・数学的な間違いを突いているわけではありません。ですから、こういう反論の場合は「そうですか」と言う以外にありません。時間を数学で考えるなという事で門前払いをしているのですから。
人それぞれによって、何を“真理”としているかは違うので、これ以上“自然科学的真理”によって著者の文を追及することは止めます。
例えば、ゴッホやルノアールの絵画を自然として正しく描かれている“写真”とは異なっているので認めないというような主張は、誰だってしないのではありませんか? ちなみに著者は画家だそうです。
世界線の屈折と光速度不変の原理の見直し:馬場駿羣氏
[窪田氏の快挙]
この章は、前章の石井氏と同じような短さですし、数式も全然出てこない章です。ただし、著者の発想は完全に理系的発想ではあり、そこに書かれているのは単純に間違いです。こういう場合は、反論のしがいがあります(^_^;)。前章と本章の文を比べると、疑似科学と言われるものにも2種類ある事がわかり、大変面白いです。
例えて言えば、前者は全く異なった『宗教』を唱えているお坊さんであり、後者は『内容の間違ったお経』を唱えているお坊さんです。余計混乱する例えだったかな(^_^;)。
さて、本章の著者の特徴は、結構歴史的な事実に詳しく、途中までは正しい道筋を進んでいるのに、いきなり明確な理由もなしに間違っているといい出すという手法が多いです。
とりあえず、よくある勘違いとして、
現在、相対論とりわけ特殊相対論は物理学会ではほとんど宗教的信仰に近いレベルで一般に絶対的信望を得ているようではあるが、学者の中には相対論不信論者がかなりあるのも事実なのである。
と書かれています。
宗教的信仰というものがどんなものか分かりませんが、少なくとも特殊相対論が受け入れられているのは、実際にその理論を元にして作られた装置が動くからですし、逆にニュートン力学で設計した場合にはうまく動かないからです。
相対論不信論者がかなりいる事は結構な事です。まともな科学者ならばそうあるべきでしょう。常識を疑わなければ新しい発見はありません。彼等が相対論の穴を発見してくれる事を期待しましょう。しかし、混同してはならないのは、ある理論の穴を見付ける人というのは、その理論を熟知している人でなければならないという点です。
分かりやすくするために、相対論という部分を流体力学によって飛行機が飛ぶこととして考えてみましょう。
現在、流体力学によって飛行機が飛ぶということは物理学会ではほとんど宗教的信仰に近いレベルで一般に絶対的信望を得ているようではあるが、学者の中には、あんな鉄の塊が飛ぶ筈がないという主張がかなりあるのも事実なのである。
…要するに、実際に飛んでいる事をどう説明するかという点がごっそり抜けている訳です(^_^;)。
[ローレンツ収縮について]
ここで著者は、マイケルソン・モーレーの実験結果につじつまを合わせるためにローレンツがローレンツ収縮を導入した事や、その後の特殊相対論の登場で、それが事実として認められた事などを述べています。この部分は特別妙なところはありません。
次に著者は、ローレンツ収縮は実際に生じるものかあるいは見かけ上のものかという2つの意見があるとしています。確かにこれも、特殊相対論発表当時には混乱の元となりました。どうやらローレンツ自身は、晩年まで、空間の縮みという概念を理解してなく、物質の縮みに還元して話をしていたようです。もっとも、実際に理解していたのかどうかは今となっては分かりません。
著者は、ローレンツ収縮が実際に起こるとしている人として、ローレンツ自身とパウリの名を挙げています。そして、見かけのものとしている人として、ジェーコフとランダウを挙げています。パウリがどのような事に言及していたのか、私は知りませんのでこれについてはなんとも言えません。
ローレンツ収縮は空間の縮みですから、空間の上にある物体は、縮んでいるのが普通になります。ただし、表現として難しいのは、猛スピードで動いている物体が縮んでいるのを見る立場では、『相手が縮んでいるのは紛れもない事実』ですが、相手の物体に乗っている人がみれば、自分の乗っている物体は止まっていて、何も縮んでいないわけです。
なお、著者によると、この部分は、
ただし、特殊相対論では運動系と静止系とはあくまで相対的に取り扱われるので、こちらから見れば相手の長さが短くなり、向こうから見ればこちらの長さが短くなるという内部矛盾を抱えることになる。
と、
正しい認識をしているにも関わらず、一番最後でいきなり内部矛盾とだけ書かれていてその説明はありません。双方から見れば、相手の立場が違って見えるという事を矛盾というならば、普通のガリレイ変換の場合も、双方が
自分が止まっていて相手が動いていると感じるという内部矛盾を含んでいる事になってしまいます(^^;)。
矛盾というのならば、例えば「運動系から見ると、静止系の人は左右からの光を同時に見た筈なのに、静止系の人はそうではなかったと主張した」というようなものでなくてはなりません。特殊相対論ではそのような矛盾した帰結は出てきません(これを勘違いしたのが窪田氏です)。
さて、著者はローレンツ収縮が実際に生じるとして主張した人物に、窪田氏の前著で序文だけ紹介されて序文だけけなされた(^^;)スコベリツィン氏を挙げています(そういえば、森野正春氏の稿も、内山龍雄氏の書いた「相対性理論」の序文にケチを付けていた。序文はケチが付けやすいのかな?)。
紹介された問題は、2台の宇宙船が全く同一な加速をすると、その間隔は当然ながら常に同じなのに、2台を繋げたロープはローレンツ収縮によって切れてしまうという話です。この話は本当ですが、これをローレンツが主張した実際の縮みと混同している点に、著者の限界があります。
つまり、この2台の宇宙船の話と、ローレンツが述べた物体の縮みとは別のものです。
| ローレンツの主張 | スコベリツィン氏の2台の宇宙船 |
| 物体は、エーテルの流れる方向には、その圧力によって物体が縮む。縮み方は鉄でも綿でも同じでなければならない。なお、空間が縮むなどという概念はない。 | 宇宙船が速度を増していけば、ローレンツ収縮によってその間隔は短くなるべきである。しかし、宇宙船の縮み方がローレンツ収縮に『追い付かない』場合は、宇宙船の間隔は空間の縮みに対して相対的に伸びていることになり、いずれ切れてしまう。 |
ローレンツの主張は数式的には相対論と同じですが、概念としてはニュートンの絶対空間の考えから一歩も出ていません。よって、当時、ローレンツ自身が懸念を示したように、鉄でも綿でも材質に因らず同様な縮み方をするのは何故か?という疑問がありました。エーテルではなく空気の流れならば、鉄の棒はあまり縮みませんが、綿の棒は結構縮んでしまうでしょう。この部分がローレンツには分からなかった。
アインシュタインの場合は空間そのものを縮めてしまったので、空間上にある物体の材質には因らなくなりました。
なお、スコベリツィンの2台の宇宙船の話は、相対論に詳しい人でも意外に間違える人が多く、中々面白い題材であります。実際に、『相対論の正しい間違え方』を書いた時、この部分を間違えて(当事者は間違えたとは思っていないようですが)反論してきた大学教授が2人ほどいました。
[時間の遅れ]
この節の著者の説明は、相対論の反論ではなくて賛成の立場で書かれているように受け取れてしまいます。結局のところ何に対して反論しているのだかよく分かりません(^^;)。
まず、[ローレンツ収縮について]と同様な発言があります。2つの時計があって、一方AがBを見て時計が遅れていると見たならば、BがAを見た場合は進んでいると見るのが常識だと述べています。…それって単にAの時計の進み方が機械の故障か何かで進んでいるだけじゃないかと思いますが。
なんでも、このような双方の時計が遅れているという事があり得ないと数式的にも容易に説明できるとかで、著者の書いた別の本『ローレンツ変換の新解釈』には、それが載っているそうです。ただし、そちらの本は持ってないのでコメントできません。
次に、「しかし、時間の遅れは実際に観測されている」という反論に対して、具体的にはハーフエルとキーティングの飛行機による実験が登場します。
実際にはハーフエルではなく、ハフェーレの筈。元がJ.Hafele(とR.Keating)なので…。
著者は次のように指摘します。
しかしながら、私の研究によれば前述のヘイらの実験およびハーフエルらのジェット機世界一周の実験では時計の遅れが確かにあったと言うが、前者の実験では遠心力、後者の実験では重力というように力の場が作用したのである。これはもはや一般相対論の範囲に入るのである。
全く持ってその通りです(^_^)。ちなみに、ヘイらの実験というのは『横ドップラー効果』を調べた実験であるという事ですが、私個人の浅学の中では知りませんm(__)m。ただ、横ドップラー効果を確かめようとした実験というのは、色々あって実験的にも確かめられておりますが、今は詳しくは述べません。
で、ジェット機世界一周による実験の方は、前回の時にも述べたのですが、著者の言う通り一般相対論的効果を無視できません。というより、
速度の違いが原因の特殊相対論的効果よりも、重力による一般相対論的効果の方が大きいくらいです。
よって、当然ながらこの実験では、著者の指摘を待つまでもなく、最初からこの事を考慮した上で実験をし、特殊相対論と一般相対論両方が絡む理論結果と実験結果が一致を見たのでした。
以上のように、著者の指摘は正にその通りとしか言えない訳でして、これが何の反論になっているのかよく分かりません。著者は実験者の名前まで調べているのですから、当然実験内容は知っている筈だと思いますから、この指摘で何を言わんとしているのか分からないのです。もしかすると、相対論の批判をしているフリをして、実は援護しているのではないかとも取れたりします(トロイの木馬かな)。
次に高速で飛ぶ中間子の寿命が伸びた話を著者は持ってきていますが、具体的な内容はなく、自らの書いた「ローレンツ変換の新解釈」の宣伝をするのみに留まっています。
そして、次に、『双子のパラドックス』の事がでてきますが、ここでも、相対論が正しいという主張とも受け取れる発言がなされていて面白いです。
内容を要約します。双子のAがロケットへ乗り、Bが地球に残ったとすれば、特殊相対論では双方の時計が遅れるから互いに相手の方が若いという矛盾した結果になる。が、Aの方は引き返す段階で加速度運動が必ず必要になるから、一般相対論の等価原理を適応すれば、この加速度が重力場のごとく作用する。その結果Aのみが一方的に時計が遅れる事になる…。
これもその通りであります。このまんまの説明が相対論の啓蒙書にもシバシバ登場するくらいですから。
そして、次のように著者は続けています。
一般相対論では時計の遅れが可能なのであるから、このような理論に取扱上の誤りがなければ事実として興味のある問題ではある。しかし、その反面これは理論的に当然の帰結でありもはやパラドックスではなくなるのである。
…これもその通りで、パラドックスは存在しないという結論が一般相対論によって説明されたわけです。
ここまでの説明では、著者は『相対論に対して単に懐疑的』なだけであり、間違った主張にはなっていない事になります。
[時刻の相対性]
ローレンツ変換をローレンツが導いた時、立場によって変化する時間を局所時間と呼んで真の時間と区別しました。真の時間というのはエーテルに対して止まっている物体の時間という事になろうかと思いますが、その後そのようなものが存在しない事が次第に明らかになります。著者は局所時間を、時間と空間座標の合の子であって、数学的技巧に過ぎないとし、
しかしこのような合の子時間に対応する真の時間がこれらとは別にあるわけで、そしてそれらは容易に見出すことができるのである。
としています。ローレンツ変換では、式をいかように変換してもローレンツ変換に戻ってしまうので、
たとえ真の時間があったとしても、検出は不可能だったから困ったのです。ただ一言「容易に見出すことができるのである」とだけ言われても困ります(^^;)。その容易な真の時間の見出し方を是非書いてもらいたかった。もしかすると、それを書くには、
この本の余白は狭すぎたのかもしれませんけど…。
[光速度不変の原理の見直し]
著者は、速度vで近付く物体からでる光は本当はc+vとなっているが、観測するとcとなる・・・という新理論(?)を打ち立てています。ただ、その変換方法はどこにも書いてありません。
きわめて簡単なルールにしたがってこの世界線が運動座標系と静止座標系の境界で屈折することになり、動く光源から出る光は静止系で観測するとc+vの速度が必ずcになることを見事に説明しうることがわかった。
とだけ書いてあります。きわめて簡単なルールで見事に説明できるならばそれを是非書いてもらいたかった。もしかするとそれを書くには…以下同文。
ちなみに、この説を反駁するのは簡単です。著者は観測地で測定した時のみcと観測してしまい、観測しなければc+vだと言っているのですから、光速度を直接測るのではなくて、ある距離を光が通過する時間を測ればよい。
ネズミ取り方式とでもいいましょうか(^_^;)? 警官がひょいと出てくると、その瞬間に速度が遅くなって捕まらないのだから、ある距離離れた2点にセンサーを置いて、その2点を通過する時間を調べればいいんです。光を使った距離計ば実際にそういう原理で現在使われてますけどね(^_^;)。
相対性理論のどこがおかしいか:後藤 学氏
[窪田登司氏の本]
まずは、著者が窪田氏の本を読んだ感想が述べてあります。そして、特殊相対論の3つの仮定があり、そのうち2つがおかしいと述べています。
3つとは、
- 特殊相対性原理
- 光速度不変の原理
- 時空座標の二点間距離の不変性(あるいはローレンツ変換といってもいい)
です。普通は1と2だけなのですが、著者は3を付け加えています。この段階で著者は既に、特殊相対論の何が新しかったかを理解していない事がわかります(ちなみに著者が変だとしているのは、2と3です)。
ローレンツ変換はアインシュタイン以前にも知られていました。しかし、それはマイケルソン・モーレーの実験を説明するため、ローレンツ収縮という発想が先にあり、どの程度縮めば実験に合うかと考えられたものです。すなわち、実験事実に合うように作られました。しかし、アインシュタインは、基本原理となる1と2のみから、3を初めて導出したのです。それまでは実験式に近かったローレンツ変換を、2つの仮定を想定して、そこから演役的に導いたのです。
よって、著者が『重大な仮説』として3を付け加えている事そのものが、既に特殊相対論の意義を理解していない事になります。
第3の仮説を付け加えるという失敗(あるいは認識不足)は過去にもよくあった事であり、著者だけのものではありません。かのポアンカレも、1と2の仮説と共に、物体は動くと縮むというローレンツ収縮そのものを仮説として導入しています。もちろん、ローレンツ変換が1と2から導かれるのですから、ローレンツ収縮も1と2から導かれたわけで、第3の仮説として付け加える必要性はありません。
という事で、著者のくっつけた第3の仮説は、百数年前のミスの繰り返しなのです。新たな指摘が付け加わっているのなら話は別ですが、そうではありません。
著者曰く、
こうした指摘は本稿が歴史上初めてだと思います。
と述べています。
[アインシュタインの相対性理論のどこがおかしいか]
ここで著者は3つの仮説(上記したように3つ目は著者が余計なお世話でつけたものですが)についての説明をしています。
1つ目の特殊相対性原理については特別新しい事を言っているわけでは無いので割愛します。特に妙なところもないと思いますし。
2つ目の光速度不変の原理について著者は反論します。反論と言っていいのかよく分からないのですが、要するに常識に反しているとは言っています。そして、
まずいことに、アインシュタインの相対性理論から帰結する、そうした奇妙な現象は、普通の人では理解できない分、とても神秘的であり、場合によってはSF的ですから読者に夢を与えてきました。
と述べています。夢を与えたかどうかはともかく、
普通の人は理解できないという部分が大いに疑問です。少なくともローレンツ変換を求める程度の事は中学校3年程度のレベルで可能です。必要なのはピタゴラスの定理と二乗やルート計算ができればいいのですから。もっとも、数学セミナーあたりを読むと、
数学という言葉自身に既に恐怖を感じる人がいる事が語られたりしているので、普通の人は理解できないという感覚は
普通の感覚なのかもしれません。
しかしながら、
著者はテンソル解析や連続体力学を専門としている工学部教授なのです。特殊相対論はもちろんのこと、一般相対論のリーマン幾何学だってお手のものの筈です。少なくとも、
数学的なハンディは全くない御仁です。
3つ目の時空座標の二点間距離の不変性は、著者が勝手に作った仮定ですが、端的に言うと、2つの座標系(x,t)と(x',t')で、光がAからBへ移動したとき、

としてしまうのがおかしいと述べています。そして時間軸を虚数単位にする必然性が感じられない(つまり人為的だ)としています。すなわち、それぞれの括弧の中身を微小Δとして表し、
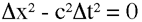
とする必然性が感じられないと言っています。ピタゴラスの定理ならば、3次元空間で考えて、

なのに、何故、時間軸を付け加える時だけ、マイナスをつけて、
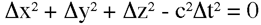
としなければならないか分からないというわけです。
これは実に簡単な話で、作為的な都合合わせでもなんでもありません。必要な考えは、距離=速度×時間という物理法則のみです。
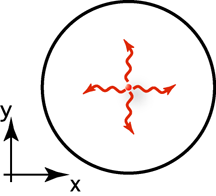 ある瞬間に光源から光が四方に飛び出したとします。実際は3次元を考えて球面状に広がる光となります。Δt秒後、x軸方向へ向かった光はどこまで進みますか?
ある瞬間に光源から光が四方に飛び出したとします。実際は3次元を考えて球面状に広がる光となります。Δt秒後、x軸方向へ向かった光はどこまで進みますか?
距離=速度×時間を考えれば、

でしょう。ただし実際には-Δxにも光は飛んでいる(四方に広がったのだから)ので、
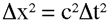
とすべきであって、なおかつ、3次元空間に広がる光ならば、
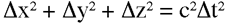
とせねばならないという…ただ単にそれだけのモンです。上式の右辺は、Δtの間に光が進む距離の二乗を『(速度×時間)の二乗』で表しているのに過ぎず、左辺はピタゴラスの定理によって球面に広がっている事を示しているに過ぎません。この式は、幾何学で言う球の公式そのものです。もっとも球の場合は半径rで記述され、右辺はr2となってますけど…。
アインシュタインは他の慣性系から見ても、この式が成り立つとして考えました。どのような慣性系から見ても光は球状に広がるという仮説です(光速度不変)。もちろんこの考えは仮説ですから、実験で確かめる必要があるのは当然です。
[静止座標系は設定できないか]
著者は自ら絶対静止系の存在を是としていると述べています。ですから、なにを絶対基準とするのかをここで述べています。
取敢えず、窪田氏の絶対静止系の考えは弱いとして、地上での振動数の分かっている光を使えばc=nλとなっていて、このcが電磁気学で導出される、
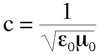
と同じならばそれは絶対静止系であるとしています。なおnは振動数でλは波長であると思われます。
後藤氏の考え方の本論はもう少し後ろに書いてありますが、どちらにせよ波長と振動数を基準とする考え方は実験で否定されています。振動数は観測者に対する光源の運動によって変化するからです。これは実際に観測されている事実です(著者は後の章で横ドップラー効果の話をしているのですが、何故ここで気付かなかったのか不思議です)。で、そのような時でも光速度cは不変だったという観測事実もまたあります。
続いて、著者は絶対的な静止基準系として2つの可能性を述べます。
1つ目は、地上は電磁気学的に宇宙から孤立していると言えるので、地上の実験は地上が静止基準系としてよいという考えです。この考えは、マイケルソン・モーレーの実験が発表された直後から既に指摘する人がいたほど、平凡な考えです。エーテルを信じている人ならば、まずこの考えが浮かぶでしょう。実験を行ったマイケルソン自身も同様の指摘を考えています。
つまり、地球上では、エーテルが地球に引きずられて、地球と共に動いているという主張です。この主張の真偽を確かめるために、地球にあまり引きずられないであろうと思われる丘の上で同様の実験が行われていたりします。
著者は、電離層より下の地上がアヤシイとして、
とくに、この電離層のために、地球が電磁場的にある程度、外宇宙から孤立系を成していることも十分あり得ることです。
と述べています。個人的には何故十分あり得ることと思ったのだろうと感じますが、まあ感じ方は人それぞれです。このへんは、昔同様な主張に答えるために丘の上で実験をしたように、是非電磁層より上の空間で直接実験をしてもらいたいです。やっぱりシャトルの装置を載せて外で実験するのが一番かと。丘の上の実験は1904年に行われましたから、シャトルはまだ無かったわけでして…。
シャトルに載せたマイケルソン・モーレーの実験が為されれば、それは直接的な反論になりますが、そのような事がなくとも、既に100年以上前から地球に静止座標系を持ってくる場合の矛盾点は指摘されています。宇宙空間へ出て実験せずとも丘の上の実験で十分なのです。その丘の上で星が見えるならば。
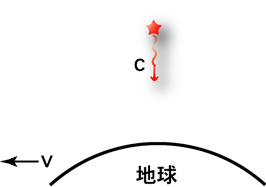 望遠鏡で星を観測すると、1年で星の位置が僅かずつながらずれる現象があります。これを光行差現象といいます。これは真っ直ぐ降る雨に対して走ると、ナナメに傘をささねばならない事と同じ原理で、夏と冬とでは地球の公転の向きが逆なので、星から降ってくる光の向きが微妙にずれるのでした。
望遠鏡で星を観測すると、1年で星の位置が僅かずつながらずれる現象があります。これを光行差現象といいます。これは真っ直ぐ降る雨に対して走ると、ナナメに傘をささねばならない事と同じ原理で、夏と冬とでは地球の公転の向きが逆なので、星から降ってくる光の向きが微妙にずれるのでした。
さて、地球周辺は外部と孤立した絶対静止系であると仮定します。星からの光は、地球に近付くまでは地球と無縁な静止系にあるという事になります。そして、地球の電離層の下に入ると、地球絶対静止系の傘下に入る。このようなモデルの場合、光行差現象は全く観測されません。
上述の雨の例で示しましょう。例えば、雨が非常に小さな霧雨で、風になびいて降る状態だったとします。無風の時、雨は垂直に降りますが、この中を走りながら観測すると、斜め前方から降ってきます。これが光行差に相当します。では、周りの空気ごと移動させたらどうなるでしょう。例えば、大きなワンボックスカーを運転していて(内部は無風)、その天窓が僅かに開いており、そこから霧雨が入ってくるような状態です。自動車内部の空気が自動車に対して動いていない限り、霧雨は運転者に対して真上から降り注ぐのではないでしょうか。
これと同様に、光は地球に入るまで真っ直ぐ降っていた。そして、地球孤立系の中に入ると、地球に対して静止している系で動くのですから、光の経路は地球に対して傾きません。強いて言えば、電離層の上と下とで光が屈折することになります。このような場合、光行差が観測されることはないのです。
ところが、光行差はマイケルソン・モーレーの実験以前に既に観測されていました。だからこそ問題となったのです。
- 光行差現象を説明するためには、地球が孤立した静止系にないとせねばならない。
- マイケルソン・モーレー実験の説明には、地球に孤立した静止系の中にあるとせねばならない。
この2つは明らかに矛盾です。当初、マイケルソン・モーレーの実験は
光行差が観測出来ない地下室で行われたことからイチャモンが付けられ、その後、
光行差現象が直接観測できる丘の上で、この実験が再度行われたのです。よって、この矛盾点を説明しない限り、地球を孤立した座標系と見ることは不可能です。
なお、著者の2つ目の可能性というのは、地上の議論では地上に絶対静止系を定義し、太陽系規模の議論では太陽系を絶対静止系にしようという考えです。どちらにせよ、光行差現象とマイケルソン・モーレーの実験を同時に説明できる代物ではありません。
[アインシュタインの相対性理論が導く神秘的で奇怪な現象]
まず著者は、最初にガリレー的な立場と称して、vAとvBで走る2人の人の相対速度や光と人の相対速度の話を出してきます。あらかじめガリレー的と言っているので、光速度は観測者の運動により変わっています。ここでの著者の計算は間違いありません。まあ、問題なのは、
ガリレー的など専門用語を使いましたが、そんなガリレー変換など知らない中学生や小学生でも理解できる疑う余地のない真実と断言できます。
という言葉だけでしょうか?
真実かどうかは実験で確かめるべきものです。事実、光速度はガリレー的な足し算は使えないのですから。まあ、これは光だけでなくて、光速度に近付くほどガリレー的な足し算が使えなくなるので、光に限った事ではありません。
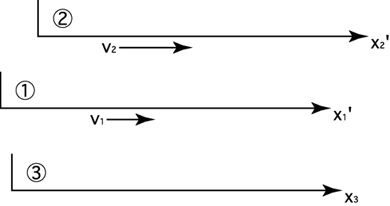 次に、相対論的な速度に対しての話になり、3つの異なった系について話が出てきます。ここで静止しているのは、3番目の座標であり、1と2は、3に対して動いています。そして、3に対するそれぞれの相対速度は、v1 及びv2 です。著者はここで、使い古された反論を述べます。
次に、相対論的な速度に対しての話になり、3つの異なった系について話が出てきます。ここで静止しているのは、3番目の座標であり、1と2は、3に対して動いています。そして、3に対するそれぞれの相対速度は、v1 及びv2 です。著者はここで、使い古された反論を述べます。
v1 が光速度の80%であり、v2 が、光速度の80%で逆向き(図の左向き)に動いていたとすると、3から見て、1と2の相対速度は0.8c+0.8cで光速度の1.6倍になるのではないかと…。
この話は、多くの啓蒙書に登場するありふれた疑問です。さらに『相対論が間違っていると言う人々』が必ずと言ってよいほど、相対論の矛盾点として挙げる話でもあります。つまり、光速度の80%で左に飛ぶ宇宙船から、光速度の80%で右に飛ぶ宇宙船を見たら、光速度の1.6倍で動いているように見えるのではないかという話。もともとこの本は、『アインシュタインの相対性理論は間違っていた』という本の続編ですが、前著の段階でこの間違いは書いてあります。[0.5c+0.5c=0.8c?]という分かりやすいタイトルで…。著者(後藤氏)は続編で、第3の観測者を出しているだけで、前著の話と本質的に何も変わっていません。
著者はこの指摘を、
こうした明確な形での指摘は、歴史上も本書が初めてです。
と述べています。著者は前著を読んでコメントしている筈なのに、
一体どこを見ているのでしょうか。
そもそも、相対論で光速度を越えないというのは、観測者がいる静止した系から考えて、光速度以上の速さで動くものはないという事であり、左右に0.8cで動く宇宙船同士が1.6cで離れているなんて事は最初から否定していません。一方の宇宙船から他方を見たときに、光速度の1.6倍だったのなら話は別ですが、そうではないのです。
 著者はこのあたりの事をよく理解していないのか、次のような話を続けてもってきます。
著者はこのあたりの事をよく理解していないのか、次のような話を続けてもってきます。
光速度に近い速度で動くAを考えます。Aをほぼ光速と見ているのは、Cです。ここで、Bを光とします。Bは、AにとってもCにとっても光速です。そしてBは図のように右に行く光と左に行く光とがあります。
著者の反論は、AとBの関係が、Aにいる観測者から見た場合と、Cにいる観測者が見た場合とで違うという点について行われています。
つまり、Aから見るとBは、右向きでも左向きでも光速で飛んでいきますが、Cから見るとBが右に動いている場合は、AB間の距離はほとんど変化無く、Bが左に動いている場合は、光速度の2倍で離れているように見えるのが変だと言っています。Cの立場ならそう見えて当然です。
Cから見て、AとBが同じ方向に移動していれば、AとBの速度の差はほとんどないのですからAB間の変化がほとんどないのは当然ですし、逆向きならば、光速度のほぼ2倍で離れるのも当然です。まさに、光速の80%で左右に離れる宇宙船と同じです。
著者の反論は、AとBが同じ向きの場合、Cから見ると短時間ではほとんど間隔の変化がないのに、AからみればBが光速で遠ざかるのは奇妙だという事だと思います。
この現象を説明するのは簡単です。CからみてAの時計はほとんど動いていません。何しろほぼ光速なのですから。そうすると、Aの時計の針が一秒進むのをCが見るのは、途方も無く長い時間の果てであるということになります。このため、BがAから離れる時間はCから見て十分にあるのです。定量的な計算を行う場合は、ローレンツ収縮も考慮しなければなりませんが、ちゃんと、Aから見てもBは光速となります。また、Cの観測者からみてAがBをどのような速さと認識しているかという計算も可能です。
なお、著者は続けて加速し続ける宇宙船を考え、
加速度計により獲得した速度を知ることはできます。その速度に上限はなく、光速の何倍にもなり得ます(もちろん、加速用の燃料は十分あるとしています)。
としております。ニュートン力学ならその通りですが相対論ではそうはなりません。要するに著者は
v=atを相対論に入れたらvはcを超えると述べているだけです。
そりゃそうです。それはニュートン力学の帰結ですから。特殊相対論においては、加速度aはどの観測者によって観測されたものかで変化するものであり、絶対的な量ではありません。この宇宙船を外から見れば、最初こそ近似的にv=atで加速して行きますが、その後どんどんと加速が鈍ります。このへんの計算は、
相対論の教科書に普通に書いてあるのですが…。
著者はこれを『全く理解できないこと』としていますが、著者が理解できるかどうかが問題ではなくて、観測・実験に合うかどうかが問題です。
実は、この後もツラツラと話が続くのですが、話の最後は『とても信じられないことです』で終わっていたりします。著者自身が信じられるか否かの問題に持ってくるというのは、森野氏の主張であるところの相対論は常識に反するという反論と通じるものがあります。
また、双子のパラドックスにおいては、相対論者が反対論者を無視したとか、元々の相対論の根本的仮説から生じる、どうにも解くことのできない矛盾などと述べているだけです。普通の相対論の教科書には、双子のパラドックスの事は特殊相対論の章で大抵は説明があります。著者は多分その説明が理解できなかっただけだと思われます。実際に計算してみて矛盾がでない事を確認すればすむだけなのですから。
面白いのが最終的に述べられている宇宙線(μ中間子)の寿命の伸びの説明です。地球座標で考えると、μ中間子は寿命が伸びることになるが、μ中間子座標で考えると、時間が遅れるのは地球の方だと述べます。これは相対論的にも正しい。
ところが著者は、μ中間子座標での考えから『μ中間子は、超光速で飛び込んでくると考えざるを得ません』と結論しています。正しくは、μ中間子座標でみると、地球はローレンツ収縮によってひらべったくなっているので、短い寿命でも地表面まで達する事ができる(もちろん光速以下で)こととなります。
なお、全く関係ない話なのですが、μ中間子というものは実在しません。レプトンとしてのμ粒子が正解です。μ粒子が発見された当時、湯川氏の中間子論が出た時であり、宇宙線の中にこの中間子相当の質量であるμ粒子が見付かったので、μ中間子という間違った名前が一時生まれたのが歴史的経緯です。
なお、湯川氏が予言した中間子は後にπ中間子として発見されています。
[マイケルソン・モーレーの実験について]
まず著者は、この実験を批判する人ならまず必ず指摘するように
この実験は100年以上前に行われたという事を述べます。もちろん、知ってか知らずか、最近でもこの実験は、レーザー光線を使って最新のエレクトロニクスを駆使して検証されているものであるという事を述べません。どうもこの本に登場する人物は全てこの傾向があるようです。そして、新たに検証すべきだと結論つけます。
検証され続けているのに。
また、自分では決して調べようとはしないようです。現在ならば、実際にレーザーを使って大学1年の学生実験で行われている実にポピュラーな実験だと言うのに。少なくとも理学部のある大学ならば、どこにでも検証装置はあると思います。
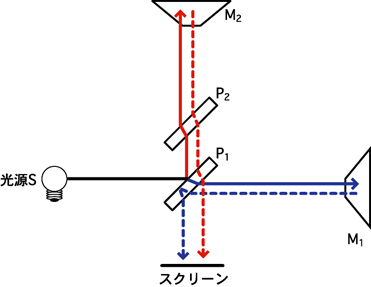 まず図を説明しますと、光源Sから出た光はハーフミラーP1に当たり、M1とM2という2つの鏡方向へ分離されます。この鏡で反射された後、再びP1へ戻った光が、焦点面のスクリーン(実際には望遠鏡があった)で合成され干渉縞を作ります。P2は、P1と同じ厚さのガラスです。著者は、この実験において、P2に挿入されているガラスに注目します。このガラスがなければ干渉縞はできないと主張します。まあ、実際にやってみれば分かる事ですが、P2はあっても無くても干渉縞はできます。
まず図を説明しますと、光源Sから出た光はハーフミラーP1に当たり、M1とM2という2つの鏡方向へ分離されます。この鏡で反射された後、再びP1へ戻った光が、焦点面のスクリーン(実際には望遠鏡があった)で合成され干渉縞を作ります。P2は、P1と同じ厚さのガラスです。著者は、この実験において、P2に挿入されているガラスに注目します。このガラスがなければ干渉縞はできないと主張します。まあ、実際にやってみれば分かる事ですが、P2はあっても無くても干渉縞はできます。
これまで何度か出てきたマイケルソン・モーレーの実験の図で、P2をわざわざ描かなかったのは、このガラスの有無があまり本質的なものではないからです。例えば、それを言い始めると、それぞれの経路での光は1往復ではなく、距離を稼ぐために4往復させられていたとか、色々と出てきます。よって、実際の実験の詳細を知りたいのでなく、単に模式図としてのマイケルソン・モーレーの実験であれば、P2を書かないのが一般的です。それどころか、ハーフミラーの厚みについても描かないことが多いくらいです。
P2を挿入した理由を説明しますと、M1とM2へ行く光の道筋を同等にするためということになります。P1はハーフミラーですが、その反射する金属面は、光源側にあります。
M1へ行った光(青線)を考えると、光はこの金属面を素通りしますから、この時にハーフミラーのガラス部分を抜けます。また帰り道も、金属面に当たるまでにこのガラス面を通ります。よって、ガラス3枚分を通過します。
M2へいった光(赤線)は、ハーフミラーP1の表面で反射されてしまうので、ハーフミラーのガラス部分は通過しません。ただし、M2で反射され戻ってきて光がスクリーンに行くためには、P1を通過する必要があります。よって、この光はガラス1枚分を通過します。
つまり、M1へいく光とM2へ行く光には、ガラス2枚分の違いがあるので、これを対等にするために、わざとP2というガラスを挿入し、条件を同じにしたのでした。このガラスの存在は、実験のテクニカルな設定に属するものですから、エーテル検証実験としての概念的な図にあまり登場しないのも納得できるでしょう。
著者はP2の存在を知っているにも関わらず、その意義については知らないのか、あるいは意図的に述べていないのか分かり兼ねますが、ともかくP2がないと干渉縞ができないなどという奇妙な(そして間違った)結論を引き出します。なんでも、P2から直接反射する光が干渉縞を作るのだとか(ニュートンリング的な発想のようで)…。さらに著者は、文頭において明確に、M1とM2が反射鏡で、P2は透明ガラスと述べているのに、後になってP2からの反射云々と述べ始めます。
P2は透明なのですから反射はありません。仮にわずかな反射があったとしても、最初から反射する事を目的とした反射鏡M2より多くの反射があったとは思えません。さらに譲歩してP2が鏡であったとしても、P2の角度から考えて、P1へ光が戻っていく筈はありません。
そもそも、マイケルソン・モーレーの実験にP2は入っていたのですが、著者は、
たとえば、図34の透明ガラスP2を外して実験をしたのではないか、という疑いです。
と、この実験に疑念を述べます。そんなことを述べるくらいなら、
現存する実際の実験装置の写真を一目見ればよいではないですか。P
2が付いていることは明らかに分かります。また、上述したように、この実験は現在も何度も行われています。気になるのでしたら、
当時の1万倍くらいの精度で何度でも再現実験可能です。
また、本に書かれている図では、ハーフミラーの金属面が逆になっており、P2の意義を全く無視した図となっております。著者は一体何を調べたのでしょう。
また、著者はこの実験で、P1〜M1間および、P1〜M2間の距離を、厳密に同じくするのは不可能だし、干渉縞の動きを調べるのだからピタリと合わせる必要は無いと述べています。その通りです。後になって、わざと双方の距離を変えた実験まで行われている程ですから。
で、著者の結論は、この実験はちゃんとしたデータが取れるほど誤差が小さく無かったのではないかというものになります(^_^;)。やはり、著者は現在もこの実験は行われていて、当時の数万倍の精度で確かめられている事実を知らないか、あるいは無視しているようです。
[光のドップラー効果について]
ここでの反論は簡単です。著者はガリレー的なドップラー効果とアインシュタイン的なドップラー効果について述べており、どちらが正しいかは精密な実験によって確かめるべきとしています。全くもってそのとおりです。
この実験は1938年にH.E.Ives&G.R.Stilwellによって検証されていますから(J.Opt.Soc.Am.,28(1938)225-226)既に著者の主張は間違っている事が分かっています。
[電場による電子の加速実験について]
著者の主張によると、電場がかかっている中を電子が飛ぶ場合、電場がある事で全くの真空とは明らかに異なるから、光速度以上の加速はできないそうです。では、重力場や電磁場のない全くの真空中で、どのように電子を加速しろと言うのでしょう。
また、ここでも、電子の立場にたつと、ずっと加速され続けるから超光速度になるという主張が繰り返されています。
[質量とエネルギーの関係について]
著者は、
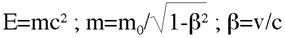 …(82)式
…(82)式
という式に対し、
もし、全質量m0が電磁波となって消滅してしまうのであれば、式(82)は意味があるかもしれませんが、そんなことは思考上以外は考えられないことです。
と述べています。電子-陽電子の対消滅は
思考上以外考えられないことなんでしょうね。
[測量的長さと視覚上の長さ]
この章は単に幾何光学的な問題を述べているだけです。これは、ニュートン力学でも相対論でも出てくる視覚上の効果です。
これについていくら述べても、相対論への反論にはなりません。この視覚的効果については1960年頃にさまざまに研究された分野で、著者の出る幕はありません。
[実験的検証に付す以前の数学的遊戯]
…この章はタイトルだけで内容は既にわかるでしょう。結局、著者はこれが言いたいだけなのだと思います。

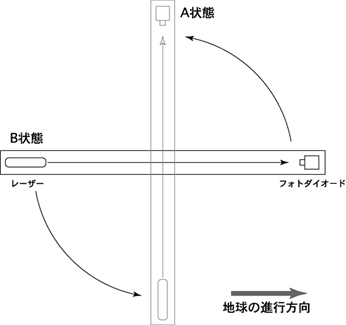 装置は長い板とレーザー装置、そして、受光するフォトダイオードです。要は、長く飛んでも拡散しない光源と、光を感知するものがあればなんでもいい事になります。
装置は長い板とレーザー装置、そして、受光するフォトダイオードです。要は、長く飛んでも拡散しない光源と、光を感知するものがあればなんでもいい事になります。 とか、大昭和精機の
とか、大昭和精機の とかどうでしょう、お客さん。前者はドムみたいで中々でしょ。共に10m先で1mm以下の誤差で測れます。板を180度回転させれば、30km/sの動きを考慮すれば、2mmの変化が出ますし、350km/sならば2.3cmもズレます。このレーザー墨出し器で十分に実験出来ます。また、板を回転させなくても、12時間たてば地球が自転するので、回転させたのと同じ状況になりますから、やはり、2mm〜2.3cmの変化が出るかどうかが分かります。
とかどうでしょう、お客さん。前者はドムみたいで中々でしょ。共に10m先で1mm以下の誤差で測れます。板を180度回転させれば、30km/sの動きを考慮すれば、2mmの変化が出ますし、350km/sならば2.3cmもズレます。このレーザー墨出し器で十分に実験出来ます。また、板を回転させなくても、12時間たてば地球が自転するので、回転させたのと同じ状況になりますから、やはり、2mm〜2.3cmの変化が出るかどうかが分かります。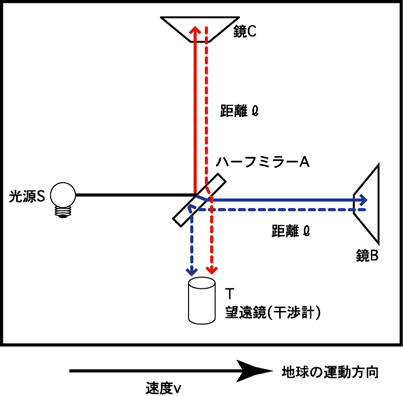 マイケルソン・モーレーの実験は何度も出ています。ABとACの距離は同じとして、光がA→B→Aと進む場合と、A→C→Aと進む場合とで、時間的なズレがあるかどうか調べる実験です。
マイケルソン・モーレーの実験は何度も出ています。ABとACの距離は同じとして、光がA→B→Aと進む場合と、A→C→Aと進む場合とで、時間的なズレがあるかどうか調べる実験です。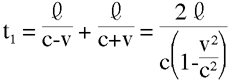 …式1
…式1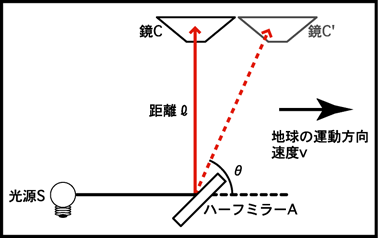 具体的に、A→Cに行くには、装置が動いているとみる系において、A→C'に行くという事です。A→C'→Aの往復にかかる時間はピタゴラスの定理により、
具体的に、A→Cに行くには、装置が動いているとみる系において、A→C'に行くという事です。A→C'→Aの往復にかかる時間はピタゴラスの定理により、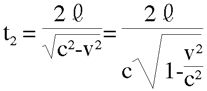 …式2
…式2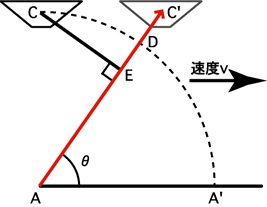 左図を見て下さい。まず求める部分というのは、AC'間の距離です。これをアインシュタインは、ピタゴラスの定理により、
左図を見て下さい。まず求める部分というのは、AC'間の距離です。これをアインシュタインは、ピタゴラスの定理により、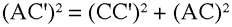
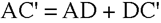
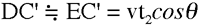
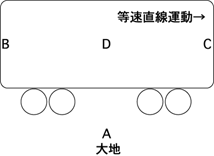 という風に同時の相対性が書いてあるとして、これを攻撃していますが、この説明なら私もNOと言います。この説明は明らかに間違っているからです。著者は、『相対論を正しく理解してないので、こんなふうになってしまった』と述べていますが、私もその意見に賛成です。
という風に同時の相対性が書いてあるとして、これを攻撃していますが、この説明なら私もNOと言います。この説明は明らかに間違っているからです。著者は、『相対論を正しく理解してないので、こんなふうになってしまった』と述べていますが、私もその意見に賛成です。
 をどのように応用しているのだろうか。
をどのように応用しているのだろうか。
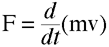


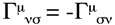
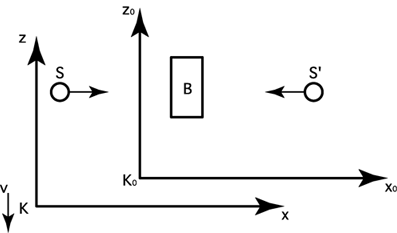 さて、それでは著者が指摘しているアインシュタインの論文(巻末資料2)について考えます。内容は次の通りです。
さて、それでは著者が指摘しているアインシュタインの論文(巻末資料2)について考えます。内容は次の通りです。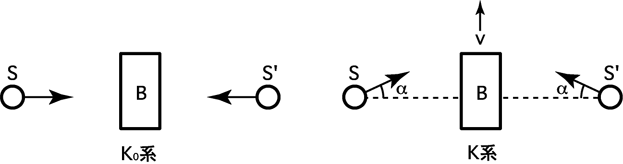

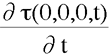
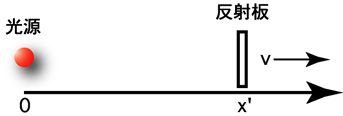 次に、光が時刻τ0の時にX軸に沿ってx'まで進み、τ1の時に反射し、τ2で原点に戻った時の事を考えます。ここで、装置と共に動く慣性系からみれば、
次に、光が時刻τ0の時にX軸に沿ってx'まで進み、τ1の時に反射し、τ2で原点に戻った時の事を考えます。ここで、装置と共に動く慣性系からみれば、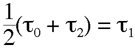
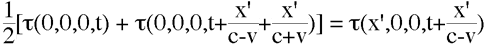
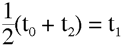

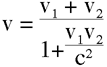
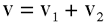 (ただし、0≦v<c)
(ただし、0≦v<c) (cには何足してもc)
(cには何足してもc)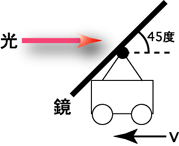 この本の中で、もっとも下らないと思われるミスはここにあります。
この本の中で、もっとも下らないと思われるミスはここにあります。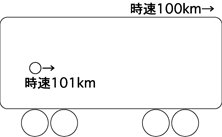 また、続いてこの著者の勘違いをさらに決定づける端的な思考実験もあります。マイケルソン・モーレーの実験で、エーテル流と平行に走る光の方の考察で、行きの光の見掛けの速度がc-vで、帰りがc+vとする部分に、著者は反論します。この部分に反論する人も、本書の中では日高氏だけだと思います。
また、続いてこの著者の勘違いをさらに決定づける端的な思考実験もあります。マイケルソン・モーレーの実験で、エーテル流と平行に走る光の方の考察で、行きの光の見掛けの速度がc-vで、帰りがc+vとする部分に、著者は反論します。この部分に反論する人も、本書の中では日高氏だけだと思います。
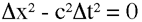

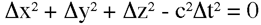
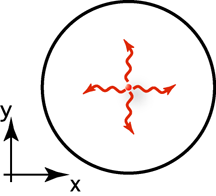 ある瞬間に光源から光が四方に飛び出したとします。実際は3次元を考えて球面状に広がる光となります。Δt秒後、x軸方向へ向かった光はどこまで進みますか?
ある瞬間に光源から光が四方に飛び出したとします。実際は3次元を考えて球面状に広がる光となります。Δt秒後、x軸方向へ向かった光はどこまで進みますか?
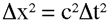
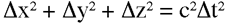
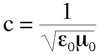
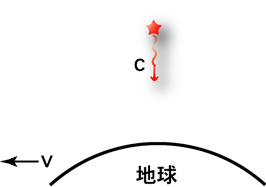 望遠鏡で星を観測すると、1年で星の位置が僅かずつながらずれる現象があります。これを光行差現象といいます。これは真っ直ぐ降る雨に対して走ると、ナナメに傘をささねばならない事と同じ原理で、夏と冬とでは地球の公転の向きが逆なので、星から降ってくる光の向きが微妙にずれるのでした。
望遠鏡で星を観測すると、1年で星の位置が僅かずつながらずれる現象があります。これを光行差現象といいます。これは真っ直ぐ降る雨に対して走ると、ナナメに傘をささねばならない事と同じ原理で、夏と冬とでは地球の公転の向きが逆なので、星から降ってくる光の向きが微妙にずれるのでした。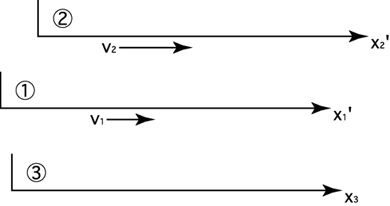 次に、相対論的な速度に対しての話になり、3つの異なった系について話が出てきます。ここで静止しているのは、3番目の座標であり、1と2は、3に対して動いています。そして、3に対するそれぞれの相対速度は、v1 及びv2 です。著者はここで、使い古された反論を述べます。
次に、相対論的な速度に対しての話になり、3つの異なった系について話が出てきます。ここで静止しているのは、3番目の座標であり、1と2は、3に対して動いています。そして、3に対するそれぞれの相対速度は、v1 及びv2 です。著者はここで、使い古された反論を述べます。 著者はこのあたりの事をよく理解していないのか、次のような話を続けてもってきます。
著者はこのあたりの事をよく理解していないのか、次のような話を続けてもってきます。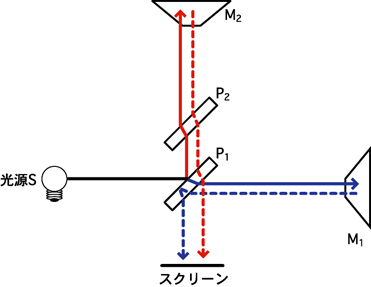 まず図を説明しますと、光源Sから出た光はハーフミラーP1に当たり、M1とM2という2つの鏡方向へ分離されます。この鏡で反射された後、再びP1へ戻った光が、焦点面のスクリーン(実際には望遠鏡があった)で合成され干渉縞を作ります。P2は、P1と同じ厚さのガラスです。著者は、この実験において、P2に挿入されているガラスに注目します。このガラスがなければ干渉縞はできないと主張します。まあ、実際にやってみれば分かる事ですが、P2はあっても無くても干渉縞はできます。
まず図を説明しますと、光源Sから出た光はハーフミラーP1に当たり、M1とM2という2つの鏡方向へ分離されます。この鏡で反射された後、再びP1へ戻った光が、焦点面のスクリーン(実際には望遠鏡があった)で合成され干渉縞を作ります。P2は、P1と同じ厚さのガラスです。著者は、この実験において、P2に挿入されているガラスに注目します。このガラスがなければ干渉縞はできないと主張します。まあ、実際にやってみれば分かる事ですが、P2はあっても無くても干渉縞はできます。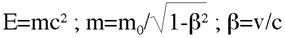 …(82)式
…(82)式