誰もが思う「アインシュタインがまさか!!」
著者は今までも色々な学説が覆された事(食品添加物の害の有無。耶馬台国の位置等)を先に述べた後、次の一文を書いています。
そんな事と相対性理論とはワケが違う! 相対性理論は深遠、かつ崇高な神が認める理論だ! 物理学の基礎になっているものだ! 頭のいい学者先生が寸分の間違いもないように、数学的にくみ立てているものだ! 一介のジャーナリストに何がわかるものか! と、あなたは私に食ってかかるかもしれません。
もし、著者が述べているように『頭のいい学者先生が作ったから正しいのだ』という理由で著者に食ってかかる人がいたとしたら即刻改めるべきでしょう。科学理論は頭のいい学者が作ったか否かで決まるものではありません。
論理的・数学的に正しく、かつ、実験・観測に照合する理論が選ばれます。
事実、相対性理論の検証は現在でも行われ続けています。少なくとも検証を続けている人達は相対論の『信者』ではありません。
次に、著者は相対論を、
25歳の一事務員であったアインシュタイン一人が、ある「ひらめき」から作った理論なのです。
と述べています。もちろんその通りなのですが、著者の意図する主張は、一介の若い事務員のひらめきだけで作られた理論であるから、当時の物理学の常識とは掛け離れた、間違った考えをしてしまったのだと言いたいのだと感じます(もちろんこれは私の感想ですから、実際にこの本を読んでみて下さい)。
しかし、アインシュタインが特殊相対性理論を発表した1905年当時の状況を考えると、アインシュタインの理論は、多少誇張して述べれば少しも独創的ではなく、他より少し早く述べただけという事になります。
発表が5年遅れていたら、他の誰かが必ずや構築していた筈の理論です。言ってみれば特殊相対論はアインシュタインが発表しなくてもよかった。アインシュタインがこの世にいなくてもいずれ登場していた理論です(一般相対論の方もヒルベルトが同様の研究をしており、アインシュタインと先取権論争がありました)。
まず、時間や空間の縮みの元になるローレンツ変換は、1905年よりかなり前(1887年)にW.フォークトにより定式化されました。その後フィツジェラルドもこの事に気付き(1889年)、1892年にはローレンツがこれに気付いています。
そして彼ら3人はそれぞれ独立にこの考えに達しているのです(その他ラーモアやポアンカレも独立にこの変換を発見しています)。ですから、アインシュタインの発想は突出したものではなく、当時の物理学としては平凡な結論だったと言ってもいいくらいです。この結論は、マックスウェルの電磁気学が完成した時(1864年)に既に予見できたと言ってもよいでしょう。マックスウェルの理論は相対論が登場する前から相対論的であり、ローレンツ変換に対して不変な形をしていましたから…。
特にポアンカレに至っては1898年に『われわれは2つの時間間隔の同時性について何も直感を持っていない』・・・すなわち、2つの場所の”同時”を決定する為には測定が不可欠であって、ニュートン力学においてのどこでも同じ時が流れているという仮定は不敵切であるという事を述べています。
その後もたびたびこの主張をし、エーテルの存在そのものに対しても疑問を投げかけ、互いに相対運動をしている観測者の時計が真の時間を示さず、それぞれが局所時間という別々の時間をもつであろうと公演しています。そして我々は、ニュートン力学に変わる新しい力学を作らねばならないとまで言及しています。
もっとも真の時間と局所時間という分け方が多少古めかしいのですが、アインシュタインがいなくても、いずれポアンカレか、その他の先人達によって特殊相対論は登場してくるであろう事は間違いありません。事実、特殊相対論の論文が発表された(1905年6月30日)の、僅か前(1905年6月5日!)にポアンカレは論文を出し、全ての自然法則はローレンツ変換に不変でなけれぱならないと述べているのです。
うがった見方をすれば、アインシュタインはオイシイトコだけをコソッとかすめ取って行った人物と見てもいいくらいです。ある本(E.T.Whittaker : History of the Theories of Aether and Electricity)には、
1905年秋・・・アインシュタインは1つの論文を発表した。その中で彼は、既に知られていたポアンカレとローレンツの相対性理論をいくらか補充した形で示し、大いに注目をあびることとなった。
と、書かれていたりもします。
もっと問題なのは、アインシュタインの論文には、ポアンカレはおろかマイケルソンとモーレーの名前も無いのです。客観的事実としてアインシュタインは、ポアンカレの論文とマイケルソン・モーレーの実験について知っていただろうと思われます(本人は思い出せないと述べています)。
もしもこれらを知っていて、ポアンカレらの論文を参考論文として掲載せずに特殊相対論を書いたとなると、かなり失礼な事になります。
ポアンカレはその後、アインシュタインの名前を一切口にせず、彼がほとんど完成させかけていた相対論の公演をする時にも、ローレンツの名前を上げて公演するという徹底ぶりでした。逆にポアンカレの死後、アインシュタインは、ポアンカレ記念論文集への論文寄稿要請を蹴っていたりします。
まあ、かなりギスギスした関係になっていた事は容易に想像できます(晩年アインシュタインはポアンカレの功績に対してふさわしい栄誉が与えられるようにと述べていますが)。
・・・ちょっと話はそれましたが、少なくとも特殊相対論は『25歳の一事務員が勝手に「ひらめいて」出来上がった代物』では無い事がわかるでしょう。それは時代の要請であったと言っても過言ではありません。
横浜で発見した相対性理論の間違い
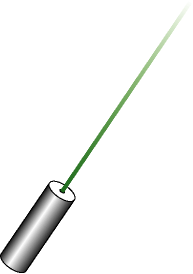 著者は横浜の花火大会において、光の速度を見たと述べます。そして光の速度は意外と遅いのだと結論づけています。
著者は横浜の花火大会において、光の速度を見たと述べます。そして光の速度は意外と遅いのだと結論づけています。
著者は花火が上がった煙一杯の空に向けて発射されたレーザーを見て、そのレーザー光がすぅーっと煙の中を飛んでいくのを観察します。
この光の移動が肉眼で認知できるという現象はよく知られたもので、その理由は後半に述べますが、それとは全く別に、光速の大小と相対論の真偽がどうして結び付くのかが根本的によく分かりません。
著者は、光の速度が1秒間に地球を7周半もするのは『昔の感覚』で、今は衛星回線による電話のやりとりのタイムラグ等で光の速さが意外に遅いという事を強調します。
『意外に遅い』と思うか『やっぱり速い』と思うかは個人の感覚の問題であり、特に反論するつもりはありません。例えば昔はハワイというのは遠い存在で憧れのハワイ航路だとか、夢のハワイとか言われたモンですが(古過ぎる)、最近はほとんど国内旅行のような感覚となりました。時代が過ぎて『ハワイは意外と近い』存在になったわけですが、実際の距離が変わったわけではありませんね(プレートテクトニクスを持ち出して、年間に数センチずつ日本に近付いているというチャチャを入れる人が5人位はいるでしょうけど^_^;)。光速の感覚はこれと同じです。
ですが、この光速度の“感覚”の変化と相対論の真偽の関係が私にはよく分からないのです。著者はこれを強調して何が言いたいのでしょうか?
とりあえず、煙の中を通過するレーザー光が飛んでいく様子が見えるように感ずるメカニズムを紹介しておきます。著者は短絡的に『光の速度を見た』と考えたようですが、本当に目に見えたわけではありません。
例えば、完全に同時に光る2つのランプを考えて下さい。もしも、ランプの一方が明るく、他方が暗かったとした場合、人間は2つの光を同時に知覚出来ず、数ミリ〜数十ミリ秒の差を感じます。そして、明るい方を先に見たと認知します。
これは所謂、視覚特性に関する現象であり、ブロックの法則(Bloch's law)と呼ばれるものです。例えばある画像の掲示時間が短く、ある閾値以下であった場合、人間はそれを知覚できません。ところが、明るい画像の場合は、この閾値が小さくなります。すなわち、明るさの閾値をLとし、掲示時間をTとすると、“LT=一定”という関係があるのです(ただし、Tは100ミリ秒以下のとき成立)。
この法則を応用して、擬似的な3D眼鏡を作ることも出来ます。どういう眼鏡かと言うと一方だけがサングラスになっている眼鏡です。この眼鏡で動きの速いTV番組を見れば、左右の目で画像の知覚にタイムラグが生じ、結果として3D映像が認識されます(あくまでも擬似的にですが)。
著者が述べたレーザー光に話を戻せば、レーザーは煙の中を通って、その軌跡が見えているわけです(チンダル現象)。そうすると、光は少しずつ散乱されているので、当然ながら先に進む程、暗くなります。このため、ブロックの法則に従って光源から遠い方の知覚が遅れ、結果的に、レーザー光がすぅーっと煙の中を飛んでいくのが認識できるというわけです。
ですから、著者が『光の速度を見た』と感じたのは確かでしょうが、それは光速が目で認識出来る程遅かったからではないのです。
思うに、ここで述べたような現象において、『光速度は目で識別できる程遅い!』と短絡的に結論つける事は確かに問題ですが、だからと言って『そんな事は有り得ないから間違っている』と早急に結論付けるのもどうかと思います。それでは進歩というか発展性が無い。
この話題では、人間の視覚における研究対象が埋もれていたわけで、『有り得ない』と一掃してしまっていたなら、この視覚特性の発見まで消えてしまうのです。人はよく正解から学ぼうとしますが、間違いから学ぶことも同程度に重要だと言えるでしょう。
自由落下するエレベータの中
この章では、重力場中を自由落下するエレベータ内を進む光についての思考実験が登場します。
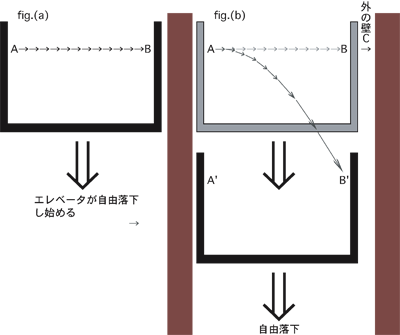
fig.(a)およびfig.(b)は、共にワイヤーの切れた状態のエレベータ内部を表していますが、fig.(a)はエレベータ内にいる観測者(エレベータと共に落下する観測者)から見た図であり、fig.(b)はこのエレベータを外の重力場中に留まって観察している観測者から見た図です。
まず、相対論でどのように説明されているかを述べます。fig.(a)の場合、観測者はエレベータと共に落下するので無重力状態と等価であり(等価原理)、エレベータ内に浮いたような形となります。このとき、Aから真横へ出た光はそのまま直進してBへ進みます。
Fig.(b)では、観測者は外の地上などに立っており、エレベータは自由落下をしていると観測されます。このとき、重力によって光も落ちるので、Aから出た光は次第に下を向き、結果的にはFig.(a)と同様、B'へ当たります。
これに対し著者は、
Aから発したレーザービームはBには届かないのです。例えば1000分の1マイクロ秒だけレーザーをパッと発射しますと、約30センチの光束となって光速で飛んで行きますが、飛んで行く間にエレベーターは下の方に行ってしまいますから、Bには到達せず、エレベーターの外の壁Cに当たります。B'に行くというのはアインシュタインの勘違いです。
と述べます。この結論の場合、エレベータ内にいる観測者(エレベータと共に落下する観測者)が見ると、Aから出た光が上方へ反り上がっている風に見えることになるでしょう。
著者は後の『静止とはどういうこと?』という章で同種の考察をしており、この点に関しては首尾一貫しています。
相対論の主張と著者の主張とで、どっちがもっともらしいかは、人によって意見が異なるでしょうし、これ以上議論を続けても始まりません。著者が強調しているように、等価原理は仮定に過ぎないのですから。問題を解決するには、どちらが正しいか・・・要するに、光が重力で曲がるか曲がらないのかを実際に観測するしかありません。
この曲がりの直接的観測の最初の例は、太陽近傍での光の曲がりの観測です。A.S.エディントンが1919年に日食を利用して、太陽周辺の星の映像の写真からこの曲がりを発見しております。
余談ですが、アインシュタインは1911年(一般相対論はまだ生まれていないが、等価原理には既に気付いている時期)に日食時の観測法を思い立つのですが、その時アインシュタインが提出した曲がりの角度計算は間違っています(実際の値の半分)。そして、一番近い日食の日は1914年8月21日のクリミアであり、これに合わせてE.フロイントリッヒ率いる観測隊が組まれました。ところが同年6月28日にオーストリア-ハンガリー皇太子が暗殺され、8月1日にロシアに対するドイツの宣戦布告がなされます。いわゆる第一次世界大戦の勃発です。観測隊は既に敵地内で観測準備をしていましたが得体の知れないやたらと性能のいい光学機器を所持した集団が不審がられない筈はありません。同日スパイとして逮捕され、結局、観測は出来ずじまいに終わってしまいます。アインシュタインが自らの間違いに気づいたのは1915年末なので、もしもこの時に観測が滞り無く行われていたら、観測結果が理論に合わないことになり、例え翌年に正しい理論が登場したとしても後だしジャンケンぽくなり、あれほど騒がれなかったかも知れません。人間万事塞翁が馬です。
余談の余談ですが、このエディントンの観測に始まる十数回に及ぶ日食観測は、結構バラバラな値が出ていて、現在では歴史的価値はありますが、定量的にうまくいったとは言えない状況です。まあ誤差は実際の値(1.75秒)より30%くらいぐらついているだけですから、一応これだけでも検証にはなっています。
もっとも最近では、わざわざ日食の時を選ばなくても電波望遠鏡で太陽近傍を通ってやってくる電波をキャッチしてその曲がりを測っています。もっと直接的には、火星に降りているバイキングへ電波を送り(火星が太陽を挟んで反対側へ行く段階の話)、その電波が太陽近傍を通って遅れる事も発見されています。太陽と水星の近日点移動の測定だけでなく遠い連星系の近日点移動の観測なんてのもあります。観測精度は当時の比ではありません。
この当たりの一般相対論の検証話は、著者も別章で取り上げていますから、その時また反論しましょう。
話を元に戻しまして、著者の次なる反論点を取り上げます。著者はFig.2において次のように論じます。
アインシュタインは1905年の特殊相対性理論の基礎となった論文の第1ページに、「光は常に、光を放出する物体の運動状態によらない一定の速度cで伝播する」と仮定しています。そう言いながら、図1のようにAから発した光はB'に行くと考えているのです。矛盾していませんか? 明らかにこれは物体と同じベクトル量です。なぜならエレベータの速度がもっと早かったら、B'は下の方にあります。これでは光の速度は一定ではないし、光源の運動によっていかようにも変わる現象です。
この引用中で『図1』というのは、ここでの『Fig.(b)』の事です。
まず基本的に、重力場中の光の運動についての反論に特殊相対論の仮定を持ち出して論破するという方法論に問題があります。「光は常に、光を放出する物体の運動状態によらない一定の速度cで伝播する」という仮定は、特殊相対論に基づく慣性系での話であり、一般相対論に基づく重力場内では違います。重力場内で光の速度が一定ではないということは、1911年にアインシュタイン自身が述べています。
一般相対論で考えれば、光を光速と観測できるのは観測者の近傍だけであり、観測者から距離を隔てた地点の光速度は変化します。ですから、光の速度はどの場所を観測者が見るかによって変化するというのが一般相対性理論の結論であるので、著者の反論は反論になっていません(もっとも、この部分は確かに色々な人が誤解を生む部分であるようです。上記の表現も多少語弊があります。実際に”見る”のは手元にやってきた光だけであり、この光は常に一定の光速度なのです)。
また、著者の言う『光源の運動によって光速度が変わる』という部分は明らかに誤解を含んでいます。光をまるで物のように扱っているのが相対論だと思っているようです(^_^;)。
著者は次のようにも述べています。
「そんなに光を物体のように扱いたいのなら、じゃ、光を減速して、半分くらいのスピードにできますか? 無重力に中で光をフワフワ浮かす事ができますか?」と聞きたいのです。
上述したとおり、減速した光を間接的に観測するのは可能ですし、
止まっている光を見ることもできます。ただし、光を物体のように扱っているからじゃありません。
富士山頂と海辺のように、高度が異なる場所での時計の進み方が違うことは実験によって確かめられているのですが、富士山頂での光を富士山頂の時計で測った場合の光速度も、海辺での光を海辺の時計で測った場合の光速度も同じなのですから、富士山頂から海辺を走る光を見れば、その光は遅くなっているのです。
もっとも顕著なのがブラックホールの表面を走る光でして、遠くから見れば、その光は止まっているのです。ただし、ブラックホールに落ちた観測者が手元の光を観測すれば常に一定の光速度を観測します(こんな特殊な場合でなくても、手元の光は常に一定です)。このように、重力場では光が減速して通過することは当たり前で、ちゃんとシャピロ遅延という名前まで付いてます。この遅延効果は光が重力場で曲がることによって生じる光行路長の伸びによる遅延よりもずっと大きいため、一般相対性理論の検証実験の1つとして利用されています。
著者は、特殊相対論から一般相対論に行く過程で、このような一般相対性原理が導入されているという事を知ってか知らずか無視しているようですし、その検証実験が多数行われていることについてほとんど言及する箇所がありません。
それから著者の発想で一番おもしろいと感じたのが、
横浜で閃いた私の考えは、「光は光源がどんな運動をしていようと関係なく、一旦出れば光速で空間を伝わっていく電磁波だから、見掛け上、光速度は変化するものだ」ということです。
という著者の
発見です。これが中学生の発見ならば確かに先見の明があります。ただ、高校に入ると『波』の単元で、波の速度は波源の運動によらないという事は必ず習いますし、ドップラー効果はこれを理解していないと説明できません。
事実、高校では、光のドップラー効果(非相対論的なもの)の問題も出てくるのです。ですから、このような事は
高校生の段階で当然知っているべき知識であり、後になって閃くような代物ではありません(少なくとも著者は大学の工学科に籍を置いていたのですから)。
このような予備知識が100年以上前の人々にあったからこそ、エーテル理論が作られマイケルソン・モーレーのような実験が行われたのです。
マイケルソン・モーレーの実験
冒頭の部分ですが、少し引用しますと、
相対性理論を語る時にいつも出てくる有名な実験の一つに、マイケルソン・モーレーの実験というのがあります。もう100年以上も前の話ですが、今でも科学者は、あの実験は非常に重要で、相対性理論の裏付けになるものだと固く信じています。
と書いてあります。まあ内容的にはこれで間違いないのですが、『相対論は間違っていた』という主張の
通俗本では何故かこの古ぅ〜〜い実験に対する反論が多いのです。
つまり、この実験の後に、全然実験が行われていないかのような表現がなされます。多くの相対論否定本の通俗書では、この実験当時の精度はあてにならないというような主張もみられます。マイケルソン・モーレーの実験の重要性は、現代に至っては、世界で初めて行われたという
歴史的実験として重要なのであり、その
精度を云々するのならば、
もっと最近の同種の実験を調べればいいのです。当然ながら、歴史的実験の後には、地道だけどより精度が上がった追試実験が山のように存在します。逆に言えば、同種の追試実験が山のように登場すればする程、一番最初の実験が後世に語り継がれるのです。1回だけ行ってその後誰も顧みなかったような実験や論文は、重要では無いと万人が認めたようなもので、単に忘れ去られるだけです。
そういうわけで、マイケルソン・モーレーの実験は、その後の歴史の中で営々と受け継がれた同種の実験のプロトタイプとして知れ渡っているのであり、当然ながらこの実験は現在でも行われています。一例を以下に挙げます。
| 実験者名 | 実験年 | |
| Michelson | 1881 | 初めての実験(Lorentzが実験ミス指摘) |
| Michelson & Morley | 1887 | いわゆるM&M実験と呼ばれている実験 |
| Morley & Miller | 1902-1904 | 実験室でやらず、あえて丘の上で実験 |
| Miller | 1921 | ウィルソン天文台にて(エーテル発見?) |
| Miller | 1923-1924 | |
| Tomaschek | 1924 | |
| Miller | 1925-1926 | |
| Kennedy | 1926 | |
| Illingworth | 1927 | |
| Piccard & Stahel | 1927 | |
| Michelson | 1929 | Michelson最後の実験(1931年死去) |
| Joos | 1930 | |
| Kennedy & Thorndike | 1932 | 装置の腕の長さが違う実験 |
| Jaseja他 | 1964 | レーザーによる実験 |
適当に調べたのでいい加減ですが、現在に至っては大学の学生実験で行われているレベルですから、この他にも無数の実験があります。また、別の方法のエーテル検出実験も多数存在しています。
要するに『マイケルソン・モーレーの実験』と言う場合、1887年の実験そのものを示すという使い方よりは、マイケルソン・モーレーの実験を初代とする一連の実験に対して使われる場合が多いと考えるべきでしょう。上述したように、マイケルソン・モーレーの実験は、初めて(ミス無く)行われたプロトタイプとしての歴史的な価値があるのです。
こういう事は、例えば『エディントンによる日食を利用した光の曲がりの測定』などに対しても同様です。この観測がたった一度だけ行われたわけではありません。
よって『古い実験を固く信じている』というような印象を与えるのは間違いで、『ずぅ〜っと疑い続けているが、未だに否定的結論は出ていない』と考えた方がいいでしょう。
そもそも『信じている』という表現は使えませんね。例えば「あなたは浮気をしてないと信じている」と言った後、留守電やメールのチェック、手帳のチェック、素行調査等あらゆる事を現在までずぅーっと続けて「信じている」とは言わないでしょう(^^;)。「疑っているが、今までの結果からはボロは出ていない」とすべきですね。
また、余談ですが(余談が多い!)、科学者は300年以上前のガリレオの『ピサの斜塔実験』さえも疑っていて現在も実験しています(ちなみに、ピサの斜塔実験自身は弟子のでっち上げなので、ガリレオ自身はそんなことをしてませんが)。それから、ニュートンが仮定した『リンゴが落ちる力も月が回転する力も重力による』という事さえ疑っていて、アポロ宇宙船が月に置いてきた鏡を使ってこれを検証していたりします。
このような実験を行う態度が『信じている』態度でしょうか? どちらかというと教科書に載っている事を信じてしまうのは、科学に携わっていない人ではないかと思ってしまいます。
『アインシュタインの相対性理論は間違っていた』という本が、科学の疑う態度を示してくれるとすれば、内容の正誤に関わらず、有用な事だと思われます。
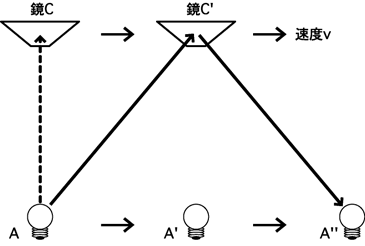 さて、ここからマイケルソン・モーレーの実験に対する著者の考えの間違いを指摘していきます。まずは著者の主張を述べることとしましょう。以下はその要約です。
さて、ここからマイケルソン・モーレーの実験に対する著者の考えの間違いを指摘していきます。まずは著者の主張を述べることとしましょう。以下はその要約です。
左図のような光源Aと鏡Cがあったとしましょう。この2つは連結されて同時に左から右に動いています。つまり、最初はACの関係だったのが時間がたつとA'C'に移動し、その後A''C''と動く訳です(C''は図中に描いてありませんが)。
Aから出た光が鏡で反射して戻ってくる為には、図のA→C'のように、斜めに光が出てなければなりません。もしもAからC方向に飛んだ光の場合、光がCの場所に到着した時には鏡は既に移動しており、光は反射して戻ってきません。光はボールとは違って光源の運動に左右されませんから、光源Aから出て行く光が、真上に届くように調整されているのならば、Aから出た光はAが止まっていようとも動いていようともCへ到達する筈であり、決してC'には行かないというのが、著者の主張です。
実際に著者がどのように書いているかと言うと、
ここでも光をボールみたいに考えているから、こういうことになるのです。光は一旦光源から出たら、もう光源には関係なく光速で伝わるのですから、Aから出た光の先頭は、図3の点線のように鏡Cの方にすーっと行って、その間に鏡CがC'に行けば、反射することなく二度とAには戻ってきません。反射して戻ってきている光は全然別物の、球面波の後続波なのです。時間的に異なる全然別の波面なのです。
という具合に書かれています。お分かりだと思いますが、この引用中の『図3』というのは、上に示した図の事です。
とりあえず著者の認識上の間違いは、マイケルソンやモーレー及びアインシュタインは『光をボールみたいに考えている』と思い込んでいる部分です。この実験当時、『光をボールみたいに考えている』全うな科学者はいません。
光が、粒子かはたまた波かという議論はニュートン時代から議論の的でしたが、1807年の有名なヤングの実験(スリットを通して光を干渉させる実験)により波動説に軍配が上がりました。
よって、著者の主張のように『光は一旦光源から出たら、もう光源には関係なく光速度で伝わる』というのは、当時誰もが知っている共通認識です。マイケルソン、モーレー、アインシュタインその他諸々の科学者の中で、これを否定している人はいません。波の伝搬速度は波源の運動には関係なく、波の媒質の速度に依存します。だからこそ、マイケルソンとモーレーは、光を伝える媒質(エーテル)の移動速度を検出しようと試みたわけです。この点は著者の認識不足、あるいは勘違いでしょう。
また、AからC'に飛んだ光は『Cへ行った光とは全然別』であるとしています。声を大にして言います。当たり前です。Cへ行った光は戻ってこないのですから。マイケルソン・モーレーの実験で干渉している光は、AからCへ行った光ではなく、AC'A''と戻ってきた光です。Cへ行った光ではありません。
著者がこんな当たり前の事をことさら強調するのにはわけがあります。著者は、当時の物理学者が揃いも揃って、このことに気づいていないと思っているからです。
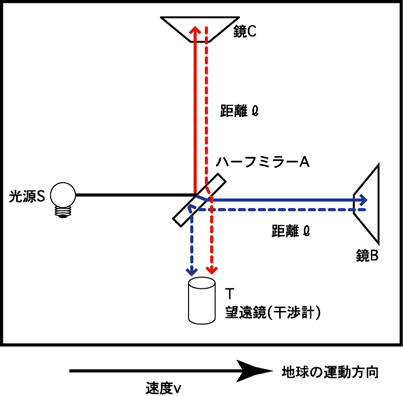 ここでマイケルソンとモーレーの実験のおさらいをしておきます。この実験は、光源から出た光をハーフミラーで90度異なる2方向に分離し、行く先にある鏡から戻った光を再び融合させて、その干渉縞を観測することで行われます。すなわち、経路1は、S→A→B→A→Tと進みますが、経路2は、S→A→C→A→Tと進みます。
ここでマイケルソンとモーレーの実験のおさらいをしておきます。この実験は、光源から出た光をハーフミラーで90度異なる2方向に分離し、行く先にある鏡から戻った光を再び融合させて、その干渉縞を観測することで行われます。すなわち、経路1は、S→A→B→A→Tと進みますが、経路2は、S→A→C→A→Tと進みます。
干渉縞の明暗の位置は2つに分かれた光の経路の差によって移動することになるので、装置全体を回転させれば干渉縞の移動が現れると思われていました。すなわち、装置を90度回転させれば、経路1と経路2の立場が逆転するので、干渉縞の明暗の位置が変化するだろうと考えられたわけです。
先に述べておきますが、AB間とAC間の距離を、光の波長に比べて十分小さい誤差まで完全に一致させるのはほとんど不可能ですし、また、2つの経路を完全に90度にするのも難しいでしょう。ただ、そのような場合でも、装置を回転させて干渉縞の移動を見るという実験には支障がありません。それどころか、わざとAB間とAC間の距離を異なるものとした実験もあります(その意義は後章で…)。
なお、著者はこのA→C→Aと光が進むの部分に対し、そこはA→C'→Aであり、C'に届くのは球面波の後続波だと主張するわけです。この装置を速度vで動いていると見る観測者にとってはもちろんその通りです。ただし、著者はこの指摘には真っ向から対立する主張を持っており、そこが著者の最大の間違いなのですが、この部分のコアな説明は次章で再び述べられていますから、そこでキッチリと反論することにします。
また、著者が本気なのかどうか分からない主張も、この章にはあります。それは、光は一定速度で伝わるとするアインシュタインの主張に対し、
本当は光は決して一定の速度ではありません。空気中と真空中では伝わり方が違いますから、地球から出た光の速度はどんどん変化しながら宇宙空間に飛んで行っていますし、海中でも速度は変わりますし、雨の日と晴れでも違いますし、宇宙空間といっても何もないわけではなく、水素分子をはじめたくさんの宇宙塵やダークマターが存在し、そのために波長は変わるし、速度も異なってきます。
と述べます。再び声を大にして言いたい。
当たり前です。
もっとも、著者は最後の方に、全く物質のない宇宙空間を進む光の速度は一定でCとしてよいと述べてはいますが、それならば、なぜわざわざ当然のことを書くのでしょうか? 少なくとも相対論を云々する前に、これは一般常識と言ってよいと思います。水による光の屈折は、光の速度の変化でおこるとか言う事は、下手すると小学生でも知っていることです。
でもこういう主張をアインシュタインの『光速度一定』の反論として掲げている本が売れているという事は、意外と知られていない事実なのかもしれません。
少し歴史的な経緯を述べましょう。最も最初に光の速度を算出したのはO.C.レーマーですが(1675年)これは天文学的な観測によるもので、概算でしか無く、空気中と水中の速度差がどの程度違うかというレベルの話ではありません。初めの精密実験は1849年で、A.H.L.フィゾーが高速回転する歯車を使って空気中の光速度を計りました。その翌年、高速回転する鏡を使ってJ.B.L.フーコーが空気中と水中両方の光速度を測定し、水中の光速度が空気中の光速度より遅くなることを確認しており、更に翌年には、再びフィゾーが高速の水流中を通る光の干渉実験によりこれを追認しています。なお、フィゾーの干渉実験は後にマイケルソンとモーリーにより高精度で追実験されていたりします(1886年)。何故このような測定が必要になったかと言えば、光が粒子であるか波であるかの論争に決着を付けるためでした。光が空気中から水中に入る時に生じる屈折は、粒子説の場合は光速度が増大するために屈折すると説明されており、逆に波動説では光速度が減少するために屈折するとされたため、実験がなされたのです。
よって、当時の科学者は、真空中で無い限り光は決して一定の速度ではないなんてことは当然知っていたことになります。また、この一連の実験で光が波であることが再度証明されたわけであり、『光をボールみたいに考えている』ことはあり得ません。
もちろん、アインシュタインの光速度一定というのは、空気中云々の変化等というものを示したのではなく、全て真空中の話です。水中ならば水中の光速度を越える物体もあります。要は、有限速度としての真空中の光速度Cを述べているだけです。水中でも空気中でも、その場所での光速度を越える物体というものは存在しますが、真空中の光速度を越えるものはないという事です。
相対性理論が間違った方向に行くきっかけとなった式
先程のA→C'に光が行くという部分で、著者は次のように言明しています。
もし、どうしてもC'の時点で鏡に反射させたかったら、予めそっちの方向に光を発射しておかないといけません。
つまり、著者は、
光がCの方向に行くように調整されているのならば、装置全体が止まっていると観測する観測者から見ても、装置全体が動いていると観測する観測者から見ても、光はCへ行くと主張するのです。
この部分が著者の主張のキモです。簡単に言えば、著者が間違った方向に行くきっかけとなった考えです。著者自身も十分承知していて、
しつこいかも知れませんが、もう一度説明しますと、アインシュタインは「静止系と慣性系は区別できない。だから静止していても、動いていても、中の人はAからCに向けて発射した光はA→Cに行くように観測する。外部の第三者にはA→C'に行ったように見える」と考えているのです。
私はそうではなく、「物体の運動はガリレオの相対性原理に従うので、静止系と慣性系は区別できない。ところが光は電磁波なので、A→C'の方向には行かない」と考えているのです。
と念を押します。つまり、装置の進路方向横向きに発射した筈の光が、装置と相対速度を持った
第三者から見ると、前方に傾いて出るように観測される考えるのがアインシュタインであり、そうではなくて真横のままであると考えるのが著者です。
どちらが正しいかは
思弁だけでは判断することはできません。実験や観測によって決着が付くものです。そして、実は
特殊相対論の誕生以前に決着が付いているのです。
まず、歴史的な背景から考えて下さい。19世紀末には、光は波であるとされていました。そして、光波を伝搬させる媒質としてエーテルが考えられており、物理学者はエーテルの流れを探すのに躍起になっていました。また、最新理論であったマックスウェル電磁気学はガリレオ変換によって変形することも知られていました。さらに当時はまだ完全なローレンツ変換は存在しません。マックスウェル方程式がローレンツ変換によって不変になるということを、電荷や電流がある場合も含めて、初めて完全に証明したのはポアンカレ(1905年)で、そのおよそ1ヶ月後にアインシュタインの特殊相対論の論文が出て、独立にこれを証明したわけです(冒頭の『誰もが思う「アインシュタインがまさか!!」』の章参照)。
19世紀末当時を考えると、著者と同じ考えの人がウヨウヨいたのです。特に珍しいことではありません(19世紀末ならば)。実際に、マックスウェル方程式が成立する特別な静止系があり、それ以外の座標系では光速は変化するとして計算された、ヘルツの方程式があります(1890年)。ヘルツは、あの周波数の単位[Hz]に名を残しているヘルツです。すなわち、19世紀末ではマックスウェル方程式が成立するのは特別な慣性系であり(エーテルに対して静止)、それ以外では変形するという考えがまず提案されたわけです。そして、本当にヘルツの考えが正しいか否かは実験によって証明されるものです。
詳しくは述べませんが、コンデンサーの中に入れた誘電体を回転させたレントゲンの実験(W.C.Rontgen)およびウイルソンの実験(H.A.Wilson)。また、両端が帯電している棒がエーテル静止系に対して動いている場合に作用する筈の偶力を調べたトールトンとノーブルの実験(F.T.Trouton & H.R.Noble)などにより、ヘルツ方程式は間違っていると実証されたのです。
そもそも特殊相対論の発表以前に、ローレンツ収縮や時間の遅れの議論が出てきたのは、これらの実験結果を説明するためです。
なお、現代においては、レーザー装置や粒子加速器などが発達していますから、アインシュタインと著者のどっちが正しいかを示す実験は非常に簡単です。
例えば宇宙船に積んだレーザー装置が、静止時において進路方向横向きにレーザーが出るように調整されていた場合を考え、この宇宙船が一定速度で動き出した後を考えます。
著者の主張が正しいならば、宇宙船が動いたとしてもレーザーの進む方向は第三者から見て変化有りません。このとき、レーザー光線はA→C'に行かずA→Cに行くと主張しているのですから、宇宙船の壁に当たっているレーザー光線の光点は、宇宙船が動くことによって場所が変化します。著者自身も実際にそう思っていて、後の章(例えば『私の提案する実験装置』や『静止とはどういうこと?』参照)で何度もこの話が出てきます。
続いて、アインシュタインの主張が正しいとすると、宇宙船が動いた場合レーザーの進む方向は第三者から見て進行方向前方に発射されるようになります。このとき、レーザー光線はA→C'に行くと主張しているのですから、宇宙船の壁に当たっているレーザー光線の光点は、宇宙船が動いても場所は変化しないことになります。
著者の主張は理路整然としていて、ブレや自己矛盾がありません。そういう意味で、著者の主張は科学的です。ここは強調しておいてよいと思います。だからこそ、科学的に完全に否定出来るのです(反証可能)。著者は単に、100年以上前に実験によって否定されているという事実を知らないか、あるいは内容を理解する能力がないだけに過ぎません。なので、粛々と間違いを指摘すればよいのです。
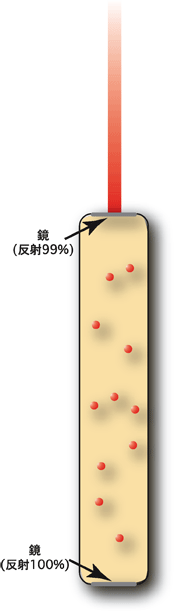 実はレーザーの場合は、発振機構まで遡って考えると、著者の間違いを思考実験だけで割と簡単に指摘することができます。
実はレーザーの場合は、発振機構まで遡って考えると、著者の間違いを思考実験だけで割と簡単に指摘することができます。
レーザーは封入された筒の中の元素による共鳴現象によって生じます。つまり、なんらかのガスをガラス管等に封入しておき、そのガスを常に励起状態にしておきます。その中の1つのガス分子が基底状態に戻る時、元素に特定の周波数の光を発射しますが、この光が別の元素の横を通ると、誘導放射という現象により、横を通られたガス分子からも同じ光が出ます。この光は位相がピッタリ合って放射されます。
後はその過程がドンドンと繋がっていって、位相が揃った大量の光が取り出せるという寸法です。(専門的な話になりますが、共鳴する周波数がガス分子によるか、それともガスを封じ込めた筒の長さによるかという問題もありますが、ここでは割愛します)。
一度に大量の光子を出すのは中々難しいですし、大量のガス分子を光が通る間に一瞬に励起させるのも困難です。よって大抵の場合は図のように鏡で反射させて、何度も管の中を往復させ、1%だけを外に取り出すという方法を使います。
また、SDI計画に使われそうになった超短光パルスレーザーの場合は、このような往復はさせず、一気に絞りだしてしまいます(SDI計画の場合、エネルギー源は核ですから、このような無茶も可能)。著者はレーザーパルスの話を引合に出していますから、こちらの方がいいのかも知れません。もっとも超短光パルスレーザーはこんな物騒なものだけでなく、色々と使われてます(そのものずばり『超短光パルスレーザー』という専門書もあります。値段が6000円くらいしたので趣味では買えませんでした。
話を元に戻します。レーザーが発振される為には、光が発射された先に別のガス分子がなければなりません。著者が述べたようにAからCへ光が発射された場合は、そのうち発振器の壁にぶつかり光が往復できなくなりますから、発振しなくなってしまいます。
よってレーザーが発振する方向というのはC'へ行った光のみということになります。
もっとも、レーザー装置の移動速度の変化が光速度に比べて小さい場合は、著者の主張が正しかったとしても全く発振しないということはないでしょう。ただし、そのような場合でも、レーザーの放出する方向が微妙に異なることになるので、それを検出するような実験を行えばよいわけです。このレーザー光の実験の話は『私の提案する実験装置』という章で筆者が提案してますので、その時具体的な実験事実も踏まえてもう一度説明します。
次にもっと直接的な実験結果がはっきり出ているものを例として上げます。宇宙船にレーザー装置を乗せて飛ばす実験を実際に行うとしても、少し未来の話になりそうですが、素粒子加速器で電子を加速して、電子が出す光を観測するという事は既に行われています(Codling:1973)。
電子を加速器でグルグルと加速するとシンクロトロン光という光を放射しますが、電子の速度が速くなると、この光が前方に集中するのが観測されています。もちろん相対論による理論値とピタリ合っております。
電子に予めそっちの方向へ光を出すように細工したとは考えられませんので、著者の考えは既に否定されている訳です。
それにしてもこのシンクロトロン光を利用した放射光実験施設(フォトン・ファクトリー)は筑波にあるSpring-8を始め、各国でかなりの数が既に実用化されているのですから、このようなこと(移動する光源からの光はA→CではなくA→C'へ行くということ)は、そのスジの人なら常識的な事実ですし、ちょっとした書店によればこの事実はすぐ調べられます。今ならインターネットで検索すれば一発です。著者はこの事実を全く知らなかったのでしょうか?
なお、この章でも、
海中や空気中では光速は異なります。空気中と宇宙空間では、また違います。太陽の近くの微粒子が引力によっていっぱい集まった場所でも、また違います。このように光速は決して一定ではありません
と念を押します。もちろん、そんなことは相対論では何も否定していないのですが…。
マイケルソン・モーレーのミス
実は著者の直接的な相対論への反論(反論というにはあまりにも稚拙、あるいは100年程遅い指摘ですが)はこの章までです。後は自説を説いて、その自説が如何に相対論と違っているかということを述べているに過ぎません。
例えて言えば、野球のルールを『ホームランを打ったら走者の倍の得点とする』と独自に規定し、「このルールによれば、この試合は巨人が勝っている。直ちに間違いを訂正せよ。」と述べているようなものです。野球のルールの場合は人間が勝手に決めたルールなので改変は可能ですが、科学の法則の正誤を決めるのは自然であり、観測や実験によって調べられます。よって、この章をやっつけてしまうと後はグンとペースが上がります。実際の観測・実験結果を述べて、間違っていることを示すだけでいいのですから。
では、とっとと片付けてしまいましょう。
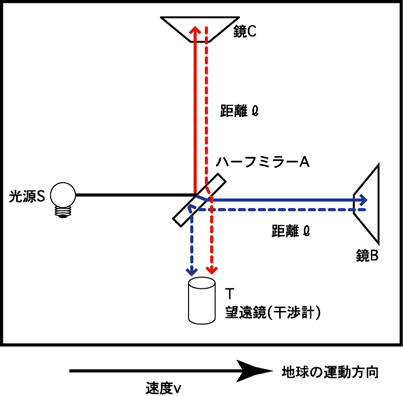 著者はこの章でローレンツ収縮の話をしているので、既出のマイケルソン・モーレーの実験の概念図を今一度描いておきます(同じ図を指定するだけだけど)。
著者はこの章でローレンツ収縮の話をしているので、既出のマイケルソン・モーレーの実験の概念図を今一度描いておきます(同じ図を指定するだけだけど)。
実際の実験では、光路長を延ばすため、鏡は一枚ずつではなく何枚もあるとか、ハーフミラーを通る光の位相ずれを補正するためのガラスが途中に入っていたりして、もう少し複雑な装置を使っています。さらに、装置上の部品は一枚岩で出来た砂岩に固定されており、スムーズに回転できるように、水銀のプールの上に浮いておりました。
この装置が光の媒質とされたエーテルの中を速度vで右に進んでいるとします。装置自身が、左向きにvで流れるエーテルの中に静止しているという風に考えてもいいでしょう。
湖面に投げた石の波紋は同心円状に広がりますね。ここで、川のように流水の上で石を投げると、同心円状に広がる事は同様ですが、波紋そのものが下流に流されていきます。エーテルの波として考えられた光もこれと同じで、一旦光源から出た光は左に流されながら広がっていきます。実験当時、A→B→Aと行く光は、行きはc-vの速度の光となり、帰りはc+vとなると考えられていました。よって往復時間は、
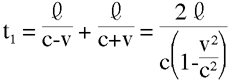 … 式1
… 式1
です。A→C→Aと行く場合は、舟が川を横断するコースですので、ピタゴラスの定理を使います。
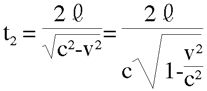 … 式2
… 式2
です。ここで2つの式は違っていますので、A→B→A経由とA→C→A経由でタイムラグが生じ(t1>t2)、装置を回転させると干渉縞が動くだろうとマイケルソンとモーレーは目論んだのですが、これが大外れだったのでした。
なお、当たり前の事ですが当時の技術が未熟で差が発見出来なかったわけではありません。地球の公転速度毎秒30km程度のエーテル流を検出するには十分な実験でした。現在の技術ならこの時の1万倍くらいの精度が出せますが、30[km/s]のエーテル流の検出に限れば、それは余分な精度です。
著者はこの説明の後、次のような文を続けています。
そこでアインシュタインは、「光速度はいかなる実験装置の運動によっても 一定の値cである」と仮定し、これを「光速度不変の原理」と名付けて相対性理論を作りました。その結果、「運動物体はその方向に短縮する」という相対性理論につきものの「奇怪な数式が現われ、つぎのようにマイケルソン・モーレーの実験を説明したのです。すなわちLは運動方向に縮み、

となるので・・・・以後略
この部分の説明だけを抜き出しますと、確かにその通りです(奇怪がどうかは別として)。ただし、マイケルソン・モーレーの実験から続けて考えると著者の思い違いがかなりあります。
まず、本論とあまり関係ない思い違いとしては、アインシュタインはこの実験を説明するためにローレンツ収縮を発見したのではないということです。まあこれは単なる科学史の誤認ですからいいでしょう。
問題なのは、このローレンツ収縮は光速度一定という仮定から導き出されたものでは無いということです。また、装置が収縮したとして実験を説明したのは、フィッツジェラルドやローレンツであり、相対論はその考えを否定しました。すなわち、皮肉な事に著者は相対論を擁護している立場にいます。
ローレンツ収縮というのは文字通りローレンツがマイケルソン・モーレーの実験を説明する為に生み出した代物です(ローレンツだけではありまんが)。ローレンツはこの収縮理論とそれを応用した電磁気学の説明において1902年にノーベル賞を貰っています。
で、ローレンツ自身は光速度一定という仮定は全く無しにこの収縮理論を発表しています。というより、見掛けの光速度が変わるからこそ、棒の長さを調節してつじつまを合わせる必要があるのです。
面白い話(よく知られた話かも知れない)を一つ。ここに登場した式変形と全く同じ式変形となった特殊相対論が後から登場するのですが、ローレンツはこの相対論の考えを否定しています(1909年初版、日本語訳『ローレンツ電子論』東海大学出版会)。
ローレンツやフィッツジェラルド等は
ニュートン力学の範疇でこの短縮理論を作ったのです。当然ながら時間の遅れなんてものは考えてません。
理論展開の順番としては、まずマイケルソン・モーレーの実験があって、最初に登場したのが、ニュートン力学の範疇における収縮理論だった。特殊相対論はその後の話です。
著者は、ここで二重の過ちを侵しています。ローレンツ達の収縮理論と特殊相対性理論とを混同し、著者自身が擁護しようとしているニュートン力学的な考えもろとも否定している。事実、
マイケルソン・モーレーやアインシュタインその他学者の理論計算というのは次のようなものです。
という前置きで、上述した計算を述べているのです。ある意味、著者と同じ発想でマイケルソン・モーレーの実験を捉えているローレンツ達に対して、このような
味噌も糞も一緒の反論をしては、ローレンツ達が浮かばれません。まず著者は、ローレンツ達の収縮理論とアインシュタイン特殊相対論の違いを把握すべきでした。
『誰もが思う「アインシュタインがまさか!!」』の時に、ローレンツの相対論をアインシュタインがちょっと直しただけという意味合いの事を書きましたが、表面的な数式はほとんど同じでも、その概念は確かに革命的に違っています。そのことに著者は全く気づいていません。実際に本著を読めば、完全に混同していることが分かります。
なお、ローレンツ達の収縮理論で得られた式1と式2に対する、アインシュタイン特殊相対論の帰結はどうなるかを述べておくと、

… 式3
および、

… 式4
となります。相対論は文字通り
相対運動がいくらかが問題なので、装置と観測者が同じ地球上にいて、相対速度が0ならば、ローレンツ収縮も時間の遅れも発生しません。
ローレンツ達の収縮理論(式1と式2)が正しいか、あるいは、アインシュタインの特殊相対論(式3と式4)が正しいかは、ケネディ・ソーンダイクの実験(1932年)によって確かめられます。この実験は、原理的にはマイケルソン・モーレーの実験と同等ですが、意図的に片方の光路を短くしている点に違いがあります。すなわち、収縮理論の場合は、エーテル流の方向に物体が短縮するということになりますが、光路の長さが元々違っていると、収縮の割合が同じであっても、縮む長さの絶対値が異なる筈なので、装置を回転させることで干渉縞が動くことが見込まれたのです。実際には干渉縞は動かず、特殊相対論が正しいということになりました。
ちなみに、著者が提唱している『光速度は見掛け上c−vcosθになっている』云々と言っている式はドップラー効果を説明する時によく使う近似です(もっとも使い方が多少違いますが^_^;)。高校の教科書のドップラー効果の部分を見て下さい。
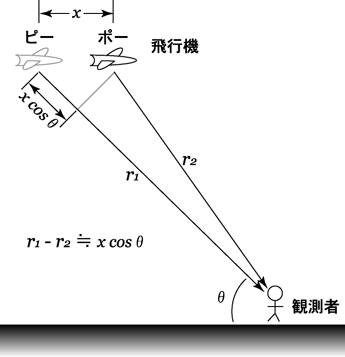 ただし、cosθが出ているので、高校生としてはちょっとややこしい部類の式になります。例えば『地上100m上空を水平に真っ直ぐ飛んでいる飛行機の音を地上から観測した場合の音のドップラー効果』を解くような問題には必須です。
ただし、cosθが出ているので、高校生としてはちょっとややこしい部類の式になります。例えば『地上100m上空を水平に真っ直ぐ飛んでいる飛行機の音を地上から観測した場合の音のドップラー効果』を解くような問題には必須です。
飛行機は移動しているので、その音はドップラー効果を受けるのですが、飛行機がピーポーピーポーと音を出しながら(それは救急車だ^^;)飛んでいるとすれば、ピーを出した後、ポーを出すまでに飛行機が観測者に近付き(この間に飛行機の動く距離をxとする)、そのために縮まるピーとポーの間隔が『xcosθ』と近似できるというモノです。
微分の考えを導入すれば、ピーとポーの間隔を限りなく小さくしていくことで、vcosθが登場します(この場合、vは飛行機の速度)。飛行機が真上に来た時にはθ=90度ですから、飛行機と観測者の距離は縮まりません。そこが最短距離ですから。
しかし、この式が本に書いてあるように、本当に、
世紀の大発見だとか、窪田の関係式として話題になっているわけです。
のでしょうか(そうするとドップラー効果そのものが
一般にはあまり知られていないものなのかな)? ちなみにドップラー効果が提唱されたのは1842年です。
なお、著者の計算は二度手間になっており、まずA→C’に行くとした後、改めてA→C’へ行く時間分だけ鏡がまた先へ行ったとして計算している事になります。そして、cosθをわざわざv/cという近似に直して計算結果を合わせ込みます。実はこの近似が、著者のもっとも大きな間違いです。なぜならば、マイケルソン・モーレーの実験はv/cのオーダーで表せない、v2/c2のオーダーの検出を目指したのであり、ここを近似式で書いてOKなら、実験する意味が全くないのです。
そもそも、マイケルソンがこの実験を行おうとしたのは、マックスウェルが『地上での検証実験はv2/c2のオーダー(〜10-8)の精度の実験をする必要があるため、不可能だ』と述べたことが発端になっており、『いや、工夫すれば今(19世紀末当時)の技術で十分検証できる』と奮起したという歴史的な経緯があります。まさに著者が近似で切り捨てた部分をマイケルソン・モーレーの実験で測定しているのです。
著者は次のようにも述べます。
なお、マイケルソン・モーレーの実験はまったく時間差がなかったわけでなく、いくらかは時間差があったのですが、それは誤差だとされて今日に至っています。
本当に著者は、この実験から現在に至るまで、追実験が一切行われなかったと思っているようです。今一度言いましょう。検証は今でも行われており、
精度は一万倍以上になっています。一万倍以上の精度で実験しても検出できないのですから、当時の時間差は誤差以外にはあり得ません。
私の提案する実験装置
ここ著者が提案した実験とほぼ同等の実験はJ.P.CedarholmとC.H.Townesによって1959年に行われました。2つのメーザーを互いに反対向きに飛ばし、筆者の言うようにメーザーの向きが変わると仮定して、その違いによるドップラーシフトを測定する実験です。もちろん測定結果にはなにも出てません。
著者は『是非この実験を一日も早く行うよう・・・』と述べてますが、40年以上遅れています。
著者はこの実験をよほど気に入ったのか、続編である『「相対論」はやはり間違っていた』でも述べていますので、もっと直接的な反論はそちらで行います。
アインシュタインの座標変換と私の座標変換
次の一文を引用するだけで著者の間違いは分かります。地球に対して光速がcで、vで進むロケットが発する光がやはりcだという著者の主張に対し、
ここまでくると多分アインシュタインは私に、「おいおい、君。ガリレオの相対性原理によれば、速度vのロケットから光を発したのだから、光の速度はc+vじゃないのかね」と反論するでしょう
地球に留まる観測者が見た場合、どのようなスピードのロケットから発射される光も、必ずcであり、それは相対論でもニュートン力学でも同じです。光の速度がc+vになるなどとはアインシュタインを含め誰も言ってません。著者のこの勘違いは、既に紹介してあるのですが、著者は、
アインシュタインは『光をボールみたいに考えている』と思い込んでいるために生じています。すなわち、勝手に相手がこう思っていると断定し、それに対して「間違っている」と主張しているわけです。
今一度、マイケルソン・モーレーの実験に戻って考えてみて下さい。実験装置の移動向きと同方向へ放出される光A→B→Aの計算がありましたが、A→B→Aと行く光は、行きはc-vの速度の光となるとして計算されていました。これに対して「おいおい、君。ガリレオの相対性原理によれば、速度vの装置から光を発したのだから、光の速度はc+vじゃないのかね」と反論した人はいません。当時の物理学者が光をボールみたいに考えていたならば、マイケルソン・モーレーの実験が出た段階で、多くの反論が出てきている筈です。
よって、この章の著者の反論は、
相対論では光速度がロケットによって変化するという
著者の間違った解釈を自らが論破しているだけですので、相対論への反論にはなっていません。著者の思い込みの中の相対論の主張を論破しているだけです。
光は直進する
著者は光はエネルギーを持っているので質量があり、それによって重力の力を得るとしています。この発想に基づいた計算はJ.ゾルドナーという人が1801年(1901年ではないよ!)にやってます。
また1911年にアインシュタインが計算したのもまさにこれです。著者と同等の計算(著者は計算してませんが)をしています。が、その後一般相対論が完成し、この光の曲がり方の計算は不十分(半分)だった事がわかりました。
日食を利用した光の曲がりの観測では、光が曲がるか曲がらないかを決定したのではなく、ニュートン力学による曲がり(光の質量を考えた曲がり)と一般相対論による曲がりとで理論値が違うので、そのどちらが正しいかを決定したのです。
よって著者の“持論”は1919年の時点で、観測によって否定されています。もちろん同時に、アインシュタインの1911年の考えも否定されていて、1915年の一般相対論の方が生き残ったのです。
引力も光速で伝わる?
著者は日食の時に、地上の日食が見える側と反対側の重力の測定を発案しています。これは単なる潮の干満現象の説明に過ぎません。
それから、本稿「『アインシュタインの相対性理論は間違っていた』は間違っていた」を最初に書いたのは1993年でした。そのとき、私はこう書きました。
なお、重力も光速度で伝わるという確証はまだなく、この観測と相対論とは無関係です。今後の実験が待たれるという事に関しては著者の主張はもっともです。
それから十数年経って、この発言を撤回する時がきました。
重力も光速度で伝わるという観測事実が出てきたからです。詳しくはアメリカ国立電波天文台(NRAO)の
プレスリリースをみて頂けばよいのですが、クエーサーの前を木星が通過するとき、重力が有限速度であることで生じるクエーサー像の光の曲がり方の変化を調べたもので、重力の伝達速度は±20%の精度で光速と一致しています。このプレスリリースの末尾にも書いてありますが、この方法は現代版のレーマーの観測のようなものです。
もちろん、今後、他のグループの追観測等が行われる必要がありますが、第一報としてはなかなかよい精度ではないかと思われます。
ところで、この章の後半には面白い記述があります。
ただし、こういう実験をするときは、相対性理論奉仕者は何とかして辻褄を合わせようとして時間や空間を歪めて合わせよう、合わせようとするに違いありません。重力による時間の遅れや空間の歪みなどを計算式の中に容赦なく放りこんできます。
当たり前ですが、一般相対論によって得られる結論は1つです。ですから、辻褄を合わせようとして時間や空間をさらに歪めたら、
それは既に一般相対論ではありません。もしも相対性理論奉仕者ならば、
理論的な部分は改変せずに実験や観察のあら探しをして間違っているというのではないかと。
等価原理の間違い
著者は一般相対論による帰結を知らないようです。ロケットの天井と足元にレーザーを置いて『同時に』発射させ、中央でぶつかれば、ロケットは重力場中に静止しているのだそうですが、一般相対論では重力場下方の方が時間の進みが遅いので、上からのレーザーの方が先に来ます。
よって『重力場ならば中央でぶつかる』という考えは相対論ではなく、著者独自の理論であり、著者独自の理論を著者自身が否定しているだけに過ぎません。
前にも述べましたように、重力場の上下方向での時計の進み方のズレは、既に観測されています。
静止とはどういうこと?
著者は『静止系と慣性系』を区別するという名目で、向き合わせた2台のレーザーを同時に発射する装置を考案します。中央で衝突したらこの装置は止まっているそうです。
反論は簡単です。
『同時に発射させる方法』を聞けばいいだけです。中央から時計あわせの信号を送ったりすると
著者の理論が完全に正しいとしても、『必ず中央で衝突する光を出すレーザー対』になってしまいますけど。
球面波だったら?
マイケルソン・モーレーの実験で、反射するのが球面波だったら、2つの別の波を分けて合成している事になるという主張の繰り返しです。
光速度不変の原理
地球から月へ光を発射する時と、ロケットをほぼ光速度で送り出す時とを比べて、地上からみると、その速さの差はほとんどないのに、ロケット内部で見るとやはり光速度は一定であるという部分に著者は不満のようです。
特殊相対論で考えれば、ロケット内の時計の進みはほとんど0に近いので、地上から見て、ロケットを光がゆ〜〜〜っくり時間をかけて追い越したとしても、ロケット内部でみれば一瞬の事です。
著者の反論が、これまた傑作なのですが…、
アインシュタインの相対性理論では、「地球と月の距離は観測者によって短くも長くもなるし、時間も地球上と宇宙飛行士では異なるので、そうなるのさ、観測者が違えば言うことも違うのさ。それが相対性理論の面白いところさ」と、結論されています。
物理学にそういう考えを導入してよいのでしょうか?
『そういう考えを導入してよいのか』と言われてもねぇ(^_^;)。問題は実験結果を理論が説明できるかどうかであって、好き嫌いの問題ではないのですが。
また、平行に走るレーザービームは見ることはできないという当たり前の事を著者は述べています。光が目に入ると見えるのであって、目の前を通過しても見えません。当たり前です。レーザー光をTVなどで写す時には、わざわざスモークを焚いて、散乱光が周囲に広がるように工夫してますから、これは常識(アニメや007ムーンレイカーあたりを見ていると案外非常識かも?)だと思います。
アインシュタインは見えると思っていたと著者は述べていますが、どこでそのように思ったのでしょうか?
月まで光は何秒かかる?
この章は珍しく計算問題が出ています。今までは単に著者の勘違いや実験事実の誤認ばかりでしたので、単なる科学史の再確認で終わっていました。まあ、この章の計算もユニークなものではないのでそれほど面白くはないですが、計算問題の場合は正否がはっきりするのでまだマシでしょう。
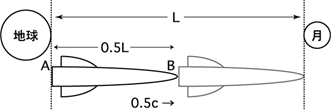 問題を要約すると次のようなものです。
問題を要約すると次のようなものです。
問題
地球と月の間の半分の長さのロケットがあり、光速度の半分で飛んでいます。図のようにロケットの最下部A地点で地球上から光が発射されました。地球から見た場合、光は何秒後に月に届くでしょうか。また、ロケットから見ればどうなるでしょうか?
著者はこれに対して、よく有りがちなミスを代表して述べています。外しどころを見事に外してくれています(ギャグの世界では、バナナの皮が落ちていたら滑って転ぶというような『お約束』という部分ですね)。
まず、著者が書いた図が違います(上に書いた図です)。ロケットの長さが地球と月の半分でという説明で、そのままそういう図を書いています。ロケットがこの長さのまま光速の半分で飛んでいたとすれば、ローレンツ収縮も何もしないことになるので、それは特殊相対論の議論ではありません。
またしても著者は自論を述べてそれを自ら否定するという行動に出ています。著者としては、ローレンツ収縮なんてあり得ないと思っているのかも知れませんが、相対論を否定したいのならば、ちゃんと相対論の帰結を用いて、そのことによって矛盾が生じるという結論を出すのがスジです。
間違って前提を述べて、間違った結果を示しても、何の証明にもなりません。
では、ロケットの長さは静止時に地球と月の間の半分ですので、このことを踏まえた上で、地球静止系からの観測と、ロケット静止系からの観測を別々に書きます。そしてそれら2つに矛盾がない事を示します。
まず、地球静止系ですが、Bを経由した地球−月間の時間は、L/cでした。Lの距離をcで進む光が走るとどれだけ時間がかかるかという事ですのでこれは当たり前です。
途中でローレンツ収縮をしたロケットのB点を経由した計算を加えても変わる筈がありません。著者は単なる計算違いだったのか、はたまたそういう思い込みかどうか分かりません。
ですが、著者の主張のように、相対論によって計算すると、
結局、このレーザー光は0.64+0.32=0.96秒で月に達することになります。
という結論は間違っているのはこれではっきりしました。相対論がそんな初歩的な間違いをしていたら、3日すら学会では生き延びれません。というか、論文審査の段階で落とされるので、日の目を見ることすらないでしょう。このような場合、どうしても持論を展開したいのならば、審査しているレフリーと徹底的に討論し、直すべきところは直すか、あるいは、
学術論文は諦めて、啓蒙書のような商業出版で出すかになるでしょう。
また、ロケット静止系の方も結論だけみればそれほど難しくありません。地球と月の間はL/γであり、それぞれ光速度の半分で左へ動いています。光(速度c)が地球から右に出て、月が左側へ光をお迎えにいってますから(速度c/2)見掛け上、光速度がc+0.5cになったのと同じです。よって光が月に到着する時間は、L/γをc+0.5cで割るという単純なものとなります。B点を経由しようがしまいが同じです。
物理の理論(物理だけではない)として、その理論自身が無矛盾であるという事は当然の事であり、そうでなければ誰にも認められません。
例えば、『双子のパラドックス』が特殊相対論発表後に問題となったのは、双方が全く相対的に見えると思われる場合に、一方の立場では地球に残った方が歳をとり、一方の立場ではロケットの方が歳をとるように思われたからです。その理論の通りに計算して矛盾がでる場合は、観測や実験結果云々以前に破棄されます。特殊相対論が破棄されなかったのは、双子のパラドックスでの双方の立場が『一方は加速度運動(=重力場)を体感し、一方は感じない』という、完全に相対的なものではなく、理論の適応外の現象を含んでいたからです。
これを解消するために一般相対性理論が生まれ、特殊相対性理論はその中の特殊な条件で成り立つものとして後に(まあ名前からしてアインシュタインは最初からそのつもりだったのですが)規定されたのはご存じの通りです。
ちなみに、ここで述べたような問題は、特殊相対論入門の本の演習問題として割とポピュラーなものです。参考書を2、3冊本屋でめくると必ず発見できるでしょう。
速度の合成則について
確か以前の話題でも出てきたように、著者は光だけを特別視して、常に光速で動くものとし、その他の物質はガリレイの相対性原理で説明出来るという主張です。ですから、0.8cで飛ぶ物体から0.8cの石を投げると光速度を越えるというような主張になっています。
この事の計算上の反論(?)は次の章に載ってます。
0.5c+0.5c=0.8c ?
この章では、また光速度の半分で飛ぶ、長さが地球−月間の半分のロケットが登場します。
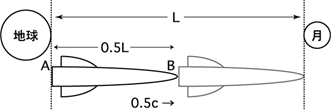 問題を要約すると次のようなものです。
問題を要約すると次のようなものです。
問題
地球と月の間の半分の長さのロケットがあり、光速度の半分で飛んでいます。図のようにロケットの最下部Aから、光速度の半分の速さの物体を投げます。物体の速さはいくらでしょうか? また、月に届くまでの時間を求めなさい。
著者はロケットの先端が月に達した時、物体もロケットの先端に達するので、物体は05c+0.5c=cとなると説明しています。そして、
この考えは一点の誤りもないはずです。物体に対するガリレオの相対性原理による計算ですし、地球の観測者から見たらとか、ロケットから地球を見たらとか、ロケットの観測者がどうのこうのというのとは違うからです。
と述べています。確かに、
ニュートン力学の範疇では、この考えは『一点の誤り』もありません。
特殊相対論はガリレイ変換を捨てて、ローレンツ変換を採用したのですから、「ガリレイ変換ではこのようになるぞ!」という主張は、
相対論への反論にはなっていません。
もしこれが、「ローレンツ変換によるロケットの縮みや時間の遅れを考えたらこのような矛盾が出るぞ」という反論ならば、それは相対論への反論になるでしょう。
で、著者は、
もし、地球から見て、ロケットの長さが短くなるとか、時間が遅れるとか、地球と月の間の空間が曲がっているからと言うのでしたら、そのように計算してください。どんなに計算しても1.28秒にはなりません。光が光を追い越す、そういう結果になります。
と述べているので、光が光を追い越すような計算には
ならないことを示します(もっとも、地球と月の間の空間の曲がりは全く必要ありませんが)。ここで、1.28秒というのは、光が地球から月へ行く時間ですから、物体が0.8cという相対論の帰結通りの速度になることを示せばよいことになります。
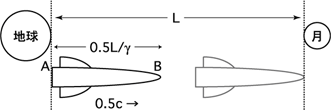 図は前回と全く同じです。著者がローレンツ収縮を考慮していない点も同じなので、これを考慮します。ロケットは1/γ倍に縮んでいます。で、この中で光速の半分の物体を投げるのですが、光速の半分と観測するのはロケット内でのことですので、ロケット内の時計で計算せねばなりません。
図は前回と全く同じです。著者がローレンツ収縮を考慮していない点も同じなので、これを考慮します。ロケットは1/γ倍に縮んでいます。で、この中で光速の半分の物体を投げるのですが、光速の半分と観測するのはロケット内でのことですので、ロケット内の時計で計算せねばなりません。
ロケット内部の観測者は、ロケットは縮んでおらず、ロケット長はL/2だと測ります。そしてロケット内部の観測においてc/2の速度の物体を投げますから、AからBへ達する時間は、

になります。ただし、Bに物体が着いた事をAに乗っている観測者が知るには、Bに到着した物体の光がAに届いてからになります。もちろん、Aにいる観測者は、この光が届く時間を差し引いて計算します。
すなわち、Aから出発した物体がBに届いた事をロケット内部のAにいる観測者が知るのは、
 …式(A)
…式(A)
時間たった後なのですが、L/2cという時間は、Bに到着したという映像の光がBからAへ届く為に必要な時間ですから、これはAの観測者が差し引いて考えます。
で、この計算を地球上にいる観測者が再検討するとどうなるかです。まず求めるべき『物体を地球上から見た速さ』をvとします。Aから出発してBに到着する時間をまず求めますが、ロケットの長さがL/2γであり、なおかつロケットそのものが光速の半分で動いている事を考慮せねばなりません。すると、求める時間t1は、
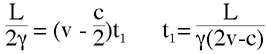
となります。そして『Bに物体が届いたという映像がAへ伝わる』という計算も、ロケット内の観測者とは異なります。
ロケット内部ではロケットは止まっていると感じているので、L/2cだったのですが、地球から見れば、ロケットは縮んでいるし、Bへ届いたという映像がAへ伝わるのを、Aが光速度の半分でお迎えに行っているのですから。
ここで、Bに物体が届いたという映像が、BからAへ伝わるまでの時間をt2とすれば、
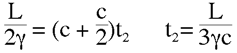
です。つまり、式(A)の時間というのを、地球上にいる観測者が計算すると、t1+t2となります。また、時間の遅れを考慮すれば、1/γ倍を掛け算して、次のような関係式、
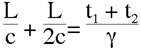
が出ます。後はt1とt2に式を代入してこれを解くだけです。
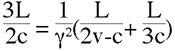
ここで、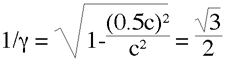 より
より
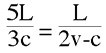

という事で、地球上から見た物体の速さは0.8cとなり、この章のタイトルにあるように【0.5c+0.5c=0.8c】となりました。
速度が出れば月に届くまでの時間もすぐ出るので、こちらの計算は割愛します。
ここでの計算をもっと一般化すれば、相対論での速度の合成則が出てきます。数値を入れずに全て記号で計算しなおすだけでいいのでそんなに難しくはないでしょう。
この計算の要は、ロケットのローレンツ収縮はもちろんのこと(著者はことごとく忘れていますが)、B点に物体が届いた事をAにいる観測者が知るにはBへ届いた物体の映像がAに届かねば、Aは判断できないという点にあります。この時、地球上の観測者は『この映像をAが迎えに行っている』と観測し、ロケット内では『静止している』とみているのでこのような事になります。この考えを更に発展させれば、同時刻の相対性の概念が出てくるのです。
ここで述べた問題も、特殊相対論入門の本の演習問題に必ず登場するのではと思います。計算としてはそれほど難しいものではないですし、著者が理解できなかったとは思えない部分です。
もしかすると、著者は本当に教育的指導としてこの本を書いたのかなとも思えます。つまり、わざと間違えて、読者に考えさせるという手法ですね。
教育現場では結構あるんですよ。先生がわざと間違えて見せて、生徒に指摘させる。そして生徒自身にどこが間違っているか解かせるという方法は…。先生は道化師役にまわる訳です。
もしそうだとすると私は『まんまとハメられた』事になるわけですが(^^;)。
同時刻って存在しない?
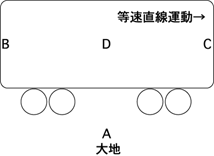 この章は単に著者の認識違いです。図のように列車が走っていて、BとCで同時に光を発すれば、DにとってCは近付いている光だから、DはCを先にみると著者は主張しています。
この章は単に著者の認識違いです。図のように列車が走っていて、BとCで同時に光を発すれば、DにとってCは近付いている光だから、DはCを先にみると著者は主張しています。
もちろんです。相対論はそれを否定していません。ただし、Aにとっての同時という注釈が必要ですが。
続けて著者は、
列車内のDにいる人がBとCの光を同時にみる場合、大地にいるAという観測者はCの光の方が先にくるように見えるなんて事は有り得ないと主張しています。
もちろんです。列車内のDに光が同時に届くのに、外から見たらCの光が早く届いて見えるなんて馬鹿な話はあり得ません。相対論でも同じ主張を元に理論を組み立てています。
結局のところ、著者は相対論と同じ結論に達しています。ただ違うのは著者は相対論の主張を誤って認識しているという点です。よって、この章で著者が自分の主張をすればするほど、相対論の主張をバックアップしている事になっています。なんだかよく分からない章です(^_^;)。
ちなみに著者がこの章で『否定しようとしているモノ』は何かと考えると、昔NHKでやっていた『アインシュタイン・ロマン』という特集の2作目で犯した間違いの追及なのです。この放送では確かに著者が指摘しているような間違った列車の思考実験のアニメが流されたのでした。よってこの章に関しては(著者がNHKの間違いを相対論の間違いと勘違いしている点を除けば)、賛同する部分もあります。間違った相対論の認識を打破するためにももっと主張してもよいかと思うくらいです。
ちなみに『アインシュタイン・ロマン』の間違いは最初の放送だけで、その後の再放送という名のリ・メイク版では直されていました。この指摘がNHK出版の雑誌に連載されていたというのは気の効いた皮肉です。
同時とは?
この章も著者は、相対論に反論するとしながら相対論の援護をしています。著者の説明は相対論の主張そのものです。
ただし、著者は、
光もガリレオの相対性原理に従うべきだとするアインシュタインの考え
と書いているように、アインシュタインの考えを誤解している(アインシュタインはガリレオの相対性原理を否定しているのですから)だけで、主張している事はアインシュタインと同じです。
既に何度も書いているのですが、このような誤解は、著者がアインシュタインは『光をボールみたいに考えている』と思い込んでいるために生じています。まあ、ある意味、著者の勘違いはブレが無く、首尾一貫して間違っているので、非常に分かりやすく、指摘しやすいというメリットがあります。
出来事の順序が逆転する?
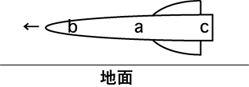 まず、図のように左向きに走っているロケットを考えてその長さを測る方法が間違っていると著者は反論しています(本では地面ではなく宇宙ステーションになってます)。
まず、図のように左向きに走っているロケットを考えてその長さを測る方法が間違っていると著者は反論しています(本では地面ではなく宇宙ステーションになってます)。
bとcにはフラッシュが取り付けてあります。このフラッシュは強烈なので、一度光ると地面のその部分に焼け焦げの跡を作ります。さて、著者はこのフラッシュを同時に光らせた場合どうなるかという考察をしていますが、aにいる観測者にとってフラッシュが同時に見えるのか、地面にいる観測者にとって同時に見えるのか述べていません。著者が述べているように光速は光源の運動によらないという主張を通すならば(これは特殊相対論の公理でもある。著者は勘違いしているが)、どちらの観測者にとって同時なのかを説明せねばなりません。
つまり、aの正面の地面にいる人が見て同時にフラッシュが見えた場合は、移動する観測者aにとっては、bからの光をお迎えに行き、cからの光を逃げながら受け取るので、同時には見えません。これは【同時刻って存在しない?】の章で著者自身が言明していることです。それをこの章では、
いろんな間違いが指摘できますが、まず、先に述べたように「ステーションに同時刻に光が到達するためには、異なった時刻に光を発しなければならない」というくだりです。そんな事をすれば、ロケットは動いているのですから、足跡が短くなるのは当然です。
と反論(?)しています。特殊相対論はこの
当然の事を述べているに過ぎません。まさにこれが
同時の相対性というやつです。
『ステーションに同時刻に光が到達するためには、
aの観測者が見て異なった時刻に光を発しなければならない』という、著者も言明し、なおかつ、当然と述べている事しか特殊相対論は言っていません。
時刻の逆転
ここでの著者の主張の1つは当たっています。
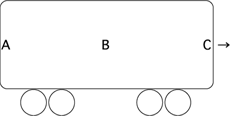
同じ場所で起きた二つの出来事の前後関係が崩れることは絶対にない。つまり中央のB点で二つのフラッシュを左右に取り付けて同時に光らせた場合、列車がどのようなスピードで走りながら観測してもフラッシュは同時に光ることはまぎれもない事実てある。
というある相対論の本の主張に対し、
二つのフラッシュということは、もう同じ場所ではないのです。離れた地点です。中央のB点というのは一点しかありません。左右にフラッシュを取り付けてというと、もう同じ場所ではないのです。
と著者は反論します。その通りです。が、これは著者が言うような
重要な間違いなんでしょうか?
相対論の書かれたその“ある本”には、まず最初に明らかに距離の離れたAとCという部分に置いたフラッシュの同時性について述べたあとに、Bのそばの二つのフラッシュなら、どの観測者から見ても同時だと比較して述べているわけです。確かに『二つのフラッシュ』ならば本当に同一の場所に置くことはできませんので厳密には違います。
でもそれは概念的な問題を述べているのであって、著者のこの発言は単なる上げ足取りに思えます。2つのランプを厳密に同一場所に置くことが不可能なのは間違いないとしても、文の初めに『同じ場所で起きた二つの出来事の前後関係が崩れることは絶対にない』と述べてあるのですから言いたい事はわかる筈です。
明らかに、AとCという離れた2点と、B近傍の2点の差異を対比して述べているのです。
なお、その後の著者の反論も、ほぼ相対論の主張と同じです。特に最後の方の、
…光の速度は往と復とで見掛け上変化するため、観測者によってAが先になったり、Cが先に見えたりします。しかし、それは事象の因果関係が逆転したわけでもないし、時刻の逆転が起きたりしたわけでもありません。きちっと順序だった計算ができる現象です。
という部分は
特殊相対論の主張そのものです。因果関係が壊れるとか、時刻の逆転がある等という事は一切ありません。因果律の崩壊が無いように組み立てられているのが特殊相対論ですから。
さて。一連の【同時刻って存在しない?】、【同時とは?】、【出来事の順序が逆転する?】、【時刻の逆転】について述べてきましたが、この4つの章は、相対論の主張をそのまま擁護しているにも関わらず、それを相対論の主張ではないとして論破するという、何だかよく分からない方法で反論されています。
で、著者の話で納得する読者というのは、『著者が否定している論理展開が相対論の主張だ』と思う人ですね。著者が否定しているものは相対論でも否定しているものであるので、『著者の主張だけ見ればもっともな部分が多い』のは当然なのです。
時計の遅れ
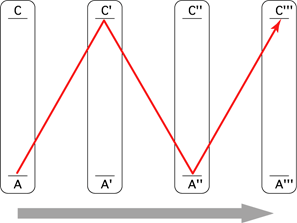 ここでは、大抵の相対論の通俗本にある時計の遅れの説明に対する反論が述べられています。
ここでは、大抵の相対論の通俗本にある時計の遅れの説明に対する反論が述べられています。
ある宇宙ステーションにAとCの対になった鏡があって、この鏡が横に動いている(図の→の方向)場合、光はA→C'→A''→C'''と動くから、AとCを静止していると見る系より光の道筋は長くなります。光速は慣性系である限り常に一定なのですから、この光の道筋が伸びた分だけ光の移動に時間がかかり、その結果、時間の遅れが計算できるという、相対論の通俗書ではよく出てくる話への反論です。
著者は今までの持論の繰り返しで、『Aから出た光はCへ行きC'へは行かない。よって、C'に行くという主張は作り話だと主張します。作り話という主張が何らかの実験に基づくものならばよいのですが、そのような主張は見られません。C'へ行くという事は、以前シンクロトロン放射光について述べてますから、C'へ行くという事は実験に基づいています。
もっとも、アインシュタインがこれを思い付いた時はそのような実験結果はほとんど無かったので『どちらが正しいか』という結論は当時は出てませんでした。
実験事実云々を考えず、論理的な話のみを考えても、著者の主張は相当破綻しています。というか、著者が思い込んでいる『相対論の主張』が滅茶苦茶なのです。例えば、次のように相対論は述べていると著者は主張します。
それに、相対性理論によれば、静止と等速直線運動はとは区別できない、とされているのですから、ステーションが等速直線運動をしていれば、光はAとCを往復するはずでしょう。
著者は、ステーションが静止していた時にA→Cと光が行くのならば、ステーションが等速直線運動していてもA→Cへ光が行くと主張しているのが相対論だと
思い込んでいるのです。それも、ステーションの脇を等速直線運動で通過するロケットから見た場合を想定して、このようなことを述べています。つまり、ロケットがステーションに対して動いていようが、動いていまいが、関係なくステーションは宇宙に浮かんでいるのにも関わらず、
ロケットの状態によってステーションの光が鏡に向かったり向かわなかったりすると述べているのが相対論だと思っているようなのです。
そんなことを述べている相対論の教科書があったら教えてもらいたいです。逆に言えば、もしもそのような説明がされていた場合、私も著者と同じように…
とても人をバカにしたというか、子供だましの説明
だと感じます。くどいですが、問題なのは、著者が
これが相対論の説明だと思い込んでいる点なのです。
ついでに、余談ですが、光速近くに走る素粒子についての面白い話がありますので引用しておきます。
高速電子を泡箱や霧箱という検出器に入れると、軌跡に沿ってスジができます。このスジは、電荷を持つ物体が傍を通った為に、その周囲の分子がイオン化し、それを核にして霧滴や泡が成長するからです。飛行機雲を類推してもらえばいいでしょう。電子が速くなってくると、ある分子の傍に電子が滞在する時間が少なくなります。よって、傍の分子がイオン化する前に電子が通りすぎてしまう場合も多くなり、軌跡が薄くなります。
で、ドンドン速くなるとドンドン薄くなるかというとそうではなく、ある程度速くなるとまた軌跡が濃くなってきます。何故かというと電場そのものがローレンツ収縮を受けて、進行方向の横方向へ電場が縮み、横方向の場が強くなるからです。このように光速に近付くと電子そのものの性質が変わってくるため、横に出るべき光が前に偏って出るなんて事がおこるのも不思議ではないのです。
次に著者の矛先は『光を使わなくても(鉄砲の弾のようなものでも)時間の遅れは説明できる』という相対論の主張に向けられます。この弾丸による説明の部分は、著者のように相対論について大きく外しているのは例外としても、結構よく勘違いされる部分です(光のみが時間の遅れを説明できると勘違いしている人が意外に多い)。よって実際に計算してみる事をお勧めします。
で、著者の反論はこの説明に対し、直接的な反論を避け、次のように述べています。
いちばん気になるのは、ここでも相対性理論の正しさを示そうと言いながら、相対性理論による「速度の合成則」や「質量の増加」、「物差しの短縮」を平気で使っていることです。そういうものを使った上で、時間の遅れを説いているのだから、もう何をか言わんやです。上の考察を全部きちっとニュートン力学的に、つまりガリレオの相対性原理にもとづいて計算すれば、時間の遅れなど出てきません。
ニュートン力学とガリレオの相対性原理を使って時間の遅れが出てくるわけがありません。ニュートン力学と相対性理論とは結果が異なっているのですから、前提も異なっていて当たり前です。
また、「速度の合成則」を使って「時間の遅れ」を出すという方法が間違っているいう主張も変なものです。もし『ある部分でニュートン力学を使いながら、一方で時間の遅れを採用する』なんて事をしていたら確かに変ですが。
ここで言う『相対論の正しさを示す』というのは『相対論自身が無矛盾である』という事を示すものです。ニュートン力学と相対論の結論が違っていて『どちらが正しいか?』を比べるのは実験的手段しか存在しません。
ニュートン力学では時間の遅れは無いし、相対論ではあるという異なった結果がでる。双方とも自己の論理が無矛盾ならはどちらも『数学的に正しい仮説』です。後は『自然はどちらの理論を採用しているか(あるいはどちらも採用していないのか)』は実験によって決められます。実験によってニュートン力学は敗北したという事であり、ニュートン力学に理論的な不手際が発覚した為に敗北したわけではありません。
余談になりますが、一般相対性理論の方はまだまだ対抗理論がありまして、先に述べたブランス−ディッケ理論(風前の灯し火)だとか、ローゼン理論(よく知らない^^;)だとか、成相理論(一般相対論を近似として内在しているから呉越同舟?)だとかあるわけです。そして、それぞれは全て『数学的に正しい仮説』であり、理論展開に矛盾があるわけではありません。既に消えたホワイトヘッド理論だってそうです(この理論だと銀河によって潮汐が生じるのでボツとなった^_^;)。
それからもうひとつ。よくある勘違いの一つですが、著者は次のような反論もしています。素粒子の振る舞いにおける時間の遅れの反論として、
…私は素粒子の衝突力学に、等速直線運動の慣性系での理論である特殊相対性理論を利用していることに苛立ちを覚えています。
と述べるのですが、著者が特殊相対性理論の参考書(入門書でよい)をめくったらもっと憤慨するでしょう。いきなり
特殊相対論的力学等という加速度なしには考えられない力学の話が出てきますから。やっている事は対した事ではなく、速度vに対する式が出ているのだから、それの時間微分が加速度だろうというそれだけの話です。ニュートン力学も単なるF=maという加速度のみを扱った理論を積分してvの式にしたりxの式にしたりしていますし、それと同じです。
第一、F=maを、
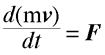
と、運動量の時間微分で表すというニュートンのやり方も単なる仮説です。著者の論法でいけば、『ニュートン力学は文字通り“力”しか扱えない筈なのに、速度の式などに使うとはもっての他だ!』・・・てなことになってしまいます(^_^;)。
ただし、『特殊相対論の話を時間微分して加速度を扱えるように拡張する事が可能か否か?』という事は実験により確かめられねばなりません(数学的には無矛盾ではありますが)。そして、それらが素粒子実験でドンピシャと当たっているからこそ、現在でも特殊相対論は使われているわけであり、逆にニュートン力学的では答えが合わないから棄却されたという、それだけの話です。
原子時計の遅れ
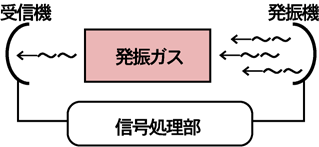 この章では原子時計の話がでています。原子時計の機構を簡単に説明します。基本的には電波発信&受信装置に毛が生えた程度のものです。
この章では原子時計の話がでています。原子時計の機構を簡単に説明します。基本的には電波発信&受信装置に毛が生えた程度のものです。
レーザーやメーザーの発振を考えると分かるのですが、原子や分子にはそれ固有の吸収しやすい波長というものが存在します。吸収しやすい波長は、逆に励起されたガスがその波長を発するという事にもなります。吸収を利用したのが、太陽からの光に見られる暗線(フラウンホッファー線)のスペクトル解析であり、逆に光っているのはトンネル等にある黄色いナトリウム燈になります。
原子時計は、前者の特定の波長の光を吸収する現象を利用します。ある電波発信器からガスの入った筒へ向けて光(といっても未だ可視光線による原子時計は存在しないので、実際には電波)を発射します。その光が、筒の中のガスが吸収できる特定の光だった場合はそれを吸収し、受信器にはほとんど到達しません。しかし、ここで僅かでも波長がズレると、ガスは折角もらった光に触手を伸ばす事なく、そのまま素通りさせます。まあ非常に好き嫌いの激しいガスだと思えばよいでしょう。いや、好き嫌いがはっきりしていればいるほど、僅かなズレを検出できるので好都合です(原子時計にセシウムが使われるのは、もっとも好き嫌いが激しいからだと思って下さい)。
受信器に発信器からの光が沢山くるようになったら、それは波長がズレている証拠です。この信号を素早く処理し、そのズレを補正して発信器から出す波長を変えて、ちゃんとガスが吸収するように直します。後はこの繰り返しです。このようなフィードバック機構のついた発信&受信器というのが原子時計の正体です。
そして、この時計の精度は10
-11以下です。著者は地上1気圧の時の原子時計と富士山の上の0.67気圧の差によって
精度が変わる事を懸念していますが、例え電波の送受信回路がこれにより変化したとしても、フィードバック機構となっているのはガスそのものですから、恒常的な変化は生じ得ません。第一、1960年代に時計の基準として原子時計が認められたのは、気圧の変化等はもちろん、振動にも影響されない理想的な時計だからです。
著者は1960年代から数十年もの間誰も気圧の変化等における変化について指摘しなかったと思っているのでしょうか(^_^;)。そんな誰でも思うような単純な検定を受ける事なく、度量衡会議で標準時計としての原子時計が認められるようになったと考えているのでしょうか。
著者はこの原子時計を使った相対論の検証実験について次のように反論します。著者は富士山頂と地上とで、富士山の方が時計の進みが早い事を引用した後に、
・・・ジェット機に原子時計を乗せて何時間も飛ばしたら速い速度で時計が運動したから相対性理論によって時計が遅れた。計算値とぴたり一致した、という話。これもちょっと考えればウソであることがすぐわかります。富士山の頂上くらいで時計が進むと言いながら、ジェット機の飛ぶ高度では全く時計は進まず、遅れる方を計算してそれがぴたり合うのですから何をか言わんやです。
と述べていますが、これは著者の
単なる事実誤認です。多分、著者の述べている実験というのは、1975年9月〜1976年1月の間に行われた
メリーランド大学の実験か、あるいは
ハフェーレとキーティングの実験です(1971年10月)の事だと思います。
まず、メリーランド大学の実験から。
この実験は、飛行機に原子時計を積み、地上1万mを飛ばして、地上の時計と比べた実験です。もしこの実験について著者が述べていると仮定するならば、『飛行機に乗っている時計は遅れた』という結果は事実と異なります。実際の実験では、時計は進んでいます。結果そのものが違っていますから、著者の主張はこれだけで単なる事実誤認だと分かります。ちなみに、高度1万mを15時間飛ばした時の飛行機上の原子時計の進みは、47.1nsでした(この実験を5回行って平均を出しています)。
また、もう1つの著者の事実誤認は、著者が述べているように「ジェット機の高度では全く時計は進まず、遅れる方を計算して・・・」というような計算をしていないということ。
こんなミスをする筈がないでしょう。当然ながら、地上1万mを飛んだという重力効果(一般相対論的効果)と、飛行機の速度効果(特殊相対論的効果)の2つが計算されており、前者が機上の時計を進める働きをし、後者が時計を遅らせるという計算をちゃんとしています。重力効果によって時計は52.8ns進み、速度効果で5.7nsだけ時計が遅れたので、正味の時計の進みが47.1nsとなったのでした。
次に、著者の述べている実験がハフェーレとキーティングの実験だとします。
この実験は、2機の飛行機に原子時計を載せ(誤差を考えて4台ずつ)、それぞれ東回りと西回りで実験をし、地球の回転の効果を調べたものです。もちろんこの実験でも、速度による時計の遅れと、重力による時計の進みの両方が計算されています。その結果、地球上の時計と比べて東周りで-255ns、西周りで+156nsのズレが観測されました。もちろん、飛行機の高度や速さで値は変わるのですが、世界一周旅行をする時は東回りにしましょう。寿命がそれだけ伸びます。
今一度述べておかねばならないのは、これら原子時計のズレを計った実験は1度や2度では無いということです。この手の実験はマイケルソン・モーレーの実験と同様、多数の追試実験があるのです。さらに言えば、現在の世界標準時の精度は、これら相対論的効果を考慮しなければ正確な値が出ない程になっています。人工衛星程度の速度や高度の物体の場合、相対論的効果による時計のズレの影響は10-10程度の精度から現れます。これに対して現在の原子時計の精度は10-15です。10-15の精度で各国が標準時の運営や比較をしているのです。1970年代ならば、相対論効果を直接的に示す実験として注目されたでしょうが、現在は十万倍の精度で現実に時計が運用されています。
少し面白いエピソードが日経サイエンスの2004年12月号に載っていたので、引用します。現在、GPS衛星という正確な原子時計を積んだ衛星が地球上を回っており、この衛星を介して、各国の標準時の比較が行われていたりしているのですが、衛星打ち上げの際に次のような議論があったと言うのです。
1970年代、初期のGPS設計者のほとんどは軍事技術者で、当時、相対性理論に従って計器を修正するという考えは自明ではなかった。「当時、この考えは議論の的だった」と、顧問を務めていたアシュビーは回顧する。「修正しなければならないと考える人もいたし、その必要はないという人もいた」。設計者たちの意見が分かれたため、最初のGPS衛星は周波数補正なしで打ち上げられた。しかし、万一の場合に備えて、補正用のスイッチを持っていた。このスイッチをオンにしなければならないことはすぐに明らかになった、とアシュビーは語る。
要するに、GPS衛星を打ち上げた人たちは相対論的な補正なんて必要ないだろうと思っていたわけであり、
万が一必要だったらスイッチを入れればいいやという感覚だったことになります。どう考えても彼らは
相対論の信者ではありません。信じているか否かとは無関係に、実際に相対論的な補正は必要なのです。
弟が兄より歳を取る?
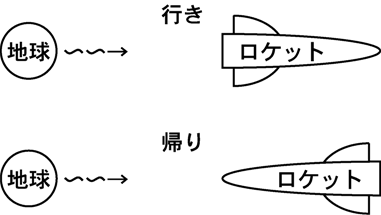 ここで登場するのは、いわゆる『双子のパラドックス』に対する反論です。ただ、この章で肴にされている双子のパラドックスの説明は、個人的にもあまり好きなものではないので(著者の反論とは全然別な理由で)、ちょっと複雑な心境です。
ここで登場するのは、いわゆる『双子のパラドックス』に対する反論です。ただ、この章で肴にされている双子のパラドックスの説明は、個人的にもあまり好きなものではないので(著者の反論とは全然別な理由で)、ちょっと複雑な心境です。
元の論は次のようなものです。
地球に弟が残り、ロケットに兄が乗り込みます。そして、地球から『1秒置きに』映像をロケットへ送ります。行きの時は、ロケットは離れていくので、地球からの映像は1秒では届かず、それ以上の間隔で受け取ります。帰りは、ロケットが近付くので、1秒より早い間隔で映像を受け取ります。
もしここで、行きの映像の滞りと、帰りの映像の過剰な送りが相殺し合って±0であれば文句はないのですが、相対論的なドップラー効果を考えると、2つを合わせても、送られてくる映像が多くなり、ロケットに乗っている方が歳を取らないという説明です。
具体的な話として、速さ0.6cの場合、行きは(1秒で1枚の映像である筈なのに)2秒に1枚を受け取り、帰りは、0.5秒に1枚受け取る。つまり、ロケット時間で行きが4年帰りが4年とすると、行きは2年分の映像を受け取り、帰りは8年分の映像を受け取るから、ロケット内では8年しかたっていないのに、映像は10年分送られてくるという説明です。
この説明では双子のパラドックスの真のパラドックス部分を説明していないと言えます。つまり、この論法をロケットが静止しているとして話すと、兄の方が歳を取る事になってしまい、やはりパラドックスだと言われる可能性があります。もっとも、実際に反転して戻ってくるのがロケットの方だとすれば、ロケットの反転前後で、ロケットから見た宇宙全体の風景が一変する(星の位置や距離、色が変化している)ことになりますが、地球にいる弟から観測して、ロケットが反転した映像を見た前後では、ロケット自身の色や大きさが変化して見えるだけとなります。
このような適切な補足を加えれば、ここで述べられているよう説明でも双子のパラドックスは理解出来ますが、誤解を生みやすいとは思います。
また、著者の反論にあるように、ドップラー効果を使った説明の場合、非相対論的なドップラー効果においても、映像が遅れて見えたりするのは当然ですから、それと誤解されやすいというデメリットがあります。もちろん非相対論的ドップラー効果の場合は、行きと帰りを足すと±0になり、双子の年の差は生じ得ません。
ちなみに、著者はこの後、非相対論的ドップラー効果を否定するという、訳の分からない行動に出ています。ドップラー効果についてもあまり知らないのでしょうか? 相対論的ドップラー効果を否定するのならともかく、非相対論的ドップラー効果を否定しているのです。
例えば(本質的な部分ではないので恐縮ですが)、
パトカーがサイレンを鳴らしながら遠ざかっている時、サイレンの音を半分しか聞いてないですか? 近付いている時、いっぱい聞きますか? そんなことはないですね。全部聞いているのです。
と書いています。完全に、非相対論的ドップラー効果…、簡単に言うと、高校で習うような
普通のドップラー効果を間違えています。サイレンの音は、遠ざかっている時は少ししか聞かず、近付いている時いっぱい聞くからこそドップラー効果が生じるのです。
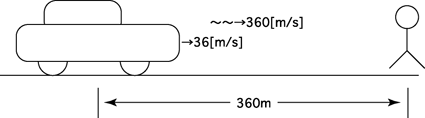 例えば図のように音速が360[m/s]の時に、360[m]離れた車から発せられるサイレンの音は1秒かかってやってきます。サイレンが1秒に1回鳴っているとすると、車が止まっていれば観測者は、やはり1秒に1回の音を聞きます。
例えば図のように音速が360[m/s]の時に、360[m]離れた車から発せられるサイレンの音は1秒かかってやってきます。サイレンが1秒に1回鳴っているとすると、車が止まっていれば観測者は、やはり1秒に1回の音を聞きます。
ところが、車が36[m/s]で走っているとすると、10秒後には車は観測者の傍まで来てしまいます。この10秒間に観測者が聞く音は11回なのです。要するに近付いている時、いっぱい聞くのです。
もし車が360[m]先に止まっていたままだったとすれば、この11回目のサイレン音は『1秒後』に聞く事となりますから、11秒間に11回のサイレンを聞いた事になり辻褄は合います。ところが、車が観測者の場所に来てしまうと、11回目のサイレンは目の前(耳の前?)で聞くことになってしまいタイムラグが無くなる。だから、サイレン音は10秒の間に11回聞こえる。これがドップラー効果の本質なのです。
なお、この議論は全く相対論と関係ありません。著者はこの事まで相対論の話だとして否定しているので、まあ矛先がアサッテの方向を向いている事になるのですが、時計の遅れ等をドップラー効果で説明すると、こういう勘違いが余分に増えてしまうと思われます。ですから、冒頭に述べましたように、この手の説明は好きではないのです。
ここで述べた非相対論的ドップラー効果を相対論的にするには、車の時計で1秒1回鳴らすとしているサイレンは、観測者から見た場合、車の時計は遅れているため、実際は1秒以上の間隔で鳴っているという事を付け加えた後、ドップラー効果を考えればいい。こんな二度手間をかけるほどのメリットは、この『ドップラー効果による説明』にはないと思います。
よって、著者が述べているように、
相対性理論では、いつも問題をすげ替えて、煙に巻こうとするクセがあります。
と勘違いされる可能性が高くなる説明法だと思われます(著者の問題認識とは全然違いますが)。
***
それからもう1つ。珍しく著者は、自らが反論している本の題名を書いています(その他の部分は「あえて書きません」とか書いてあるだけで、何という本の何処を指摘しているのか分からないようになっています)。
ここで登場する本は、旧ソ連の物理学者のデ・スコベリツィン氏の書いた『相対性理論における双子のパラドックス(1966年)』という本です。
で、著者の紹介によるとこの本は、
- 準光速で運動するロケットは実現不可能で、確かめられる議論ではない。
- 何億トンもの燃料がいるから絶対に遠い将来でも不可能だ。
- 宇宙線から飛行士を守るため、ロケットの壁を数メートルにしなければならないから実現不能だ。
と書いている(確かに書いてます)とし、著者独自の結論として、
これが本当の物理学なんでしょうか。そして実現できない事だから、兄弟のパラドックスなど問題にするな、と説いているのです。
と述べます。
著者のこの本の紹介部分だけ読むと確かにそうだと感じますね。が、実際は違います。幸か不幸か(^_^;)、私はこの本を持っています。そこで、デ・スコベリツィン氏がこのような発言を書いた背景を付け加えます。
まず、『実現不可能』と釘を刺しているのは、SFの著者があまりにも簡単にロケットを光速近くにまで加速する話を書いているので、それを牽制するために書かれているという事です。
その事は、『相対性理論における双子のパラドックス』の中の、次の一文を引用してくれば分かるでしょう。
SFなどの著者たちは、実際には実現不可能な光速に近い速さで飛行する装置を想定し、これに相対論を適応することによって得られる結論から導かれるパラドックスをあまりに強調しすぎる傾向がある。ある場合にはこれら著者たちは、彼らが想定する状況に対する限界を考慮せずにつぎからつぎへと空想的な仮説に基づいた議論を進めていく。
確かに、『現実不可能』と断定するのは誤解の元かも知れませんが、スコベリツィン氏は、ちゃんと核融合ロケットや光子ロケットの話も述べており、その実現性を否定している訳ではありません。
また、このような論が述べられているのは本の序章の部分であり、その前のまえがきには、
この部分は本書の主題とあまり関係がないので、とばして読まれてもさしつかえない。
と書かれており、続く第1章からは、双子のパラドックスの事について手を変え品を変え、あらゆる方向から取り組んでいます。
ページ数で言うと、序論はほんの13ページ、それ以降の双子のパラドックスに関する話題は、15〜186ページになります。
この本は、『実現できない事だから、兄弟のパラドックスなど問題にするな』などと書かれた本では決してありません。それとは逆に、この本の主題は、間違いなく兄弟のパラドックスそのものなのです。
著者の主張だけ見ていると、現実不可能とだけ書いてある本のように誤解されるかも知れませんが、それではあまりにもデ・スコベリツィン氏が可哀相です。著者はこの本の序章までしか読んでいないのではないかとすら思います。いや、逆に読了していてこの引用だったとしたら、悪意があって序章のみを引用しているとさえ感じられることになります。
せっかくなので、付け加えておきますと、この『相対性理論における双子のパラドックス』は、双子のパラドックスに特化しているだけあって、かなり突っ込んだ話題もあり、名著です。私は神田の古本屋(明倫館というそのスジでは有名)で見つけ、速攻で買いました。
光の横ドップラー効果について
ここでも、著者は『光は見えない』とか思考実験とまったく関係のない部分をつついています。飽きない人です。これに付き合うのは止めます。
この章でも、著者は(非相対論的な)ドップラー効果の結論を間違えています。相対論抜きで『自分の真ん前にまで走ってきた宇宙船から出た光は昔から言われているドップラー効果によって振動数が小さくなる』と述べています。
この結論は間違っています。高校の教科書を今一度見直せばよい。もっとも、著者は、高校で習う普通のドップラー効果を間違えていることが、前章で分かりますから、それはそれで
スジが通っていると言えるのかも知れません。
フィゾーの実験
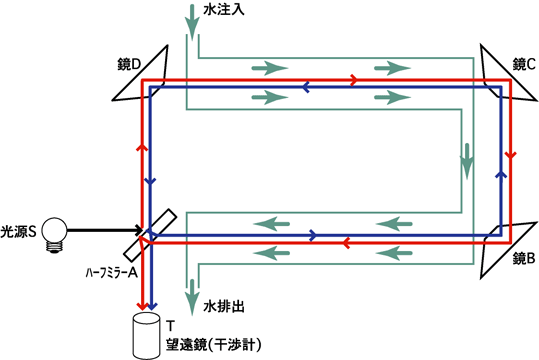 まず最初に、フィゾーの実験とはどういうものかを説明する必要があるでしょう。実はこの実験、ある意味、マイケルソン・モーレーの実験よりも重要だと言えるかもしれません。何故ならば、アインシュタインが特殊相対論を作った時に重視したのが、この実験の結果だったからです。
まず最初に、フィゾーの実験とはどういうものかを説明する必要があるでしょう。実はこの実験、ある意味、マイケルソン・モーレーの実験よりも重要だと言えるかもしれません。何故ならば、アインシュタインが特殊相対論を作った時に重視したのが、この実験の結果だったからです。
また、マイケルソンとモーレーも、このフィゾーの実験をマイケルソン・モーレーの実験の前年(1886年)に行っています。なお、フィゾーがこの実験を行ったのは1851年のことです。
この実験は、水などの媒質の移動によって、光が引きずられる効果を検証する目的で行われました。要するに、流れのある水中を光が進むと、水流に乗った光は速度が増し、逆流の場合は押し戻されるために減速すると考えられていたのです。ただし、完全に引きずられるわけではなく、部分的に引きずられるということがフレネルよって言われており、それまでの実験(エアリーの実験等)で証明されていました。どういうことかと言うと、静止した液体中を進む光の速度をwとすると、液体の速度が光の進む方向にvとなれば、光速はw+vになりそうに思われますが、実際はそうはならず、
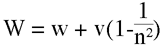
になることが知られていました(nは液体の屈折率)。
つまり、液体の流れの影響を全く受けなければ、光速はwである筈ですし、完全に引きずられるのであれば、光速はw+vですが、実際はその中間であったということで、一部だけ引きずられるという解釈が成り立ちます。このことを指摘したのがフレネル(1818年)だったので、(1-1/n2)の係数を、フレネルの随伴係数といいます。
話をフィゾーの実験に戻します。フィゾーは上図のような装置を考案し、実際にこの光速の変化を実験で示しました。
光は、ハーフミラーAで直進と上向きへと分けられた後、3つの鏡を経て再びハーフミラーAへ戻って干渉計Tへと到達します。光の経路の途中に2ヶ所の水槽通過部分があり、中の水が移動しています。2つの光経路を追って見れば一目瞭然なのですが、A→D→C→B→A→Tと行く光は、水槽部分で水流に乗ることになります。逆にA→B→C→D→A→Tと行く光は、水流に逆行します。これによって、水流の速度vの効き方が逆になるため、Tへ届く時間が2つの経路で異なるのです。ただし、最終的にこの実験で得られるのは干渉縞であるので、このままだと速度差を計測できませんが、水流の速さを変化させれば干渉縞がそれによって変化することが観測できるというわけです。
著者はこの章で、
フィゾーの実験は非常に重要な意味を持っています。それは光は真空中と、モノがある場所とでは光速度が変わってくることを示しています。そして媒質の運動によっても光速度は変化することを示しています。
と述べていますが、これは19世紀後半では常識でありますし(この実験は1851年に行われているのですから)、相対論もこれを否定したりしてません。著者は一体何に反論しているのでしょうか?
また、上述したフレネルの随伴係数の式を引用した直後に、
アインシュタインは液体中の光速度は液体が静止していていても、動いてても同一だと仮定しています。
と述べていますが、
どのように見ればこういう結論に辿りつくのか分かりません。液体中の光速度Wが、液体の速度vによって変わらないという主張ならば、
Wを示す式の中にvが入る筈がないという事は誰でも分かります。
第一、静止流体中の光速度も運動流体中の光速度も同じだったなら、

で終わりではないですか(^_^;)。わざわざ、「静止している流体の速度をwとする」なんて書く筈がありません。
ちなみに、フレネルの随伴係数の式による光速の変化は、相対論による速度合成則の一次近似から導く事ができ、このことは著者も書いていますが、これを示したのはアインシュタインではなく、ラウエです。どうやら著者は、アインシュタイン自身がこのようなこじつけを行ったと勘違いしているようですが…。
余談ですが、ラウエは師匠のプランクから相対論という新説に興味を持ち、遥々海を越えてベルンの特許局まで出向いたのですが、入り口付近にアインシュタイン自身がいたのにも関わらず、もっと立派な風体の人物だろうと勝手に想像して部屋の奥まで探しまわった挙げ句、やっと戸口にいたみすぼらしい人物がアインシュタインだと気付いたという逸話が残っています。
重力で光が曲がる
著者は『光に質量があるので重力で曲がる。これはニュートン力学で表される』と主張しています。
以前説明しましたが、『光に質量があった場合どの程度曲げられるか?』という計算は1801年に既に行われており、1911年にはアインシュタイン自身で計算されています。
著者はこの光の質量による曲がりを「とても小さいものだと思います」と単に述べているだけですが、アインシュタインは0.88秒と値まで出しています。一般相対論による再計算によると、曲がりはこの2倍であるという結果がでました。
さてどちらが正しいかと観測したら、一般相対論による結果の方が正しかったという事実があります。著者はこの事を知っているのでしょうか?
また、光が曲がるのはこういう重力作用が主ではなく、星間ガス等を光が通るために屈折するのだと説明しています。
まあ実際に地球の大気などで、水平線に見える太陽は34分23秒ほど浮き上がって見えます(大気差といいます)。ですから地平線に夕陽が見えている時は実際は既に地平線の下に太陽があったりします(既に沈んでいる太陽が見えているのです)。だから、著者の述べるような事は実際に有り得る事なので、これも実験によって確かめる必要があります。
その方法は著者自身が本の中で述べています。
私は前述したように、太陽の傍には無数の荷電粒子や、微粒子が集まっているので、それらによって電波が屈折したためだと思っています。もし空間が歪んでいるためなら、どんな周波数の電波でも一様に遅れる筈です。しかし、私の予想では、周波数によって、つまり波長によって曲がり方が異なり、遅れる時間も違ってくると思っています。これは光に対しても同様で、色の異なる光は屈折率が違うので、曲がり方が違ってくると予想されています。いつかきっと、この事は実証されるでしょう。
著者の主張は完璧です。光の曲がりが荷電粒子等の屈折によるものなのか、あるいは空間の曲がりによるものなのかは、
周波数の違う光や電波での曲がりを比べて見ればいいのです。
著者のように「いつかきっと・・・」ではなく、これは既に確かめられています。著者の予想に反して、どのような波長でも曲がりは同じでした。太陽周辺での光の曲がりは、昔は日食を利用した可視光線の曲がりを調べるものだったのですが、現在は電波望遠鏡で調べるのが一般的です。何故ならば、いちいち日食を待たずとも観測が可能ですし、VLBIを使ったより高精度な観測が可能ですから。
荷電粒子の屈折によるものなら、電波望遠鏡で曲がりを調べる段階で、大問題になっていると著者は思わなかったのでしょうか?
また、観測精度の飛躍的な向上によって、太陽もちろんのこと、木星や火星などの惑星周辺を通過した光の曲がりも観測されています。
皮肉な事に、相対論で太陽による光の曲がりを説明している本には、『一般相対論の重力による曲がりのよいところは、電波や光やX線を区別せずに曲げてくれるところである』とはっきり述べているものもあります。
もちろん、地球の大気や太陽コロナと言った、荷電粒子の屈折によるズレや、地球の自転の不整などで、観測結果に影響が出ます。どの程度かというと、理論値に対して、200分の1くらいの誤差でしょうか(D.S.Robertson and W.E.Carter : Nature 310 (1984) 572. とか)。
著者は自分で検証法を述べて、自分の主張の実験的間違いを暴露してしまった事になります。なにやらこれは、マイケルソンがエーテルの存在を調べるために、逆に自身の実験でそれを葬り去ってしまったのと似ています。
ただし、マイケルソンは、ちゃんと実験装置を考案し、その誤差精度を把握した上で科学的な結論を出しており、著者のように実験どころか計算もせずに『いつかきっと・・・』と述べるだけとは全然違いますが。
重力による赤方偏移の怪
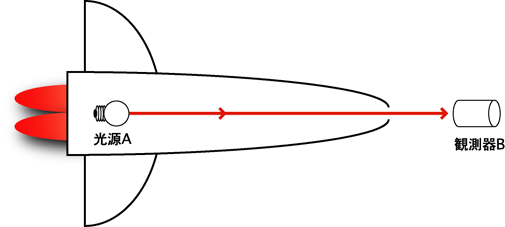 ここでも荷電粒子やダークマターがうんぬんと『光屈折説』を述べてますが、上述したように、既に実験的に否定されているのでここでは追及しません。
ここでも荷電粒子やダークマターがうんぬんと『光屈折説』を述べてますが、上述したように、既に実験的に否定されているのでここでは追及しません。
ただ、誰でも気付くであろうミスを著者がしていますので、ちょっと触れておきます。著者は、重力を振り切って出ていく光は波長が伸びるという、いわゆる赤方偏移を『等価原理』を用いて反論しています。
図のように、加速中のロケットがあるとします。ロケットの乗客は、ロケットが加速しているのか重力場の中に静止しているのか分かりません。これが等価原理です。次に、ロケットから光を出します。その時、この光の観測に矛盾があるというのが、著者の主張です。すなわち、
光は光源の運動には無関係に、一旦出たら、光速で空間を伝搬するものです。この光は宇宙空間を、ロケットであろうが、なかろうが、そんなことは無関係に進んで行きます。一旦光源から離れたら、周りに重力などない宇宙空間です。この光がロケットを離れる時、エネルギーを失うなど、ゼッタイにありません。
ロケットの進行方向の先の方のBで、この光を観測すると、近付きつつあるのですから、ドップラー効果によって、青方偏移するはずです。
わかりましたか? こんなに相対性理論は内部に矛盾をいっぱい含んでいるのです。
と述べるのです。わかりましたか?
著者の主張に内部矛盾がいっぱいあることが…。
著者の主張は、ロケットから出た光は、相対論では赤方偏移して波長が長くなければならない筈だけれども、周囲は重力のない宇宙空間なのだから、そんなことは絶対にあり得ないという点と、宇宙空間に置かれた観測器によって観測された光は、ロケットが近付きつつ出された光を観測するので、赤方偏移どころか青方偏移して観測されるという点になります。
「おいおい」と言いたくなりませんか(^_^;)。ロケットから見ると光の観測器は、ロケットに向かって落ちているのですから、ドップラー効果によって波長が短くなるのは当然です。地上で行われる実験の場合、メスバウアー効果を使った実験になりますが、光源および、この光の観測器は共に重力場中に固定されています。ロケットを使った思考実験であるならば、光源と光の観測器は共に、ロケットに固定されていなければなりません。
ロケットの外の慣性系にいる観測者から見ると、光源から出た光はドップラー効果により波長が短くなって出て行きます。そして、その光を観測器が受け取る時、今度は後ずさりしながら受け取るために、波長が伸びたように受け取ります。
問題は、この場合、赤方偏移が観測されるのかという事ですが、ロケットの固有長の縮みを考慮すれば、計算可能です。外部慣性系にいる観測者は、ロケットは次第に縮んでいくのを観測します(ローレンツ収縮)。当然ながら、ロケット前方よりも後方の方が速さが大きいことによって縮むのですが、この速度差が赤方偏移の原因になります。腕試しだと思って定量的に解いてみることをお薦めします。
なお、余談ですが、著者は本章の冒頭で、次のように述べます。
こじつければ、こんな事も予言でき、みんなをあっと言わせることが出来る例の一つに重力による光の赤方偏移というのがあります。アインシュタインが1911年(明治44年)6月に発表したものです。
普通、こじつけというのは、
観測後に理論と結果が合わなかった時にするものだと思います。観測前にこじつけるというのは聞いた事がありません。さらに、既に述べたように、
1911年の理論は間違いだということで否定されているのですが…。何というか、著者は詰めが甘過ぎます。
水星の近日点の移動
この章の話は個人的にも初めて聞くものですので、ちょっと評価できません。事実関係をご存じの方はお知らせ願います。
ここでは、例の水星が太陽を回る時に、近日点が次第にずれていくという事の説明をしています。現在では一般相対論による説明がなされているわけですが、著者はこれを否定しているのです。
著者の主張は次の通りです。
現在では、パソコン程度のコンピュータでも、一般相対性理論ではない、別の理論、多くはニュートン力学ですが、これで計算して水星の近日点の移動は説明がつきます。
・・・ 中略 ・・・
(アインシュタインが一般相対論で、近日点移動を説明したという話の後に・・・)
でも、その後太陽は円形ではなく、自転のため扁平になっている事がわかり、アインシュタインの計算は太陽は完全な円形だとしているので、どうも、この計算は怪しいということがわかってきました。それで、天文学者が太陽の扁平率から引力の摂動を考慮に入れてニュートン力学的に計算し直したら、殆ど誤差はなくなりました。でもまだ、ほんの0.5くらいの誤差が残っているのを、空間が歪んでいるせいだとして、現在にいたっています。
もしニュートン力学によって、43秒(一般相対論によって説明されたのは、100年当たり43秒の近日点のズレだった。ズレそのものは100年で574秒に達する)のズレのうち、0.5秒を残して残り42.5秒が説明出来たのなら、一般相対論はあっさり捨てられるべきです。現在に一般相対論が残る余地はこの段階で既に無くなっている筈です。
私が知っている論争は、『近日点移動がニュートン力学によって説明された』と言うものではなく、『ブランス−ディッケ理論によって説明された』というものです。
アインシュタインが円形の太陽を仮定した部分に間違いがあって計算が怪しいと指摘をしたのもディッケですから、著者はこの話を引用してきたのではないかと推測されます。
ただし、ブランス−ディッケ理論はニュートン力学的ではありません。『ニュートン力学的』という表現だと何だかよく分からないので言い換えると、『非計量理論的』とでもいいましょうか? 簡単に言えば時空を平らなままで計算しようという理論の事です。
『電磁場的』といってもいいかもしれません。電磁場の場合は場そのものが曲がったりせず、単なる力の作用する入れ物として存在していますから、計量理論が介在する予知がありません。
ですから、重力場も幾何学的にどうこう言う理論ではなくて、電磁場のような非計量的なものにしようという試みがありました。ニュートン力学への回帰を望む人も結構いたわけです。ただし、これらの試みは尽く失敗しておりまして、著者の言うように80年も誰も気付かなかったのではなく、尽く淘汰されてしまったというのが本当の話です。
逆に、電磁場も計量的な扱いができるように拡張しようと試みた人もいる訳です。有名なトコではアインシュタインの『統一場理論』なんてのがソレですが、一番最初にこの拡張に手を出したのは、H.ワイルのようです。1918年(一般相対論発表の3年後)ですから、すごく早いですね。ワイルは一般相対論の計量の線素そのものを一般化するためにベクトル同士の比較に接続場を導入したりしてます。ちなみに、このへんの努力は現在でも行われています(ゲージ場の話になります)。
で、ブランス−ディッケ理論ですが、ニュートン力学的ではなくて、一般相対論と同様曲がった時空を採用(時空の尺度が計量で決まる計量理論だった)し、かつそれにスカラー場を上乗せしました。
どちらかというと一般相対論に“トッピング”した理論です。テンソル場にスカラー場をくっつけているので、別名『スカラー・テンソル理論』とも言います。ここで、スカラー場の時空における寄与の割合を示したωなるものが導入されており、ωが大きな数になると一般相対論と同じになってしまいます。
ωの数を適当に取ると(ブランスとディッケはωは7くらいとした)、水星の近日点移動が、一般相対性理論より小さくなります。
一般相対性理論による予言は、近日点移動は43秒でしたが、ブランスディッケ理論ではω=5の時は、水星の近日点移動は40秒となります(ω=10なら41秒、ω=100なら42.8秒)。
ただ近日点移動は43.11±0.21秒と観測されていましたから、ω=7付近の値(40秒程度)では一般相対論の予言に負けます。そこでディッケ達が注目したのが、アインシュタインの計算方法では太陽の扁平率による補正がないという部分でした。
太陽の自転による扁平率を測定したところ、52kmほど赤道の方が長い程だとわかり、そこからこの扁平による水星の近日点移動の寄与が3秒。よって、実際に空間の曲がりによってズレているのは40秒だけとなり、ブランス−ディッケ理論の値の方が観測事実に近い! …という話になったわけです。
この扁平率の観測は1966年に行われて、ω=7とした時のブランス−ディッケ理論とピタリ合うという事になり、1960年代後半から70年代前半には、ブランス−ディッケ理論に関する論文(ブランス−ディッケ理論に基づく中性子星やブラックホール。ブランス−ディッケ理論に基づく宇宙理論等)が多数出たようです。
1970年代前半の物理の本を見れば、この時までに生き残っている重力理論は一般相対論と肩を並べてブランス−ディッケ理論も堂々と扱われてます(ω>6という注釈入りで)。当時の観測ではどちらが正しいかは分かっていませんでした。
その後、太陽の扁平率の観測が何度も行われ、1980年代初頭には扁平率はそんなに大きくないと観測されており、結局のところ、扁平によって生じる補正は0.5秒程度とされています。
・・・まさかとは思いますが、著者はこの0.5秒の誤差を勘違いしているのでは?
要するに、ここで言う0.5秒の誤差とは、近日点移動のズレは43秒だと思われていたのが、太陽の扁平の補正により、空間の歪みによるズレは、本当は42.5秒ではないかという疑惑が持たれたというものです。また、その他、太陽の光の曲がりの詳しい観測も行われるようになって、一般相対論の予言による値と観測値とが0.1%で当たるようになってきました。
ブランス−ディッケ理論では、ω=500くらいにしないと現象を説明出来無くなったのです。ωが大きくなると、ブランス−ディッケ理論は一般相対性理論に限り無く近くなりますから、それなら簡単な一般相対論の方がいいやという事で、最近はブランス−ディッケ理論は忘れ去られようとしている感じです。
ただし、科学者というのはトコトン突き詰めるのが商売ですから、現在でも扁平率のもっと正確な値を得るべく、太陽探査衛星計画(ユリシーズ計画)を進めています。ωの値の下限がもっと上になるようなら、さらに一般相対論が実証されることになります。
余談ばかりになってしまいましたが、どちらにせよ、ニュートン力学が、現在のままの形で復活するという事は、未来永劫ありません。
もしかすると、
現在では、パソコン程度のコンピュータでも、一般相対性理論ではない、別の理論、多くはニュートン力学ですが、これで計算して水星の近日点の移動は説明がつきます。
という著者の話を補足すると、
『一般相対性理論でない別の理論(→ブランスディッケ理論)、多くはニュートン力学ですが(→ブランスディッケ理論は含まれない)、これで計算して水星の近日点の移動は説明がつきます(→でも、説明可能なのはブランス−ディッケ理論であって、多くのニュートン力学の理論の方ではないよ)』
もしその通りだとすると、「多くはニュートン力学ですが」という注釈が、まるで近日点移動がニュートン力学で説明出来てしまうような誤解を生むので、真意(?)が伝わらずよくないですね(^^;)。
空間とは
この章は、単に著者の物理感を述べたものですから是か否かを言っても仕方がないので割愛します。
ただし、著者が抱いている『相対論感』も述べてありますが、これは明らかに相対論とは異質な概念です。著者が抱いている相対論のイメージというのは、しいて言うと『完全なるマッハ原理の世界』のようです。
ただ、そうだとすると、マッハ原理に引かれながら、全てのものを相対的に考えようとするマッハ原理には付いて行かなかった相対論よりも、マッハ原理により忠実に従おうとするブランス−ディッケ理論を支持するという行動はどうもよく分からなかったりします。まあ、単に知らないだけでしょう。
物差しが縮む怪
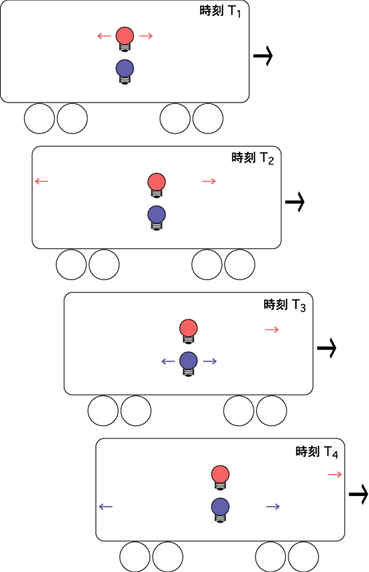 この章の間違いは、著者のみならず多くの人がひっかかる部分のようです。まずはここに出てくる思考実験を書きます。
この章の間違いは、著者のみならず多くの人がひっかかる部分のようです。まずはここに出てくる思考実験を書きます。
列車の中に2つの電球があります。この電球の光を外から見てみます。まず最初に上の方の電球が点灯しました。列車は右方向へ動いていますが、一度光源から出た光は列車の運動に左右されないので、列車後部に光が当たるのが先です。図では2コマ目で、光が列車後部に当たってますが、前方へ行く光は最後の4コマ目でやっとぶつかっています。
さて、下の方の電球は遅れて点灯します。3コマ目でやっと点灯し、4コマ目で、後方に光が当たっています。
そして、この結果から次のような事が言えます。
列車の外にいる観測者にとって、列車前方と列車後方に同時に光を届かせたかったら、列車中央の同じ位置に並んでいる2つの電球を別々に光らせねばならない…。
もちろん、2つの電球が左右に光を発射しているので、車体の前部に当たる光は、4コマ目の上方の電球の光と、6コマ目(描いてませんが)の下方の電球の光があります。同様に、車体の後部に当たる光は、2コマ目の上方の電球からのものと、4コマ目の下方の電球のものとなります。それぞれ2回ずつ光が当たるのが気になる場合は、電球を懐中電灯とし、上の懐中電灯は前方を向いており、下の懐中電灯は後方を向いているとしてやればいいでしょう。そうすれば、4コマ目に列車前方と列車後方に同時に光が届くのを観測できます。ただし、当然のことながら、車体前後に同時に届いた光は、異なる懐中電灯からタイムラグを付けて発射された光であり、同時に出た光ではありません。
要するに、この実験で言える事は、外から見て列車の前方と後方を同時に照らすには、中央の2つの懐中電灯のスイッチを押すのを、少しズラして押さねばならないという事です。
著者はこれを、次のように批判します。
この列車は等速直線運動をしている例ですので、アインシュタインによれば、光1は(同様に光2も)、列車内で発射されているのですから、列車の両端に同時に到達するはずです。なぜなら、アインシュタインによれば、光の速度は物体のいかなる運動にもよらないで一定の速度cで伝搬する、となっているからです。列車の中央に光源があるのですから、列車の両端に同時に光は届くはずでしょう。
これは、
列車内の観測者にとって当然の事です(光1とは上方の電球から出た光。光2とは下方の電球から出た光のことを示します)。上方の電球から出た光は、列車内の観測者にとって同時に前方と後方に到達しますし、下の方の電球の光も同様です。この事について特に間違いはありません。どうやら著者は、
この思考実験はそのことを認めていないと勝手に勘違いして批判しているようです。
また、もう1つ(1つだけではありませんがいちいち上げてたらきりがありませんので)単純なミスがあります。
このような列車の思考実験で出てくる光源は、ほとんど必ずといって言いほど、列車の中央にあります。何故ならば、ここから左右に光を飛ばせば、列車が止まっている(と感じる観測者の)場合は、左右に同時に届くからです。またその逆に、左右から同時に光を出せば、中央で同時に光を受け取るからです。要するに、説明するのに都合が言い位置なのです。決して中央で“なければならない”というものではありません。
電球が列車最高尾にあったとします。この時、前後同時に光を届かせるにはどうすればいいかというと、列車の長さを光速で割って、そのタイムラグだけ2つの電球の光らせる時間をずらせばそれでいいのです。単にそれだけです。
例えば地球上にいて、地上と月を同時に2つの懐中電灯で照らすにはどうしたらいいかと考えると、地球と月の距離は分かっていて光速で1.3秒かかるのですから、まず先に月を照らしておいて、1.3秒後に地上を照らせばいいだけですネ。まあ、地球と月のちょうど中間に観測者が入れば、いちいち計算せずとも同時に地球と月に向けて光を出せばよく話が簡単になりますので、思考実験の場合はこちらを採用するわけです。
思考実験のように勝手に観測者を配置できる場合はともかく、実際の場合は、観測者をちょうど中央に置くなんて事が不可能な場合が多々あります。例えば『各国に置かれた原子時計の時刻合わせ』なんてのがそうです。思考実験ならば、地球の中心から光を発すればいいのですが、そんな事は不可能です(^_^;)。
現在、基準となっている原子時計(一次周波数標準器)は7つありまして、フランス、スイス、イギリス、ドイツ、カナダ、アメリカ(には2つ)にあります。最近は、日本とアメリカが共同開発したNICT-01とかありますから、日本にもあると言ってもいいかと思います。
ここで、ヨーロッパ一帯とアメリカの時計を合わせるという目的で、わざわざ大西洋に船を出すような無駄なことはしません。どうするかというと…、理屈はすぐわかると思いますが、それぞれの距離を測量しておいて、イギリスからアメリカへ0時の原子時計の時報が届いた時、その時報は(アメリカ−イギリス間/光速)の分だけ遅れて届いているとして計算してやればいいだけです。実に簡単ですね。
話が長くなりましたが、著者はこのような時間合わせは不可能であると結論づけているのです。タイムロスを予め計算に入れて時刻を合わせるという方法に、著者は気付かなかったのでしょうか?
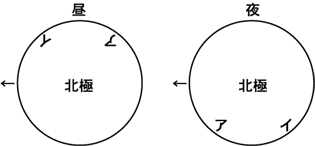 余談ですが、アメリカとヨーロッパの間の時刻合わせは常に行われていて、これら7つの時計の平均値が世界の標準になっています。で、もし著者の言うように、『慣性系と静止系は区別できる。静止しているのか等速度運動か区別できる』という事ならば、この時計を使えば検証可能です。
余談ですが、アメリカとヨーロッパの間の時刻合わせは常に行われていて、これら7つの時計の平均値が世界の標準になっています。で、もし著者の言うように、『慣性系と静止系は区別できる。静止しているのか等速度運動か区別できる』という事ならば、この時計を使えば検証可能です。
地球が秒速30kmで公転していて、地球そのものも自転しています。大西洋の真ん中に太陽がある時に時計合わせをしたとしましょう。次にその反対の夜中に時刻合わせをしたとしましょう。公転を考えると昼夜でイギリスとアメリカの立場は逆転します。昼間はイギリスの方が公転の前面になっていますが、夜はアメリカの方が前面です。
図は、地球儀を北極から見た図だと思って下さい。アがアメリカ、イがイギリスを示します。時刻合わせ信号がグリニッジから出ているとして(今はフランスに基準があるけど)、アメリカでそれを受け取るとすれば、昼間の場合は、アメリカがこの時刻合わせ電波をお迎えして受け取る事になりますから、時刻合わせが、早めになってしまいます。夜はその逆で遅れてしまいます(著者の主張によればね)。このズレは僅かですが、6μsのズレとなります。で、時刻合わせをしている標準時計の精度は0.1μsですので、もしこのような変動があれば即刻分かります。ですが、そのような変動(日変化)は今まで一切検出されておりません。
長さが短くなる公式
著者は『長さの縮みの説明に、時間の遅れの公式を使うとはけしからん』と主張しています。これらの公式にはどちらが主でどちらが従という関係はありませんから、理論の無矛盾性を説くにはどのように使ってもかまいません。というか、そもそも、長さの縮みと時間の遅れは別々に登場しているのではなく、ローレンツ変換に含まれているのであって、どちらか一方だけ採用するということができません。
著者の『証明になっていない』という言葉を、実験的な証明にはならないという意味だと解釈すればその通りです。これはニュートン力学でも他の理論でも同じ事です。だからこそ実験で確かめる必要があるのです。
光が止まって見える?
またまた『光そのものが移動している姿は見えない』という主張です。ここに書いてある事は一ヶ所を除いて当然の話であり、相対論でも当然ながら否定したりしてない部分です。
一ヶ所というのは、『相対論を使うと、光速で飛ぶ電球から出る光は超光速で飛ぶ事になってしまう』という話だけです。かなり前の方で著者のこの主張は間違っている事を計算したと思います。
列車が縮む
いままでもそうでしたが、著者は列車に乗って移動している人の見る立場と、外に残っている人の立場を分けずに考え、この2つを分けて考える相対論の説明を否定しています。
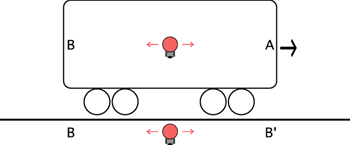 何度も出てきたものですが、プラットホームの中央から出た光が左右対称にBとB'に進みます。そして、列車に目をやると、列車は右向きに走っているので、後部に先に光があたります。著者の反論は、これを列車内で見ると(外で見れば、必ずBの方に先に届くのに)、AとBと同時に光が届くとするのはおかしい! というものです。
何度も出てきたものですが、プラットホームの中央から出た光が左右対称にBとB'に進みます。そして、列車に目をやると、列車は右向きに走っているので、後部に先に光があたります。著者の反論は、これを列車内で見ると(外で見れば、必ずBの方に先に届くのに)、AとBと同時に光が届くとするのはおかしい! というものです。
これは反論になっていません。特殊相対論は、2つの立場はどちらが動いていてどちらが止まっているのか分からないという公理から理論を組み立てているわけで、公理が常識に反すると述べても反論にはなりません。もちろんこの公理に従って計算すると、超光速度が出てくるというような事があれば反論は出来ます(無矛盾であるかの検証)。こちらの方も著者は色々と述べていますが、尽く的を外しています。
さらに、ホームで見た場合同時でなくても、列車内の観測者は同時に届いたと見るということを理論的に証明できます。AとBは距離的に離れた地点なので、この地点同士の事象が同時であったかどうかは、そこからの映像を目で見て確かめる必要があります。つまり、AとBでピカッと光が届いたという映像が、再び列車中央の観測者にまで到達した時に始めて、同時だったと確認できるわけです。この光の復路で、今度は逆の過程が生じます。つまり、列車中央から発せられた光は、ホームにいる観測者から見て、Aよりも先にBへ届くことになりますが、届いた光が戻って行くのは、BからのものよりAからのものの方が断然速い。結局のところ、2つの効果が相殺され、列車内の観測者へは同時に光が戻ることになります。
質量の増大について
素粒子の加速や減速を計算する場合に特殊相対論を使っていいのかという反論がまた載っています。速度の式を時間微分して加速度の式にするだけですので、簡単に拡張できます。
素粒子の運動の計算はもちろんこれで行っています。著者のような定性的な疑問だけでなく、実際に定量的に計算し、巨大加速器を動かしているのです。
これに対する著者の反論はつぎのようなものです。
典型的な例が素粒子の寿命とかその質量の増大とか言う、あのこじつけです。本当は流体力学や電磁気学、摩擦力学、衝突の力学などを駆使してコンピュータで計算すれば別の結果が出るのでしょうが、相対性理論を使って煙に巻いていた方が簡単でいいから、無理矢理こじつけているのです。
むりやりこじつけた間違った計算で、電子をうまく補足して実際に加速器が運転できますか?
自然が人間のこじつけに合わせてくれますか?
煙に巻くというのは、なにやら難しそうな事を述べて、具体的な計算や方法は何もしゃべってくれない場合の事を言います。電子の加速の仕方や、光速度に近くなった時の加速器の具体的なシンクロの仕方は、相対論の教科書に具体的に書いてあります。
ですが、この本では、本当は流体力学や電磁気学、摩擦力学、衝突の力学などを駆使してコンピュータで計算すれば別の結果が出るのでしょうがとだけ書いてあり具体的な方法は何一つ書いてありません。煙に巻くというのはこういうことをいいます。
ちょっと話は変わりますが、ロケットのように単独の物体が飛んでいる場合、質量が増大するというのは(著者の主張とは別の次元で)本当は間違っています。実際に重くなる訳ではありません。
E=mc2について
多々気になる部分はありますが、これは一言でケリがつきます。太陽や原爆のエネルギー源を説明せよと問うだけです。
それから、著者は静止質量を虚構のものとして述べています。やっぱり著者はマッハ原理に対して反論してますね。質量も宇宙全体に対して相対的であるべきだというマッハの主張はアインシュタインも反論した部分ですから、著者の主張はアインシュタインの主張と同じです。
回転光源のパラドックス
見掛けの超光速は存在するという事を述べているだけです。例えば月の軌道上にグルリとスクリーンを張り、地球から1秒1回転する懐中電灯で照らすと、そのスクリーン上の光は光速度以上に回っていると観測されるという事です。そりゃそうです。誰もそんなことを否定していません。
動いている光線スジは1つのものではなく別々のものですから、情報を伝える事はできません。ある場所から発した光が別の場所に届くからこそ情報が伝わるのです。懐中電灯をグルッと回しても、右に発射した光と左に発射した光は別物ですからなんの情報も伝えません。
ライトバリア
進行方向の真横に発射されたレーザー光は、どのような慣性系から見ても真横だと述べてます。この考えは既に実験で否定されています。以前もシンクロトロン光等でこういう事は実験的に無かった事を説明しましたし、電子や陽子の塊であるレーザーも同様です。
誤った理論展開
これが最後の章です(第二部もありますが、こちらは読み物ですので)。著者の思考が非常によく分かる文が載っています。著者は、アインシュタインがガリレオの相対性原理とマックスウェルの電磁気学をごちゃまぜにしたと言う事を述べて、
自然界には自然の摂理というものがあります。やってはいけないことは、やってはいけないのです。二つあるものは、二つあるのです。男性と女性なのです。動物と植物です。ニュートン力学とマックスウェル電磁気学なのです。
と続けています。
すなわち著者によれば、ニュートン力学とマックスウェルの電磁気学は
手を加えてはならないものと定義される事になります。著者にとってそれは
タブーなのです。
要するに『私はそういう“仮定”は認めない』と言っているに過ぎません。これでは「嫌だから嫌だ」といった某小説家みたいなモンです。
物理に限らず、科学にはタブーな仮説は一切ありません。タブーな理論値ならば存在します。実験結果と合わない理論値です。私は今回の書き込みで、相対論は正しいと述べたのではなく、著者の結論は間違っている事を述べただけです。
ある物理学者が、家の前にある馬の蹄鉄のおまじない(踏んで家に入ると幸福になるそうな)を他人から、「まさかそんなおまじないを信じている訳ではありませんよね?」とたしなめられた時に、次のように答えたそうです。
「もちろん信じてなんかいませんよ。でも、実際に幸福を呼んでくるようですがね…」
科学の理論なんてものは戦時中の不可侵条約みたいなモンで、信じる信じないは意味がなく、まだ守られているか否か?ということが重要なんです。

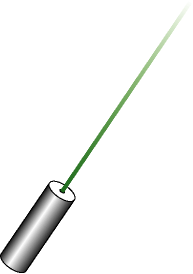 著者は横浜の花火大会において、光の速度を見たと述べます。そして光の速度は意外と遅いのだと結論づけています。
著者は横浜の花火大会において、光の速度を見たと述べます。そして光の速度は意外と遅いのだと結論づけています。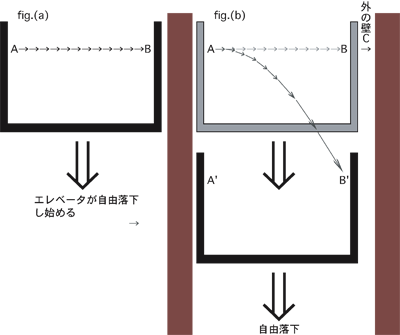
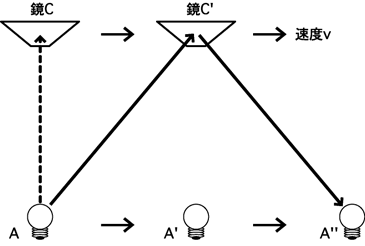 さて、ここからマイケルソン・モーレーの実験に対する著者の考えの間違いを指摘していきます。まずは著者の主張を述べることとしましょう。以下はその要約です。
さて、ここからマイケルソン・モーレーの実験に対する著者の考えの間違いを指摘していきます。まずは著者の主張を述べることとしましょう。以下はその要約です。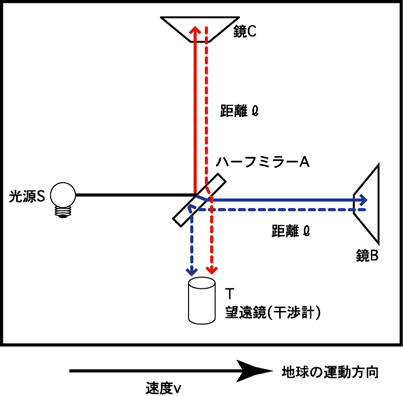 ここでマイケルソンとモーレーの実験のおさらいをしておきます。この実験は、光源から出た光をハーフミラーで90度異なる2方向に分離し、行く先にある鏡から戻った光を再び融合させて、その干渉縞を観測することで行われます。すなわち、経路1は、S→A→B→A→Tと進みますが、経路2は、S→A→C→A→Tと進みます。
ここでマイケルソンとモーレーの実験のおさらいをしておきます。この実験は、光源から出た光をハーフミラーで90度異なる2方向に分離し、行く先にある鏡から戻った光を再び融合させて、その干渉縞を観測することで行われます。すなわち、経路1は、S→A→B→A→Tと進みますが、経路2は、S→A→C→A→Tと進みます。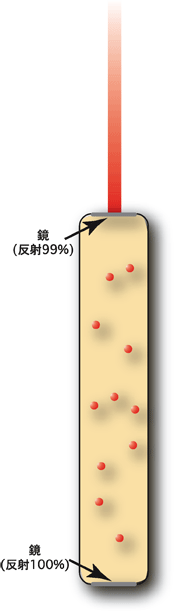 実はレーザーの場合は、発振機構まで遡って考えると、著者の間違いを思考実験だけで割と簡単に指摘することができます。
実はレーザーの場合は、発振機構まで遡って考えると、著者の間違いを思考実験だけで割と簡単に指摘することができます。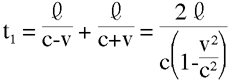 … 式1
… 式1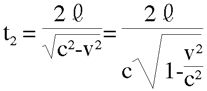 … 式2
… 式2
 … 式3
… 式3 … 式4
… 式4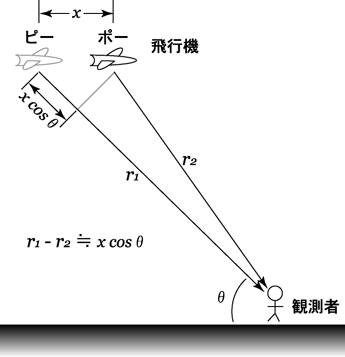 ただし、cosθが出ているので、高校生としてはちょっとややこしい部類の式になります。例えば『地上100m上空を水平に真っ直ぐ飛んでいる飛行機の音を地上から観測した場合の音のドップラー効果』を解くような問題には必須です。
ただし、cosθが出ているので、高校生としてはちょっとややこしい部類の式になります。例えば『地上100m上空を水平に真っ直ぐ飛んでいる飛行機の音を地上から観測した場合の音のドップラー効果』を解くような問題には必須です。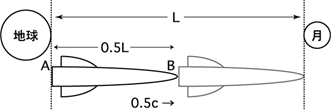 問題を要約すると次のようなものです。
問題を要約すると次のようなものです。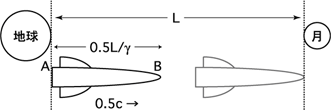
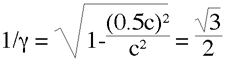
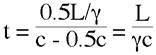
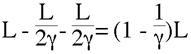

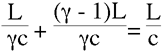
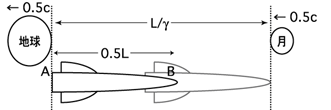


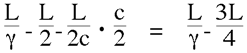

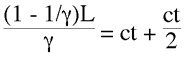
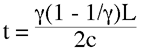
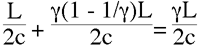
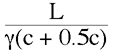

 …式(A)
…式(A)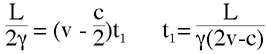
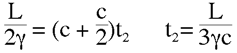
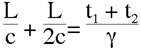
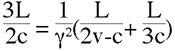
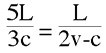

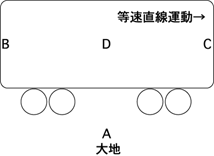 この章は単に著者の認識違いです。図のように列車が走っていて、BとCで同時に光を発すれば、DにとってCは近付いている光だから、DはCを先にみると著者は主張しています。
この章は単に著者の認識違いです。図のように列車が走っていて、BとCで同時に光を発すれば、DにとってCは近付いている光だから、DはCを先にみると著者は主張しています。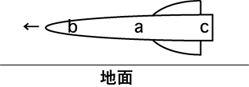 まず、図のように左向きに走っているロケットを考えてその長さを測る方法が間違っていると著者は反論しています(本では地面ではなく宇宙ステーションになってます)。
まず、図のように左向きに走っているロケットを考えてその長さを測る方法が間違っていると著者は反論しています(本では地面ではなく宇宙ステーションになってます)。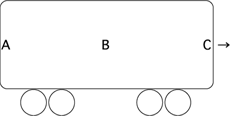
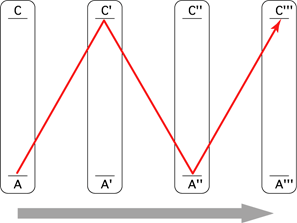 ここでは、大抵の相対論の通俗本にある時計の遅れの説明に対する反論が述べられています。
ここでは、大抵の相対論の通俗本にある時計の遅れの説明に対する反論が述べられています。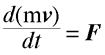
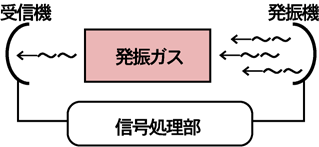 この章では原子時計の話がでています。原子時計の機構を簡単に説明します。基本的には電波発信&受信装置に毛が生えた程度のものです。
この章では原子時計の話がでています。原子時計の機構を簡単に説明します。基本的には電波発信&受信装置に毛が生えた程度のものです。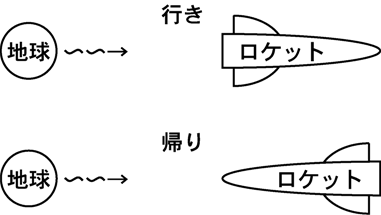 ここで登場するのは、いわゆる『双子のパラドックス』に対する反論です。ただ、この章で肴にされている双子のパラドックスの説明は、個人的にもあまり好きなものではないので(著者の反論とは全然別な理由で)、ちょっと複雑な心境です。
ここで登場するのは、いわゆる『双子のパラドックス』に対する反論です。ただ、この章で肴にされている双子のパラドックスの説明は、個人的にもあまり好きなものではないので(著者の反論とは全然別な理由で)、ちょっと複雑な心境です。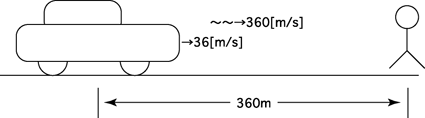 例えば図のように音速が360[m/s]の時に、360[m]離れた車から発せられるサイレンの音は1秒かかってやってきます。サイレンが1秒に1回鳴っているとすると、車が止まっていれば観測者は、やはり1秒に1回の音を聞きます。
例えば図のように音速が360[m/s]の時に、360[m]離れた車から発せられるサイレンの音は1秒かかってやってきます。サイレンが1秒に1回鳴っているとすると、車が止まっていれば観測者は、やはり1秒に1回の音を聞きます。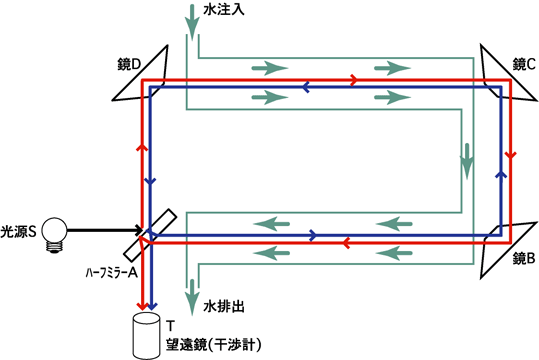 まず最初に、フィゾーの実験とはどういうものかを説明する必要があるでしょう。実はこの実験、ある意味、マイケルソン・モーレーの実験よりも重要だと言えるかもしれません。何故ならば、アインシュタインが特殊相対論を作った時に重視したのが、この実験の結果だったからです。
まず最初に、フィゾーの実験とはどういうものかを説明する必要があるでしょう。実はこの実験、ある意味、マイケルソン・モーレーの実験よりも重要だと言えるかもしれません。何故ならば、アインシュタインが特殊相対論を作った時に重視したのが、この実験の結果だったからです。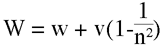

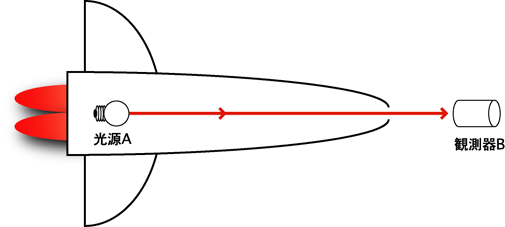 ここでも荷電粒子やダークマターがうんぬんと『光屈折説』を述べてますが、上述したように、既に実験的に否定されているのでここでは追及しません。
ここでも荷電粒子やダークマターがうんぬんと『光屈折説』を述べてますが、上述したように、既に実験的に否定されているのでここでは追及しません。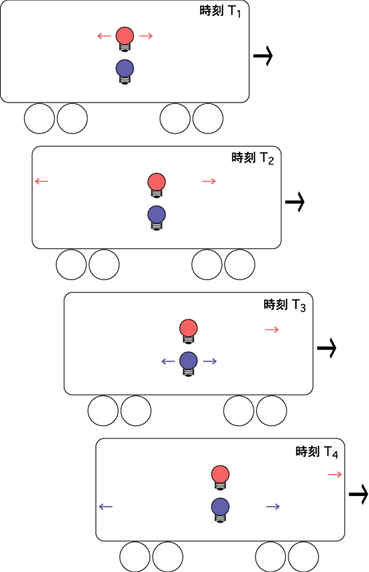 この章の間違いは、著者のみならず多くの人がひっかかる部分のようです。まずはここに出てくる思考実験を書きます。
この章の間違いは、著者のみならず多くの人がひっかかる部分のようです。まずはここに出てくる思考実験を書きます。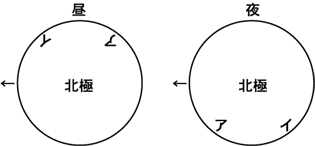 余談ですが、アメリカとヨーロッパの間の時刻合わせは常に行われていて、これら7つの時計の平均値が世界の標準になっています。で、もし著者の言うように、『慣性系と静止系は区別できる。静止しているのか等速度運動か区別できる』という事ならば、この時計を使えば検証可能です。
余談ですが、アメリカとヨーロッパの間の時刻合わせは常に行われていて、これら7つの時計の平均値が世界の標準になっています。で、もし著者の言うように、『慣性系と静止系は区別できる。静止しているのか等速度運動か区別できる』という事ならば、この時計を使えば検証可能です。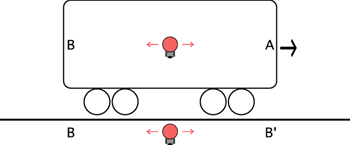 何度も出てきたものですが、プラットホームの中央から出た光が左右対称にBとB'に進みます。そして、列車に目をやると、列車は右向きに走っているので、後部に先に光があたります。著者の反論は、これを列車内で見ると(外で見れば、必ずBの方に先に届くのに)、AとBと同時に光が届くとするのはおかしい! というものです。
何度も出てきたものですが、プラットホームの中央から出た光が左右対称にBとB'に進みます。そして、列車に目をやると、列車は右向きに走っているので、後部に先に光があたります。著者の反論は、これを列車内で見ると(外で見れば、必ずBの方に先に届くのに)、AとBと同時に光が届くとするのはおかしい! というものです。